毎年4月8日、この日は各地のお寺で「花祭り」という行事が行われます。
花祭りは、別名「灌仏会」などとも呼ばれますが、はじめて聞いたという方も多いのではないでしょうか?
この記事では花祭りの内容や由来などをご紹介します!
花祭りとは

4月8日は仏教の開祖である釈迦が誕生した日とされており、その誕生を祝う行事が花祭りです。
この仏教行事は、インドから中国を経て日本に伝わったもので、推古天皇が在位14年(606年)に元興寺で行ったのが始まりといわれています。
花祭りでは、その名の通り、花をふんだんに飾った「花御堂」という小堂に釈迦の誕生時の姿をかたどった誕生仏を祀り、参拝者はこの誕生仏に甘茶をかけてお祝いします。
誕生仏の姿は、生まれてすぐ東西南北の四方向に7歩あるき、右手で天を左手で地を指して「天上天下唯我独尊(一切の生きとし生けるものはみな尊い命を持っている)」と唱えたときの姿を表しています。
甘 茶をかける理由って何?
では、なぜそんな誕生仏に甘茶をかけるのでしょうか?
甘茶は、一度飲むと不死になれるという言い伝えを持つ「甘露」の代わりです。
お釈迦様にまつわる伝説の1つに、誕生の際、天からやってきた龍が甘露の雨を注いだというものがあります。
そこから、釈迦の像に甘茶をかけることで釈迦如来が霊力を保ち続け、いつまでも釈迦から守り助けてもらえることができると考えられ、誕生仏に甘茶を書けるようになったのです!
また、甘茶を参拝者に振る舞う寺社もあり、これを持ち帰って飲むと身体が丈夫になるとか、甘茶で墨をすれば書が上達するというといった言い伝えがあります。
また、かつては甘茶ですった墨自体も力を持つと考えられており「千早振る卯月八日は吉日よ、神さげ虫を成敗ぞする」
(意訳:山の神を招き下して、害虫を成敗してもらうには良い日だ)
という歌を書いた紙を門口や室内に逆さまに貼って害虫除けのまじないにしていた…なんて話もるんですよ。

農村の花祭り「卯月八日」
かつて、農民たちの間では現在の花祭り(灌仏会)とは少し違う花祭りが行われいたのはご存じでしょうか?
灌仏会は、鎌倉時代には定着していた行事です。
しかし、それを行っていたのは、寺院であり、民衆にとって4月8日は仏教と関係のない風習を行う日でした。
それが「卯月八日」という風習です。
当時の農民たちは、気候が良いこの時期から農耕を開始するのですが、その前に野山へ出かけ、飲食をしたり花を摘んだりします。
この日が4月8日と決まっていました。
かつて、春になると山の神が里に降りて田の神になると考えられていたため、農耕開始する時期に山に神を呼びに行き、里に降ろすことで豊作を祈願しました。
この神を降ろすという行為が、山で摘んだ花を持ち帰り家に飾るというものだったのです。
主に、石楠花や山つつじ、卯の花や山吹といった花を、長い竹竿の先に取りつけて門口にさしたり庭に立てたりします。
これを「天道花」「高花」「夏花」 などと呼びます。
卯月八日の花にはヤマツツジやシャクナゲ、ツツジなど山に繁生した花が使われており、現在はツツジが飾られることが多いようです。
もともとはシキミをよく飾っていたと言われています。
このシキミは古くから神の依代という意識があり、現在でもよく仏前などに供えられる植物でもあります。
各地の風習として、奈良県には上部と中間に花をつけた竹竿の下に竹籠を結んで7日の夕方に立てる風習があり、下の竹籠にアマガエルが入るとその年は豊作になるという言い伝えがあります。
花は高く上げるほど良いとされ、地域によっては「花を高く上げるほど鼻の高い男の子が生まれる」「花の中にすりこぎ を入れておくと男の子が生まれる」という出産に関する言い伝えや、ひな飾りのように「花を片付けるのが遅れると女の子の婚期が遅れる」などといった言い伝えもあるようです。
この卯月八日の風習によって現在の生け花が生まれたという説もあります。
また、この花は竿を倒したあとも大切に保存しておきます。
家出や行方不明になる人がいたり、盗難にあったり失せ物がでたときに、保存しておいた花を燃やして煙の流れる方角を探すと見つかると言われています。

有名な花祭り
花祭りは、全国で行われているので気になった方はぜひ訪れてみてください。
ただし、花祭りを4月8日ではなく、その前後の日曜日に行うお寺も多くありますので、ホームページなどで事前に花祭りが行われる日を調べておくことをオススメします。
また、寺院によっては、花祭りの日に稚児行列という伝統的な衣装を着た子供が練り歩くという催しも開かれることがあります。
「稚児行列に参加すると健康に育つ」という言い伝えもありますので、お子様がいる方は参加してみてはいかがでしょうか?
築 地本願寺(東京)
築地本願寺では稚児行列や大道芸、移動動物園、たくさんの屋台も出店しており、にぎやかな花祭りを開催しています。
毎年3月上旬頃からホームページで稚児行列のお稚児さんを募集しています!
年齢は、概ね2歳~10歳までの参加が多いようですが、年齢制限はありません。
貸衣装・記念撮影・お土産代金を含む8,000円の参加料で申し込みをします。
毎年応募が殺到するようなので、お早めにお申し込みください。
神 戸妙昌寺(埼玉)
神戸妙昌寺では灌仏会の法要のほかに、参加者全員に木剣祈祷という木剣で背中や肩をさすって祈祷してもらったり、甘茶のこんぺいとうを頂くことができます。
また稚児行列も行っていますが、空きがあれば当日参加も可能のようです。
ジャンケン大会のプレゼントなどもあり、お子様も楽しめる花祭りを開催しています。
総 本山 智積院(京都)
総本山 智積院では、子どもたちの健やかな成長を祈る「子ども花まつり」を開催しています。
紙芝居や、僧侶による寸劇なども行っており、楽しく仏教を学ぶことができます。
その後お子様の額にお釈迦様の梵字の判子を押してもらい、その姿で法要を行います。
他にも、くじ引きや「うでわ念珠」をつくって遊ぶ時間もあるので、ご家族で楽しめる花祭りとなっています。
また、全日本仏教協会のホームページでは全国寺院で行われる花祭りを紹介しています。
ぜひお近くのお寺もチェックしてみてください。
おわりに
仏教行事というとなんだか堅苦しく感じてしまいますが、この花祭りは決まった作法などもなく、子どもでも気軽に参加しやすい行事です。
いつも見守ってくれている仏様に感謝をし、今年1年の健康を祈るような気持ちで参加してみてはいかがでしょう?
卯月八日にならい、家にお花を飾る日として4月8日を楽しむのも良いかもしれませんね。


日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。
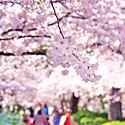
日本の春を代表するイベント、お花見。家族や友人と桜の下で楽しく食事をする人も多いのではないでしょうか。最近では、日本人のみならず、お花見目的で訪日する観光客も増えているそうです。そんなお花見ですが、いつ頃から日本で行うようになったかご存じでしょうか?

春の訪れを告げる風物詩「修二会」は、主に奈良のお寺で行われることが多い仏教の伝統行事です。仏教行事とはいえ、修二会ではすべての人々の幸せや国家の平和が祈念されているので、誰もが関係のある儀式といえます。今回は、修二会では何が行われているのか、有名な東大寺の修二会(お水取り)も踏まえながら詳しくご紹介します。

3月のカレンダーを見てみると、21日前後が赤くなっていますよね。遊びに出掛けるのも良し、家で寝ているのも良しですが、一体この日は何の日かご存知ですか? 「知ってるよ、春分の日だよ!」 という声が聞こえてきそうですが、それでは具体的に何のための日なのでしょう。





































































