皆さんはふるさと納税をご存じでしょうか?
ふるさと納税とは、日本における寄附金税制の一つです。
お好みの自治体に寄付をして、その寄付金額を居住する地方自治体へ申告することにより、寄付分が控除できるという制度です。
希望自治体に事実上の”納税”をすることにより、生まれ故郷を離れてもその地域に貢献することができたり、地場の特産品を採用することによって低迷する地域経済の活性化を図ることができるのです。
また、最も重要なこととして、伝統産業への知名度上昇と需要が発生し、地元の伝統工芸が活性化することへも繋がります。
各地方の自然の中で育まれた文化と伝統。
そこから発生した多くの伝統工芸品は、確かな技術をもった匠の技とともに、一つひとつ手間ひまかけて丁寧に生み出されていきます。
今回は、ふるさと納税の返礼品としてもらえる伝統工芸品をご紹介します!
鹿児島県霧島市の薩摩錫器のタンブラー!飲みやすさを考えたおしゃれなフォルムと錫の光沢が美しい
大人気テレビ番組「マツコの知らない世界」でも紹介された伝統工芸品、「薩摩錫器」のタンブラー!
薩摩錫器は、300年の歴史をもつ薩摩藩ゆかりの錫細工であり、鹿児島県霧島市を代表する伝統工芸品です。
江戸時代に薩摩で錫鉱山が発見され、錫器が作られるようになったといわれています。
第一次世界大戦の後、軍備を抑制する目的などから生産の縮小を余儀なくされますが、錫山工業組合は負けじと生産を続け、今では鹿児島の伝統工芸品として有名になり伝統を守り続けています。
見た目の上品な美しさだけでなく、錫にはイオン効果があると報告されており、ビールや焼酎の味がまろやかになるといわれています。
男性へのプレゼントランキングで常に上位になる酒器。
同じ値段で切子柄もあります。
どうぞ大切な人へのプレゼントとして贈ってみてください。
大分県日田市の日田杉を使った曲げわっぱのお弁当箱♪木の温もりと実用性で、ご飯がより美味しく戴けそう!
木目の優しさと、木の香りに満ちた伝統工芸品、「日田杉曲げわっぱ」のお弁当箱です。
見た目のかわいさに加えて、大きさも手ごろで仕切りもあり、とても使いやすい♡
大分県日田市のスギは古くから「日田杉」と呼ばれ、鹿児島県屋久島の屋久杉、宮崎県日南地方の飫肥杉と並んで、九州三大美林の一つといわれています。
そんな日田杉で作られた器は、耐久性にも優れ、軽量で持ち運びも便利です。
最近はInstagramでも大人気の曲げわっぱのお弁当箱は、男女問わずお使いいただけます♪
丸形のタイプもありますのでお好みの形を選んでくださいね。
この機会に、ぜひ日本ならではのお弁当箱をお試しください!

「曲げわっぱ」とは「曲物(まげもの)」とも呼ばれる、薄く加工した木材を曲げて作られる伝統工芸品のことです。
なめらかな曲線を生かしたお弁当箱やおひつなど、蓋付きの入れ物が製品として多く見られます。
特に秋田県大館市の「大館曲げわっぱ」は有名で、1980年に日本の曲物の中で唯一、国の伝統的工芸品に指定されています。

曲げわっぱとは日本の伝統工芸品の一つであり、古くから受け継がれる伝統的な手法によって職人の手で一つずつ丁寧に作り上げられる非常に奥深いものです。この記事では、曲げわっぱがどういったものかだけでなく、曲げわっぱの種類をご紹介します。
鹿児島県南さつま市の薩摩切子のおちょこ♪鮮やかな色のガラスと模様が美しい!
色鮮やかなガラスとカッティングが美しい伝統工芸品、「薩摩切子」のおちょこです。
鑑賞用にしたいくらい、まるで宝石のようなおちょこですよね!
薩摩切子は、鹿児島県の伝統工芸品の一つ。
無色のガラスの上に色ガラスを溶着させる厚みのある「色被せガラス」をカットして繊細な文様を付けていきます。
製作者はツジガラス工芸の職人・辻俊幸氏。
「ぼかし」や「カボッション」など独自のカットグラス技法で定評があり、これまでも受賞作は多数。
平成18年(2006年)には日本の伝統工芸をヨーロッパに広める取り組みに、ツジガラス工芸の薩摩切子が選ばれました。
そんな実力者が作ったおちょこで飲むお酒は、さぞ美味しいことでしょう…♡
石川県七尾市の輪島塗と山中塗のお箸・お椀セット♡漆の雅なお色がとっても上品!
艶やかな漆が美しい石川県の伝統工芸品、「輪島塗」のお箸と「山中塗」のお椀のセットです。
輪島塗は、下地に粘土粉や生漆などを混ぜて作る特殊な地粉を使うため、とても堅牢な漆器です。
山中塗はロクロを使用して木を加工する挽物という技法を使い、木目を生かしたデザインや金銀粉を使った美しい蒔絵が特徴的な漆器です。
山中塗のお椀は、能登七尾の風習として受け継がれている「花嫁のれん」をイメージした漆陶舗あらきのオリジナル商品です。
花嫁のれんとは石川県を中心にみられる、婚礼に用いられる特別な暖簾のこと。
そんな祝いの品をイメージして作られた「花嫁お椀」は、平成29年(2017年)に石川県観光土産推奨商品にも認定されました!
セットの輪島塗のお箸には蘭の紋様が描かれています。
お箸の先には食べ物がすべらないように加工を施してあるので、麺類やお豆腐などにも使いやすいのが嬉しいポイント♪
二種類の伝統工芸が一度に手に入るなんて、とても贅沢なセットですよね。
色は花嫁用の赤色と、花婿用の黒色がありますので、ご夫婦で揃えて使いたい♡

「石川県の食器」「石川県の器」といえば、多くの人が輪島塗や九谷焼、あるいは山中漆器を思い浮かべるのではないでしょうか。これらは伝統的工芸品の一つであり、昔から多くの人を魅了してきました。石川県には上記以外にも、「金沢漆器」と呼ばれる伝統的工芸品があります。今回は、この美しい「金沢漆器」について取り上げていきます。
鹿児島県西之表市の伝統工芸品、種子包丁は切れ味抜群。ストレスフリーで万能
しっかりした持ち手に、切れ味の優れた頑丈そうな刃の種子包丁。
熱した刃を丹念に手打ちし、薄い両刃に仕上げたので切れ味抜群!
見た目は重そうですが、意外と軽いので使っていても疲れません。
鉄砲が伝来してきたことや、海岸で多くの砂鉄が取れたこともあり、鍛冶は古くから種子島で盛んに行われてきました。
そこで紹介するのが、連綿と伝承されてきた鍛冶技術を受け継いだ職人たちによって作られた「本種子島包丁」。
鍛造、成型、焼き入れ、仕上げなど複数の工程がありますが、手作業で一本ずつ丹念に包丁を作っています。
あまりに切れ味がいいので、思わず切るものを探したくなってしまうかも!?
ぜひ一度、気持ちのいい切れ味をお試しください!
徳島県鳴門市の大谷焼!シンプルな外観と色味がとっても使いやすい♪
徳島県で230年以上の伝統を誇る焼物、それが大谷焼です。
大谷焼に使われる土には鉄分が多く、土の素朴さを感じるざらりとした手触りが特徴的です。
また、「寝ロクロ」といって、陶芸家の助手が下に寝転んで足で蹴ってロクロ台を回す技法で作られることが有名です。
そんな大谷焼のシンプルなお茶碗をご紹介します。
淡い色味のためとっても使いやすそうで、大谷焼独特の素朴さと雄大さがよく表現されている一品です。
爽やかな色使いのお茶碗が毎日食卓を彩ります。
プレゼントにも最適です。
富山県高岡市の高岡銅器の出世兜!健やかな男児の成長を願って
富山県高岡市の伝統工芸品である高岡銅器より、とってもクールな出世兜が登場!
高岡銅器の起源は江戸時代前期の慶長14年(1609年)、加賀藩主の前田利長が高岡の町を開いた際に町の繁栄を図るため、慶長16年(1611年)に現在の高岡市戸出西金屋から七人の鋳造師を現在の高岡市金屋町に呼び寄せたことがはじまりといわれています。
それ以来、高岡市で作られる銅器を「高岡銅器」と呼ぶようになり、昭和50年(1975年)には国の伝統的工芸品に認定されます。
現在では、日本の銅器生産の90%以上が高岡銅器だということをご存知でしたか!?
明治時代にはパリ万国博覧会に出品、世界的にもその技術が認められ名を広めました。
そんな歴史も実力もある伝統的工芸品で作られた、堂々と気品ある兜。
出世兜は端午の節句や誕生日などにお子さんが健康に育つことを願うためのものでもあります。
男の子のたくましい成長を願って、ぜひ飾ってみてください!
佐賀県有田町の有田焼キン肉マン箸置き!かわいさに思わず笑ってしまう…!
有田焼ではこんなユニークなものも作れてしまうの?!と驚いてしまうような商品をご紹介します!
日本の大人気漫画、「キン肉マン」の有田焼の箸置きです♪
全部で6個ある箸置きは、それぞれ人気のあった懐かしいキャラクター達ばかりです。
有田焼の認知度が低いと思われる世代へも、有田焼の魅力を知ってもらいたい!という想いから作られたそうです。
友人やご家族との会食の時などにぜひご活用ください。
きっと盛り上がること間違いなし♡
場が一気に明るくなりますよ!
福島県白河市の伝統工芸品、白河だるま♪見ているだけ癒される♡
まんまるの胴体にいかついお顔。
何故か見ているだけでほっこりしてしまうかわいだるまさん。
東北系のだるまに比べて丸みがあるのが特徴で、顔には縁起が良いとされている鶴、亀、松、梅や竹が模様化して描かれています。
それぞれどこに描かれているか探してみるのも面白いかもしれませんね♪
白河だるまが誕生したのは天明3年(1783年)、白河藩三代藩主の松平定信が市の発展を願い縁起だるまを作らせたことがはじまりだといわれています。
願い事を叶えてくれるとされる縁起物のだるま。
願掛けをする際は、まず願い事を込めながら左目を描きいれてください。
そして、願いが叶ったら感謝の気持ちを込めて右目を描きいれる…というのが正しい目の入れ方です♪
兜をかぶったユニークなデザインもあります!
あなたは何をお願いしますか?

手足のない丸い体と、ヒゲをたくわえた凛々しい表情が特徴の「だるま」。
年の瀬から新年にかけて買い求め、厄除けのために飾るのが一般的です。
また、だるまは大願成就の縁起物としても親しまれ、願掛けしながら片方の目を入れ、願いが叶ったらもう一つの目を入れることでも知られています。
大阪府貝塚市のさつまつげの和櫛♡古風なかわいらしさが漂う一品
とても古風でどこかかわいらしさが漂う和櫛。
つげ櫛とは、その名通り柘植(黄楊)の木から作られる櫛のことです。
柘植の木は年輪の幅が狭いことから肌理が細かく、弾力性がありながらも耐久性に優れているため、平安時代の頃からつげ櫛は日本で親しまれていました。
櫛の歯って細いので折れてしまいやすいのですが、柘植はその特質が櫛にぴったりだったというわけです!
このつげ櫛が作られている大阪府貝塚市は日本最古の櫛産地として知られており、江戸時代中期にはたくさんの櫛職人がいました。
つげ櫛工房「辻忠商店」は、現在もその伝統の技法を守り続けている工房です♪
辻忠商店では最高級の柘植から一年以上もの歳月をかけて作られています。
つげ櫛はプラスチック櫛に比べて静電気が起きにくく、枝毛や切れ毛予防になるので鞄に一つ入っていると、静電気で髪の毛が広がりやすい冬の時期には重宝しますよ♡
一本一本丁寧に手作業で作っているので、使うほどに馴染み、味が出てきます。
サイズ違いもありますので、自分に合った方を選んでくださいね。

毎日のヘアケアで美髪を保つのも大切ですが、使うだけで美髪を目指せる魔法のような櫛があるのをご存知でしょうか?それは、日本の伝統工芸品でもある「つげ櫛」という、木でできた櫛。近年では100円均一でも販売されているので、目にしたことがある方も多いかもしれませんね。
長野県野沢温泉村の蔓細工のカゴバッグは真夏に大活躍!
日本の夏はとにかく蒸し暑い…。
そんな時に活躍しそうな夏らしい蔓細工のカゴバック♪
通気性もよく、見るからに涼しそうですね♪
長野県の野沢温泉村の伝統工芸である、アケビの蔓を編んで作るアケビ蔓細工の技法を使って編み上げました。
天保元年(1830年)から約200年の歴史があり、昔は野沢温泉村のほとんどの人が副業にしていたという伝統工芸です。
本物の美しさと実用性を兼ね備えた伝統工芸によって作られた鞄。
ぜひ、夏の季節に使ってみてくださいね。
三重県伊勢市の手ぬぐいとハンカチのセットは身近に伝統工芸を楽しめる一品
こちらは、三重県伊勢市のふるさと納税の返礼品で、手ぬぐいとハンカチが5枚ずつセットになった品です。
江戸時代から降り続けられている伊勢木綿を和さらし製法という方法でさらに柔らかく仕上げた布は、肌触りがとてもいいんです。
さらに、柄は千年以上の歴史を持つ伊勢型紙を用いて染められたもの。
普段から伝統工芸に触れていたいという方にオススメの返礼品です。
使い続けることでどんどん手に馴染む楽しみも味わってみてください。
山形県鶴岡市の絵ろうそく!かわいいお花の絵はすぐに飾ってみたくなる♡
ろうそくにかわいらしい花模様をあしらった「絵ろうそく」は、庄内地方で300年の歴史をもつ伝統工芸品です。
庄内の和ろうそくが有名になったのは、庄内藩主・酒井氏が将軍に和ろうそくを献上する際に、道中で破損してしまったろうそくを江戸のろうそく職人では直せなかったため、庄内の職人・皆川重兵衛を呼び寄せて修正したところ、将軍から日本一と称されたことがきっかけです。
現在、和ろうそくを手描きで製造しているのは庄内地方に数軒のみであり、その中の一件である鶴岡の富樫絵ろうそく店2代目の富樫雄治氏は、平成8年(1996年)に国の卓越技能者として表彰された名匠でもあります。
そんな由緒あるお店の絵ろうそくを、贅沢なセットでお届けいたします♪
燭台もセットで付いてくるので、はじめての方もこれならすぐにお楽しみいただけます!
リビングのほか、ご先祖様のいるお仏壇に置いても素敵ですね。
田舎への帰省の時のお土産にもいいのではないでしょうか?

かつて照明として重宝された蝋燭は、今でも仏事やお誕生日ケーキなど私たちの生活の様々な場面で使われています。
蝋燭には、大きく分けて洋蝋燭と和蝋燭の二種類があります。
おわりに
いかがでしたか?
どれも思わず欲しくなってしまうような素晴らしい作品ばかりでしたね。
それぞれの土地の特色や歴史、文化的な背景から生まれた貴重な伝統工芸品。
皆さんから集められた資金は、各地域の活性化に関する様さまざまな事業に活かされることでしょう。
皆さんはどれに決めましたか?

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

































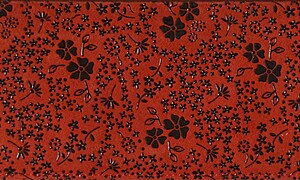





















![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)



















![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)


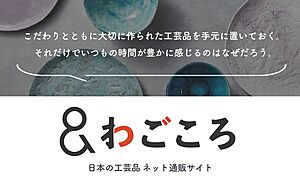




















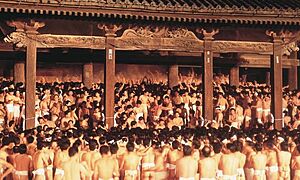











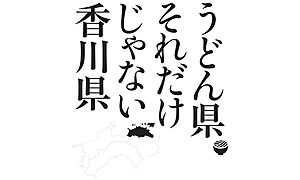













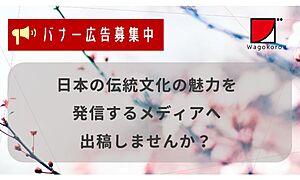




![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)


![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)
![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)





