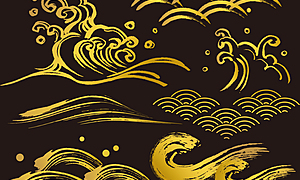「富嶽三十六景」などで有名な浮世絵師・葛飾北斎。
90年の生涯で3万点以上の作品を残した彼は、平成10年(1998年)に発行されたアメリカのフォトジャーナル誌「LIFE」にて、“この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人”に日本人でただ一人選ばれました。
世界で最も知られた浮世絵師といっても過言ではない葛飾北斎ですが、実は江戸時代後期を代表する奇人としても知られています。
特に引っ越しの回数は、生涯でなんと93回!
彼の奇人ぶりを語るエピソードとしてよく語られます。
この記事では、葛飾北斎を「引っ越し」という視点から語っていきます。
葛飾北斎とは?宝暦10年~嘉永2年(1760年~1849年)
葛飾北斎とは、江戸時代後期の文化文政(化政)時代(1804年~1830年)あたりに活躍した画家です。
化政時代は江戸時代の町人文化の爛熟期であり、化政文化ともいわれ、浮世絵や歌舞伎などといった庶民にも拡がる文化が生み出されました。
葛飾北斎は生涯に3万点以上の作品を残したため数多くの代表作がありますが、名所を浮世絵で描いた「富嶽三十六景」と絵手本※1「北斎漫画」は特に有名です。
富嶽三十六景の内の「神奈川沖浪裏」は、迫力のある構図と波の造形から、海外でも“グレートウェーブ”と呼ばれ人気があります。
また、葛飾北斎が85歳の時に信濃国小布施(現在の長野県上高井郡小布施町)に残した、「東町祭屋台天井絵」や「岩松院天井画 八方睨み鳳凰図」などの肉筆画は、集大成作品として知られます。
亡くなる直前まで描き続けた葛飾北斎は、当時としては長寿※2である90年の波乱の生涯を生きました。
※1 絵手本:絵の手本が描かれた絵本の一種
※2 長寿:江戸時代の平均寿命は30~40歳。特に数え年で7歳(満年齢6歳頃)までの子供の死亡率が高く、成人の平均寿命は60歳くらいともいわれるため、葛飾北斎の享年90歳は長寿にあたる。

葛飾北斎は生涯に渡り、表現を変えて波の絵を何点も描いています。中でも「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」は、北斎の傑作「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」の一つであり、海外でも広く知られています。今回は、葛飾北斎の描いた波の変遷をたどり、またなぜ葛飾北斎が波の表現を追求したのかについて迫ります。
葛飾北斎は“引っ越し魔”だった!?

江戸時代後期になると交通が発達し、庶民の引っ越しが盛んに行われるようになります。
当時は、引っ越す際に家財道具をすべて売り払い、引っ越した先の古道具屋で家具を調達するというのが主流で、今よりも手軽に引っ越しができました。
とはいえ、やはり葛飾北斎の93回という数は尋常ではありません。
葛飾北斎にとっては年に2回の引っ越しはざらで、3回引っ越した年もあったようです。
多いときは、たった一日で3回も引っ越しをしたともいわれています。
引っ越しの理由はさまざまにいわれますが、ここでは主な3つの理由を紹介します。
葛 飾北斎の目標は、生涯に引っ越し100回!
葛飾北斎の引っ越しが頻繁だった理由…それは、彼が“引っ越し100回”を目標にしていたことです。
100という数字は当時も今も、切りが良く縁起が良いとされます。
もしかすると、何かしらの願掛けもあったのかもしれません。
引っ越し回数目標100回は、他人がやらないことを多く行った葛飾北斎らしいエピソードといえます。
葛 飾北斎は掃除がイヤで引っ越しを繰り返していた!?
“引っ越し100回!”を目標にしていた葛飾北斎ですが、実は一番大きな理由は、掃除が嫌いで、食べかすでもなんでも放り投げたままにしていたことです。
そのようなごみは溜まるだけでなく、腐臭を放ちとても耐えられたものではなかったでしょう。
掃除をするくらいなら引っ越すという、まさに住居の使い捨てだったのです。
もっとも、生涯に3万点以上の作品を残していることから、掃除をする時間も惜しかったのではないかと推察できます。
さらに、共に暮らしていた娘の葛飾応為も、父親である葛飾北斎に似て作品のことしか考えず、まったく掃除をしなかったため、引っ越しをするしかなかったのです。
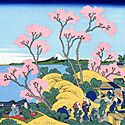
「富嶽三十六景」で有名な葛飾北斎を支えた娘・葛飾応為をご存知でしょうか?
自分自身も類まれなる絵画の才能を持ち、絵師として生涯を過ごした葛飾応為の画業人生とはどのようなものであったのか、代表作品などと共に見ていきましょう。
葛 飾北斎は借金取りに追われていた…
葛飾北斎の引っ越し三番目の理由は、借金取りから逃げていたことです。
実際に、彼が版元から借金をした時の証書も現存しています。
また、金には無頓着で無造作に置いていたため盗まれたり、請求に来る店の者には大金を投げつけるなど、貯金はしませんでした。
70歳代の頃には、葛飾北斎は人気絵師であり稿料も高かったのですが、返していた主な借金は、博打にはまった孫がつくったものでした。
特に、遅い円熟期である60歳代では、娘や妻の死、娘二人の離婚、さらには自分自身も中風(脳卒中)で倒れるなど、家庭的には波乱の時期でした。
そんな家庭の不幸も、頻繁な引っ越しと関係があったのかもしれません。
豊 原国周~葛飾北斎の引っ越し回数を抜いた浮世絵師~
世の中、上には上があるもので、葛飾北斎が目標にした引っ越し数100回を達成し、117回も引っ越しをした浮世絵師がいます。
浮世絵師・豊原国周です。
浮世絵が下火になった幕末から明治時代に活躍し、月岡芳年、小林清親と並び「明治浮世絵界の三傑」と称された、当時の代表的な浮世絵師でした。
豊原国周は天保6年(1835年)に江戸京橋五郎兵衛町(現在の東京都中央区八重洲)に生まれ、幕末の名浮世絵師・歌川国貞に師事しています。
豊原国周の引っ越しは葛飾北斎を意識したといわれ、画風も写楽など過去の作品を参考にするなど、浮世絵の寂れた明治時代に全盛期を偲んでいたのかもしれません。
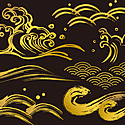
江戸時代後期の浮世絵師国貞は、初代歌川豊国の門下生です。門下生の中でもとくに役者絵・美人画に優れた才能を発揮し、幕末最高の人気絵師となりました。10代半ばの早い頃から初代豊国に弟子入りし、その才能の片鱗を見た豊国が大いに驚いたという話もあります。
葛飾北斎の主な引っ越し先は?
葛飾北斎は、どのような場所に引っ越したのでしょうか。
あまりにも頻繁に引っ越しをしたので、本人自身でも覚えていないほどでした。
記録がないためすべては正確にはわかりませんが、ここでは葛飾北斎の主な引っ越し先を紹介します。
引 っ越し先は、現在の墨田区の狭い範囲だった
引っ越しといっても、江戸時代は現在のように自動車があるわけではなく、行動範囲は限られています。
そのため、葛飾北斎が引っ越した範囲は、現在の東京都墨田区に限られていました。
葛飾北斎は江戸本所南割下水(現在の東京都墨田区亀沢)に生まれ、引っ越し先は隅田川の東側の狭い範囲に集中しています。
居住地の多くは現在跡形もありませんが、面影を残す居住地は以下の二箇所です。
1.立川(本所林町)三丁目
葛飾北斎30代後半から40代はじめまで、比較的長く居住しました。
2.本所亀沢榛稲荷神社
当時は榛馬場と呼ばれ、葛飾北斎円熟期の天保年間(1830年~1844年)終わりに居住。
また、80歳の頃には現在の東京都墨田区東駒形一丁目に居住しており、そこでは火事で資料や素描を焼失しています。
葛飾北斎が引っ越しをやめた理由
100回という目標を持ちながら、なぜ達成せずに引っ越しをやめたのか。
葛飾北斎の謎の一つといえるでしょう。
ここでは、その理由について考えていきます。
ご みの山だった旧居に虚しさを感じた?
葛飾北斎が旧居をもう一度借りた時、以前自分が汚したままでまったく掃除がされていなかったことにショックを受けたため。
一般的にはそういわれます。
確かにそのような状態では、その後誰も借り手がなかったことが想像され、こんなことを繰り返しても意味がないと思ったのかもしれません。
ばかばかしさや虚しさを感じ、自分の立てた目標がひどくつまらなくなったとも考えられます。
しかし、引っ越しをやめたのは80歳を越えた最晩年です。
実際のところ、体力の衰えも関係していたのではないでしょうか。
また、この頃は肉筆浮世絵を主な仕事としており集大成の時期であったことから、引っ越しすらも時間の無駄だと考えるようになったとも推察できます。
葛飾北斎、画号の改号も30回!
葛飾北斎は住居だけでなく、画号の改号、つまりはペンネームも頻繁に変えています。
改号数は、なんと30回。
ここで、「葛飾北斎」以外の画号をいくつか並べてみましょう。
北斎辰政・宗理・辰斎・辰政・百琳・画狂人・雷辰・画狂老人・天狗堂熱鉄・鏡裏庵梅年・月痴老人・卍・三浦屋八右衛門・百姓八右衛門・土持仁三郎……
これらは葛飾北斎にとって、それぞれが意味のある名でした。
例えば「北斎」という名は、若い頃に名乗った北斎辰政の略称であり、北斗七星の別称“北辰”と“七政”から取ったとされます。
葛飾北斎が信仰していた、日蓮宗系の「開運北辰妙見大菩薩」とも関係がありました。
次に、葛飾北斎がなぜ30回も改号したのかの理由、および主な画号とその時代の代表作を紹介します。
葛 飾北斎が改号をくり返した理由は?
・その時々に所属した絵の流派に合わせていたから
改号の大きな理由は、葛飾北斎の、自分の才能を信じ自説を決して曲げなかった時に傲慢と思える態度と奇行のため、浮世絵師仲間からは嫌われ、他のさまざまな流派に学んだことがあげられます。
その時の流派に合う名前を用いており、まだまだ自分は途上だという意思もありました。
・弟子に売ったから
浮世絵師として安定してからの改号の理由は、弟子に売ってしまったということです。
金だけでなく画号にも無頓着というのは、いかにも葛飾北斎らしいですね。
葛飾北斎は改号するたびに画風を変化させ、名声も上がりました。
その後も、名前に執着せずに改号を続けたことも、葛飾北斎ならではのエピソードです。
葛 飾北斎の主な画号と作品
葛飾北斎が画号に多く用いた基本となる言葉は、春朗・宗理・北斎・戴斗・為一・卍の6つになります。
それぞれ用いていた時代と作品を紹介します。
春朗(しゅんろう)時代 安永7年~寛政6年(1778年~1794年)19歳~34歳頃
葛飾北斎が勝川春章に弟子入りし、去るまでの修業時代です。
役者絵、美人画など人気の浮世絵や、江戸時代の一種の絵本である黄表紙の挿画を書きました。
代表作は「正宗娘おれん 瀬川菊之丞」、「婦女風俗図」、黄表紙「昔々桃太郎発端説話」など。
宗理(そうり)時代 寛政6年~文化元年(1794年~1804年)34歳頃~44歳頃
当時人気だった琳派の俵屋宗理の影響を受けるのとともに、古今の多くの画風を学びました。
葛飾北斎にとって雌伏※1の、しかし飛躍の時代でした。
この時代に美人画様式を確立します。
代表作は、「隅田川 渡の雪」、狂歌絵本「狂歌歳旦 江戸紫」、「画本東都遊※2」など。
※1 雌伏:人に仕えながら、実力を養い活躍の機会を待つこと
※2 画本東都遊:改題前は「狂歌東遊」
戴斗(たいと)時代 文化元年~文政2年(1804年~1819年)44歳頃~59歳頃
いよいよ葛飾北斎が画家として大活躍する時代です。
読本挿絵と肉筆画、「北斎漫画」などの絵手本を多く手掛けます。
「北斎漫画」をはじめとした絵手本では、「戴斗」の画号も用いました。
120畳の大きさの和紙に大達磨絵を描いたり、米粒に2羽の雀を描くなどのパフォーマンスをしたのもこの時期です。
代表作は、「北斎漫画」、「酔余美人図」、「潮干狩図」、「東海道名所一覧」、「仮名手本忠臣蔵」など。
為一(いいつ)時代 文政3年~天保5年(1819年~1834年)59歳頃~74歳頃
「富嶽三十六景」など多くの錦絵を描いた時代です。
葛飾北斎の遅い円熟期であり、江戸でも最も人気の浮世絵師の一人となりました。
この時期、“北斎”は用いていますが、葛飾北斎でなく主に「為一」を用いているのは意外です。
代表作は、「富嶽三十六景」、「百物語」、「琉球八景」、「諸国滝廻り」、「千絵の海」など。
画狂老人卍(まんじ)時代 天保5年~嘉永2年(1834年~1849年)75歳頃~90歳まで
最晩年期、葛飾北斎はまだ足りないといわんばかりに、また画号を変えます。
まさに葛飾北斎の奇人ぶりを示す画号、「画狂老人卍」です。
この時代は集大成期であり、錦絵を去り肉筆画に専念しました。
代表作は「富嶽百景」、「肉筆画帖 鷹」、「上町祭屋台天井絵」、「岩松院天井画 八方睨み鳳凰図」、「富士越龍図」など。
おわりに
葛飾北斎は作品の質、数ともに、日本を代表する画家であることは間違いありません。
また、引っ越しや改号の数からみても、桁外れの奇人であったといえます。
今回は、「引っ越し」という視点から葛飾北斎をみてきました。
彼から学ぶことは、人とは違う発想や行動が優れた作品の源であるということです。
葛飾北斎の作品も生き様も、興味が尽きません。

今や海外でも大人気の浮世絵。海外の美術館などには「国宝級」とも称される、浮世絵の名作が所蔵されていることも珍しくありません。さらに展覧会が開かれれば大盛況。