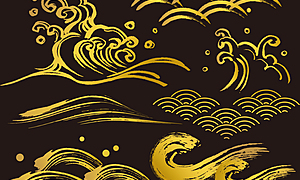「富嶽三十六景」で有名な葛飾北斎を支えた娘・葛飾応為をご存知でしょうか?
自分自身も類まれなる絵画の才能を持ち、絵師として生涯を過ごした葛飾応為の画業※人生とはどのようなものであったのか、代表作品などと共に見ていきましょう。
※画業:絵を描く仕事のこと。
葛飾北斎の娘、葛飾応為(お栄)とは?
葛飾応為は、江戸時代後期の浮世絵師・葛飾北斎の三女として生まれました。
生没年は不明ですが、寛政13年(1801年)頃~慶応4年(1868年)頃という説があります。
葛飾北斎の二人目の妻の子とされ、葛飾北斎が40歳の頃にできた子供でした。
名は“栄”といい、“お栄”と呼ばれ幼い頃から画才があったといわれています。
絵師の南沢等明に嫁ぎますが離縁され、その後は葛飾北斎の画業を支え、自身も絵画の技量を磨いていきました。
「 葛飾応為」の画号の由来
葛飾応為の本名は“栄 ”ですが、画号は「応為」とされています。
葛飾応為は顎が出ていて、葛飾北斎は彼女のことを「アゴ」とか「顎の四角い女」などと呼ぶほか、よく「オーイ」と呼んでいたことから「応為」という画号を名乗っていたといわれています。
洒脱※や粋に生きていた、江戸っ子らしいノリですね。
※洒脱:あか抜けている、さっぱりしていていること。
葛 飾応為の人生
嫁ぐも離縁され、実家に出戻る
葛飾北斎の三女として生まれた葛飾応為は、二十歳頃に町絵師である堤等琳の門人、南沢等明に嫁ぎます。
ところが、父親である葛飾北斎ゆずりの画力を持っていた葛飾応為は、夫の絵の稚拙さを笑ったために、3年ほどで離縁されてしまいました。
実家に戻った葛飾応為は、葛飾北斎と同居して彼の画業に携わったとされています。
悪衣悪食(あくいあくしょく)を恥じない心根の持ち主
葛飾北斎との暮らしは決して豊かなものではありませんでしたが、葛飾応為は父親に似て、衣食の貧しさを気にしなかったようです。
ちなみに、葛飾北斎は絵を描くこと以外のことはしなかったため、家はゴミ屋敷になるがまま、どうしようもなくなると引っ越しの繰り返しで、90年の生涯で93回の引越しをしたといわれています。
葛飾北斎は、布団から出ずに四つん這いで絵を描き続けた様子も伝えられています。
このように、ただひたすら画業に邁進する彼を、葛飾応為はただただリスペクトしていたことでしょう。

「富嶽三十六景」などで有名な浮世絵師・葛飾北斎。
世界で最も知られた浮世絵師といっても過言ではない葛飾北斎ですが、実は江戸時代後期を代表する奇人としても知られています。
特に引っ越しの回数は、生涯でなんと93回!
彼の奇人ぶりを語るエピソードとしてよく語られます。
葛飾北斎との暮らし・その後
葛飾応為が実家に出戻ったのは天保(1831年~1845年)のはじめ頃のようで、葛飾北斎が亡くなるまで20年ほど一緒に暮らしたとされます。
先ほど父親に似ていると触れましたが、彼女は葛飾北斎が嗜まない酒や煙草を好んでいました。
また、商家や武家の娘達に家庭教師として絵を教えていたりもしたようです。
葛飾北斎没後は仏門に帰依し、加賀前田家に扶持※されたとか、信濃国小布施(現在の長野県上高井郡小布施町)で亡くなったといわれていますが、実際のところは謎に包まれています。
※扶持:主君から家臣への俸禄。江戸時代では主に米か金が給与された。
「 おんな北斎」と呼ばれた葛飾応為の実力
「おんな北斎」とも呼ばれた葛飾応為の絵の実力について、江戸時代後期の浮世絵師であり優れた美人画の名手・渓斎英泉は、
“女子栄女、画を善くす、父に従いて今専ら絵師をなす、名手なり”
と評しています。
葛飾北斎も、
“余の美人画は阿栄におよばざるなり”
“彼女は妙々と描き、よく画法に適っている”
と述べていることから、葛飾応為が葛飾北斎の画業に携わった当初から優れた画力を持っていたことがうかがえます。
ところが、葛飾応為のものとして認められている作品は十数点と極めて少数です。
時の巨匠たちに評価される絵画の技量を持ち、常に葛飾北斎のそばにいたことを思えば、もっとたくさんの作品が残されていても良いはずです。
また、葛飾北斎の生涯の作品数は3万点といわれていますが、それだけの数の作品を一人で描いたとはとても思えません。
このことから、「北斎」のものとされている作品の中に相当数、葛飾応為の作品があるのではないかと考えられます。
「吉原格子先之図」〜葛飾応為の代表作品〜
葛飾応為の代表的作品、「吉原格子先之図」は、吉原遊郭の和泉屋を舞台に、格子越しの花魁と遊女、手前の禿と客を描いた作品です。
この作品は、葛飾北斎がオランダ人から依頼されたものと紙のサイズが一致していることから、1818年(文化15年)頃から1844年(弘化元年)の間に描かれたといわれています。
それでは、この絵の見どころをご紹介しましょう。
「 吉原格子先之図」の見どころ①光の表現の正確さ
この作品の最も素晴らしいところは、これまでの日本の絵画史にない美しい光と影の表現のあり方です。
日本で最初に影を描いたのは平賀源内の一党でしたが、この絵ほどの完成度ではありませんでした。
また、遊女のいる大行灯の明るい部屋中は遠近法を用いて描かれており、格子も立体的に構成されています。
これには、国内外関わらず貪欲に画法を学んだ葛飾北斎の影響を受けていることが見て取れます。
遠近法というと西洋人が開発したパースペクティブが有名ですが、日本絵画とは根本的に違う画法でした。
影を書き込んだ西洋画をはじめて見た東洋人が「何故、西洋人はこんなに画面を黒く汚すんだ」といったという言い伝えがあるほど、画法の違いはカルチャーショックだったのです。
江戸時代での画業は、一つの流派に入れば一生その道を進んで行くものでした。
しかし、自らを画狂と呼ぶ葛飾北斎は、貪欲に国内のさまざまな画法を学んでいき、ついには絵師で蘭学者でもあった司馬江漢などからも西洋の画法を学びます。
そのような葛飾北斎から、葛飾応為も西洋の画法を取り入れていったのでしょう。
ちなみに、葛飾北斎の絵には葛飾応為のような光と影の作品は見られません。
「 吉原格子先之図」の見どころ②絵の中にサイン?~「応為」という画号と本名の「栄」を探せ!
この作品が何故、葛飾応為の作品だとわかるかというと、絵の中の三つの提灯が鍵となっています。
提灯をよく見るとそれぞれに、「應」「為」「栄」の三文字がそっと書き込まれているのです。
「應」と「為」は画号の応為、「栄」は本名のお栄の意味でしょう。
画号を堂々とではなく遠慮がちに書いていることから、葛飾応為の画業における立場が察せられます。
「 吉原格子先之図」の見どころ③応為の美人画の実力
葛飾応為は、美人画にも定評があります。
彼女は葛飾北斎の描いた春画を見て、気をやる瞬間の女の足の指は内側に曲がるのだと述べ、葛飾北斎を驚かせることもあったともいわれ、葛飾応為の観察眼の鋭さを表すエピソードとして知られています。
浮世絵 太田記念美術館所蔵
「唐獅子図」〜葛飾北斎と娘・応為の合作〜
「唐獅子図」は、長野県上高井郡小布施町の「岩松院天井画 八方睨み鳳凰図」を描いた翌年である嘉永2年(1849年)の作といわれています。
この作品は葛飾北斎と葛飾応為の合作とされていますが、脳梗塞を患った葛飾北斎のリハビリのため日課として描かれたものであり、唐獅子の周りの牡丹の色使いや線の細かさなどから見て、葛飾応為の意図の方が大きかったと推察されます。
ボストン美術館所蔵
「春夜美人図」(別名「夜桜美人図」)
「春夜美人図」(別名「夜桜美人図」)は、絹本着色という絹に色を施す日本画の代表的な技法を用いた作品で、菱川師宣以来の縦長サイズの肉筆浮世絵です。
描かれた時代は江戸時代後期である19世紀(1801年~1900年)中頃のものと推察されます。
「 春夜美人図」の見どころ:背景の星
葛飾応為の得意な光と影の演出が素晴らしい作品で、前述の「吉原遊郭格子先之図」でも用いた人工的な光の表現に、さらに自然的な星の光を加えています。
この星の光は、光の強さ、位置なども非常に正確で、一等星などが5種類ほどに描き分けられています。
江戸時代には妙見信仰※が盛んで、葛飾北斎の“北斎”という名もここからきているといわれますが、葛飾応為ももれずこの信仰に造詣が深かったことがうかがえます。
葛飾応為は葛飾北斎の助手としてだけでなく、絵師としての独自の才能を開花させていきます。
なお、こちらの作品には画号はありません。
※妙見信仰:北斗星(北辰)・北斗七星を神格化した妙見菩薩に対する信仰。
メナード美術館所蔵
葛飾応為の他作品
葛飾応為の代表的な三作品をご紹介しましたが、彼女は他にも作品を残しています。
いくつかご紹介しましょう。
「 月下砧打美人図」
「月下砧打美人図」は、いわゆる勝川派※浮世絵の画法を用いた木版画で、葛飾応為の早期を代表する作品です。
この作品にはまだ、前述の光と影の表現はありません。
葛飾応為の作品はほとんどが絵師直筆の一点物である肉筆浮世絵といわれるもので、木版画はこの作品のほか作画を担当した、弘化4年(1847年)刊行の高井蘭山の絵本「絵入日用女重宝句」と、嘉永元年(1848年)刊行の山本山主人作「煎茶手引の種」のみです。
この作品の後、葛飾応為は葛飾北斎の春画の作成に力を添えていたと考えられます。
※勝川派:1700年代に活躍した絵師である勝川春章を祖とする浮世絵の流派。版画絵では写実的な「似顔絵」と呼ばれる役者絵や半身像の大首絵などを得意とするなど、リアルさを求め新画風を生み出した。
東京国立博物館所蔵
「 百合図」
「百合図」は、長野県上高井郡小布施町のとある旧家の貼交屏風 ※1の、向かって右中ほどに貼り付けられており、絹本着色の作品です。
数少ない葛飾応為の作品であり、小布施に唯一残されたもので、この旧家には葛飾応為からの手紙も2通残されており、葛飾北斎晩年の小布施に住む高井鴻山※2への訪問以降の作品であると推察できます。
百合図自体は葛飾北斎作の横大判「北斎花鳥図」や「北斎漫画」などでも見られますが、葛飾応為の「百合図」は、これらよりも一層リアルに描かれています。
※1 貼交屏風:いろいろな書や画を適宜交ぜて貼った屏風。
※2 高井鴻山:江戸時代末期の儒学者であり葛飾北斎門下の浮世絵師。
個人所有(信州小布施 北斎館寄託)
「 竹林の富士図」
葛飾応為の作品としては比較的新しく発見されたのが「竹林の富士図」です。
絹本着色で、誰かの依頼で描かれたもののようです。
実は、この作品と構図もモチーフもよく似た作品が他に2点あり、一つは葛飾北斎が描いた富嶽百景の二編にある「竹林の不二」、もう一つが葛飾応為が描いたものです。
この3点のうちの1点に葛飾応為の款記※があり、他のものはそれを写したものではないかともいわれます。
ちなみにこの頃、西に富士山を飾ると幸運が来るとされており、浮世絵には富士山が多く描かれています。
※款記:書画の作者を示す表記。
個人所有
「 三曲合奏図」
「三曲合奏図」の三曲とは、地歌三味線(三弦)、箏曲、胡弓のことです。
もともとこれらの楽器は盲人が扱う楽器で、合奏や作曲は盲人の最高位である検校がしていました。
検校は貸金業が許されていたため大名と同じくらいの地位も認められており、吉原との関わりも多かったようです。
この作品で演奏しているのは、描かれている着物や髪型、簪などからそれぞれ、花魁、芸者、町娘とわかります。
浮世絵のモチーフとして三曲合奏はしばしば見られるのですが、花魁などの遊女は年季明け以外の理由で遊郭から外に出ることは許されず、また町娘の遊郭への立ち入りを禁じられていたため、実際にこの三者が合奏するということはあり得なかったでしょう。
ボストン美術館所蔵
「 関羽割臂図」
“右腕に毒矢を受けた関羽を、医師の華佗が治療する”という「三国志」の一場面が描かれた「関羽割臂図」。
華佗は曹仁との戦闘で毒矢の傷を受けた関羽を治療するため、自らの意思で荊州に出向き、関羽の右肘の骨を削ってトリカブトの毒を取り除きました。
この時、関羽は治療中には腕を柱に固定した方が良いとの華佗の提案を断り、酒を飲みながら平然と補佐の馬良を相手に碁を打っていたと描写され、華佗は関羽の強靭さに大いに驚いたとされています。
この作品以前の美人画とは違う深みのある人物表現は、中国の画法を学んだ葛飾北斎の影響とも取れます。
縦の直線がある構図や、碁を打つ関羽の指先の繊細さ、また色彩表現が豊かであることなど、葛飾応為特有のものが散見されます。
なお、大きさは140.2cm×68.2cmと葛飾応為の作品の中では最大のものです。
天保の大飢饉以降、江戸市中でも錦絵の出版もできず、葛飾応為は肉筆浮世絵を絵草紙屋に並べてもらったりしていたようですが、これだけ大きなものは依頼されて描かれたと考えられます。
クリーブランド美術館所蔵
おわりに
葛飾応為は生涯を通じて父親である葛飾北斎を支え続けて来ましたが、画力においては決して独り立ちができないということではありませんでした。
当時の絵師の仕事の仕方として、今のような厳密なオリジナリティが求められていたわけでもなく、どちらかといえば、工房的な色彩の濃いものであったとされます。
葛飾応為は、葛飾北斎の執念のような画業にかける思いを丸ごと引き受けるような実力と精神を持った絵師といえます。
彼女の晩年の作品「関羽割臀図」などを見ると、その画業の間に「月下砧打美人図」などに比べてはるかに深く、力強い表現力を得ていることがうかがえます。
遠慮がちな画業人生を送った葛飾応為ではありますが、今もなおさらなる研究が重ねられ、より高い評価が与えられることを願います。

今や海外でも大人気の浮世絵。海外の美術館などには「国宝級」とも称される、浮世絵の名作が所蔵されていることも珍しくありません。さらに展覧会が開かれれば大盛況。

葛飾北斎は生涯に渡り、表現を変えて波の絵を何点も描いています。中でも「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」は、北斎の傑作「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」の一つであり、海外でも広く知られています。今回は、葛飾北斎の描いた波の変遷をたどり、またなぜ葛飾北斎が波の表現を追求したのかについて迫ります。

鈴木春信(すずきはるのぶ)は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師です。春信の画風の特徴は、色っぽいというよりはどちらかというと可愛らしく、まろやかな雰囲気の繊細で優しげな甘い美人を描きます。本記事では、そんな人気浮世絵師・鈴木春信の代表作をご紹介します!

江戸時代後期の浮世絵師国芳は、初代歌川豊国の門下生です。幼少期から絵に興味を持っていた国芳は、北尾重政などの絵師の絵柄をまねて人物描画を練習したと言われています。
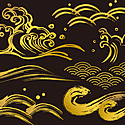
江戸時代後期の浮世絵師国貞は、初代歌川豊国の門下生です。門下生の中でもとくに役者絵・美人画に優れた才能を発揮し、幕末最高の人気絵師となりました。10代半ばの早い頃から初代豊国に弟子入りし、その才能の片鱗を見た豊国が大いに驚いたという話もあります。