
日本庭園は古く、奈良時代から築かれてきましたが、江戸時代になると武士、とくに大名が多く手掛けるようになりました。
その多くが池の周囲を回遊しながら楽しむ池泉回遊式の庭園で、水戸の“偕楽園” 、金沢の“兼六園” 、岡山の“後楽園)” はとりわけ素晴らしい庭園と称賛され、今では「日本三名園(日本三大庭園)」として日本を代表する庭園となっています。
今回はこの3つの庭園について歴史や見どころ、アクセスなどをご紹介していきます。
日本三名園(日本三大庭園)とは
茨城県水戸市の“偕楽園”、石川県金沢市の“兼六園”、岡山県岡山市の“後楽園”の「日本三名園(日本三大庭園)」は、いずれも江戸時代の大名が造園した100年以上の歴史を持つ池泉回遊式の庭園です。
偕楽園は水戸徳川家、兼六園は加賀前田家、後楽園は岡山の池田家が築きました。
三園とも広大な敷地を舞台に、地形を活かした池や築山、植物、茶室が配され、庭園を巡りながら移り変わる景色を楽しめるよう工夫されています。
閑雅な茶室など大名家らしい趣もありつつ、自然美を余すところなく感じられる日本文化として、偕楽園は国の史跡名勝に、兼六園と後楽園はともに特別名勝※に指定されています。
※特別名勝:文化財保護法によって国(文部科学大臣)が指定する文化財の種類の一つである“名勝”の中でも、特に価値の高いもののこと。

日本庭園とは、主に中心に配置された池、勾配をつける築山、そしてさまざまに組み合わされた石で構成されており、長い歴史の中で日本が独自に形成してきた様式です。この記事では、日本庭園の定義、多種多様な日本庭園とその特徴、日本庭園の歴史と文化、庭園の構成要素についてご紹介します。

日本庭園は、長い歴史の中で日本が独自に形成してきた様式です。この記事では、日本庭園の歴史について時代区分を設けながらご紹介します。
偕楽園(茨城県水戸市)

偕 楽園とは
茨城県水戸市の千波湖を見下ろす高台に広がる「偕楽園」は、江戸幕府最後の将軍である徳川慶喜の父である水戸藩主9代藩主・徳川斉昭が、構想・設計して造園した庭園です。
徳川斉昭が民衆と「偕に楽しむ場」にしたいと「偕楽園」と名付けました。
梅の名所として知られ、冬の間は100種3,000本ある梅の木が楽しめるほか、2月~3月には“梅まつり”が開催され、観梅客でにぎわいます。
梅の他にも、桜やツツジ、萩、竹林など日本らしい自然景観をゆったり楽しめる庭園です。
偕 楽園の歴史
偕楽園は天保13年(1842年)、徳川斉昭によって千波湖を望む山を切り開いて作られました。
徳川斉昭は学び舎となる藩校・“弘道館”を作り、同時に修行をする藩士の休養、憩いの場として造園を計画。
あわせて領民とともに楽しむ場にしたいという思いもあり、「偕楽園」と名付けました。
徳川斉昭は造園に先立ち、梅の木を数多く植えさせたことから梅の名所となりました。
その理由は梅干しにすれば非常食になることや、春に先駆けて早春に咲く花で領民に希望を与えたいという思いがあったからのようです。
千波湖を望む山を切り開いて梅林を設け、“好文亭”や“楽寿楼”などの建物も築いて現在の形となりました。
また、千波湖を庭の泉に見立て、梅林や竹林などを設け、さらに箕川を入れて川を作り、ヤナギ、カエデなどを植栽するなど、自然の風景を大切に造られています。
江戸時代、毎月3日と8日には、領民にも開放されました。
明治時代に「常磐公園」と称しましたが、昭和初期に「偕楽園」と元の名称に復帰します。
第二次世界大戦の折、空襲により好文亭は焼失してしまいましたが、その後、復元され、公園も拡張されました。
平成27年(2015年)には日本遺産にも認定されています。
令和5年(2023年)4月には、「The 迎賓館 偕楽園 別邸」がオープン。
優雅な大自然に囲まれた中で結婚式が行える、茨城県水戸市最新の式場として評判を呼んでいます。
偕 楽園の見どころ
偕楽園の見どころは、なんと言っても“梅”!
偕楽園は100の品種、数にして3,000本の梅が順次咲き、長期間かぐわしい香りに包まれる梅の名所として有名です。
とくに花の形、香り、色などが優れた品種は「水戸の六名木」※と呼ばれています。
園内は四季折々の見どころも多く、春は桜、初夏はキリシマツツジ、真夏は孟宗竹、秋は萩やモミジ、初冬は二季桜に彩られます。
偕楽園を満喫するなら、表門から入るのがよいでしょう。
孟宗竹の林、大杉森といった幽玄な世界を経て進んでいくと一転、明るく華やかな紅白の梅林が目に飛び込んできます。
この陰と陽の絶妙なコントラストも偕楽園の楽しみ方の一つです。
好文亭もほの暗い1階から3階(楽寿楼)にのぼると、梅林や千波湖をのぞむ眺望が一気に開け、感動もひとしおですよ。
※水戸の六名木:偕楽園内にある、烈公梅、月影、虎の尾、白難波、柳川枝垂、江南所無の6つの梅を指す。
偕 楽園のアクセス
住所
〒310-0033
茨城県水戸市常磐町1-3-3
電話番号
029-244-5454(偕楽園公園センター)
交通アクセス
【バス】をご利用の場合
・茨城交通:「好文亭表門入口」「偕楽園東門」「偕楽園前」「偕楽園」下車徒歩3~5分
・関東交通:「偕楽園」「千波湖」下車、徒歩5~10分
【自動車】をご利用の場合
・常盤自動車道「水戸IC」から約20分
・北関東自動車道「茨城東IC」、または「水戸南IC」から約20分
【電車】をご利用の場合
JR常磐線「偕楽園臨時駅」徒歩すぐ
※梅まつり期間中のみ運行
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
兼六園(石川県金沢市)

兼 六園とは
「兼六園」とは、金沢城(石川県金沢市)の外郭に位置する江戸時代の代表的な回遊式庭園です。
加賀藩前田家の歴代藩主が神仙思想※1の基に、約180年かけて築いてきました。
約11万㎡※2という広大な庭園には池や築山が点在し、およそ8,000本の樹木が四季折々の彩を添えています。
兼六園の名はかつての老中・松平定信が命名したもので、宏大・幽遂・人力・蒼古・水泉・眺望の6つの景勝を兼ね備えた名園という意味が込められたものです。
近年では周辺施設と合わせてライトアップも話題となっています。
※1 神仙思想:神人や仙人を信仰し、修行を積むことで不老不死の神仙となることを願う古代中国の思想。海の彼方には神人や仙人が住み長寿延命の薬があるとされる神仙島が存在するとされる。兼六園はこの思想の基に、大きな池を大海に見立て、そのなかに神仙島を配した設計となっている。
※2 11万㎡:東京ドーム2個分以上の広さ(東京ドームの面積46,755m²)
兼 六園の歴史
兼六園の作庭は、延宝4年(1676年)、加賀藩5代藩主・前田綱紀が金沢城に面した地に別荘を建て、その周辺を庭園として整備したのが礎となっています。
当時は庭と座敷があり、“蓮池亭”と呼ばれ、客人の接待や紅葉鑑賞の場として使われました。
のちに大火で焼失してしまいましたが、11代藩主・治脩が再建に着手し、“翠滝”や“夕顔亭”、“内橋亭”を造営します。
13代藩主・斉泰は、先代が上部の平地に作った隠居所“竹沢御殿”を取り壊して中心となる霞ヶ池を作り、さらに拡張整備して一大庭園を作り上げました。
母の隠居所として現在の“成巽閣”も造営し、ほぼ現在の形が完成します。
藩主の個人的な庭でしたが、明治時代に一般にも公開され、現在では“時雨亭”と“舟之御亭”が再建されています。
兼 六園の見どころ
徽軫灯籠(ことじとうろう)
兼六園のシンボルともいわれるのが、霞ヶ池の岸に立つ二本足の「徽軫灯籠」で、虹橋と紅葉の古木との三位一体の風景が何とも言えない風情を感じさせます。
根上松
徽軫灯籠に次ぐ名物が、高さ15mの「根上松」。
40本ほどの松の枝が地上2mもせり上がった立ち姿は圧巻ですよ。
また、四季折々の美しさも見どころで、40種以上の桜が咲き誇る春は花見橋や桜ヶ岡など鑑賞スポットもたくさんあります。
夏のカキツバタと新緑のコントラスや夏の霞ヶ池など心地よい涼感も魅力ですが、雪どころらしく冬も見逃せません。
雪の重みから枝を守るために施される唐崎松の雪吊りは冬の風物詩で、円錐状のシルエットが織りなす雪景色は息をのむほどの幻想的な美しさです。
兼 六園のアクセス
住所
〒920-0936
石川県金沢市兼六町1
電話番号
076-234-3800(石川県金沢城・兼六園管理事務所)
交通アクセス
【バス】をご利用の場合
・「広坂・21世紀美術館」下車(最寄りの出入り口:真弓坂口)
・「兼六園下」下車(最寄りの出入り口:桂坂口)
・「出羽町」下車(最寄りの出入り口:小立野口)
【自動車】をご利用の場合
・北陸自動車道「金沢東IC」、「金沢東IC」から約30分/「金沢森本IC」から約20分
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
後楽園(岡山県岡山市)

後 楽園とは
岡山県岡山市にある「後楽園」は、日本三名園の中でも最も広い約13万㎡の敷地を舞台に、岡山城や山々などを背景にした雄大な景観を楽しめる池泉回遊式庭園です。
岡山藩2代藩主・池田綱政が、自らの憩いの場として築いたのがはじまりで、歴代の藩主が少しずつ手を加えて形作っていきました。
延養亭や沢の池などを中心に築山、水の流れ、茶亭など変化に富んだ回遊庭園で、梅林や桜林のとりどりの色彩や芝生の緑など豊かな彩も印象的です。
今では季節ごとの“幻想庭園”と称したライトアップで、ロマンチックな夜を楽しむことができます♪
後 楽園の歴史
後楽園は池田綱政が家臣の津田永忠に命じて築かせたもので、貞享4年(1687年)に着工し、14年の歳月をかけて元禄13年(1700年)に完成します。
藩主の居間であり賓客を接待した延養亭、能舞台、林などのほか、修練の場である馬場や、茶畑や田畑もありました。
藩主の座る間から見える景色が最も美しいように工夫されていました。
当初は岡山城の後ろにあることから“御後園”と呼ばれます。
3代藩主・池田継政が園の中央に築山の唯心山とその中腹に唯心堂、ひょうたん池を作り、歩いて楽しめる回遊性を加えます。
その後、田畑の一部が芝生に代わり、また田畑に戻るなど歴代の藩主による景観の変化が積み重なり、現在の庭を形作っていきました。
明治時代には岡山県に譲渡され、一般公開が始まりました。
後 楽園の見どころ
後楽園は、池や全長640mの水路などの水の景観と、目にも鮮やかな緑の芝生が広がる園路の融合が特徴的です。
園路を散策すると、木々や築山、池など移り変わる景観のさまざまな表情とともに、水面に映る花々やモミジを楽しむことができます。
沢の池から唯心山方向を眺めると、岡山城の天守も望め、大名庭園らしい趣を感じられます。
また、唯心山からは雄大な沢の池など、庭園全体の眺めを堪能できます。
園内の景勝が一望にできる延養亭は普段は非公開ですが、期間限定で特別公開※されることがありますよ。
※初夏の「延養亭」特別公開:令和5年(2023年)は、5月24日(水)を除く、5月22日(月)~28日(日)の期間に開催予定(事前優先)
後 楽園のアクセス
住所
〒703-8257
岡山県岡山市北区後楽園1-5
電話番号
086-272-1148
交通アクセス
【バス】をご利用の場合
・岡電バス「後楽園前」下車すぐ
【路面電車】をご利用の場合
・岡山電気軌道東山本線「城下」下車徒歩10分
【自動車】をご利用の場合
・山陽自動車道「岡山IC」から車で約20分
【徒歩】をご利用の場合
・JR西日本「岡山駅」から徒歩25分
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
金沢・能登の最新情報を知るなら!
もっと金沢や能登について情報が知りたい!そんな方には、金沢や能登のローカル情報メディア「金沢日和」と「能登日和」がオススメです。
石川県に住む地元ライターが金沢や能登の魅力を届けるべく、金沢や能登の観光スポット・グルメ・イベント情報を配信していますので、最新情報を知りたい方はアクセスしてみてくださいね♪
おわりに
日本三名園(日本三大庭園)である水戸の偕楽園、金沢の兼六園、岡山の後楽園について紹介しました。
それぞれ江戸時代に大名たちが広大な敷地に精魂込めて作り上げた庭園で、大名たちの思いが込められた名園です。
豊かな自然と日本の情緒が合わさった庭園美にきっと心を癒されるはず。
かつての大名たちが見たような風景を眺めてみてはいかがでしょうか。

日本には有名な庭園が数多くありますが、それを造った庭師・作庭家のこととなると、ピンとくる名前は少ないのではないでしょうか。江戸時代以前は庭園を造る専門家は存在せず、僧侶や茶人として知られる人物が自分好みの庭園を造っていました。

戦国時代から江戸時代にかけて、武将たちが居住し、戦闘のための要塞でもあった日本のお城。武将たちが実用的な機能と美観を両立するべく精魂注いだお城は、今では日本を代表する観光スポットとして人気を集めています。ここではそんな数多く残る日本の城のなかから、一度は訪れたい名城をランキング形式で15城ご紹介します!
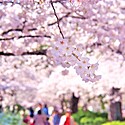
日本の春を代表するイベント、お花見。家族や友人と桜の下で楽しく食事をする人も多いのではないでしょうか。最近では、日本人のみならず、お花見目的で訪日する観光客も増えているそうです。そんなお花見ですが、いつ頃から日本で行うようになったかご存じでしょうか?

全国各地で見られる秋の紅葉の中でも歴史ある場所や建物が多い“京都の紅葉”は、やはり格別。しかし、実際に訪れるとなると、名所が多いだけにどこへ行けば良いのか迷ってしまいますよね。この記事では、京都出身のワゴコロ編集部員が厳選した、『京都のオススメ紅葉スポット20選』を各スポットの特徴とともにご紹介します!









