江戸時代から続く伝統芸能、人形浄瑠璃(文楽)の人気が再び盛り返しつつあります。
大阪の国立文楽劇場の年間観客動員数は平成24年(2012年)度以降、6年連続で10万人を突破する盛況ぶりです。
今回はそんな人形浄瑠璃(文楽)についてもっと知りたい!という方のために、人形浄瑠璃と文楽について詳しくご紹介します!
人形浄瑠璃(文楽)とは?

「文楽」とは、日本の操り人形浄瑠璃芝居(人形浄瑠璃)のことで、歌舞伎や能と並んで日本の三大古典芸能の1つに数えられています。
浄瑠璃は、物語に節を付けて語る日本音楽の一種で、琵琶法師が『平家物語』を語る”平曲”から始まったとされています。
一方、人形芝居は、平安時代に諸国を放浪しながらさまざまな芸を見せる傀儡という集団が行った人形回しが、日本での起源と言われています。
別々に発達してきたこれら2つの芸能が、江戸時代に合体して生まれたのが人形浄瑠璃文楽です。
人形浄瑠璃(文楽)の歴史

室 町~安土桃山時代:日本に三味線が渡来
日本には、もともと「語り物」と呼ばれる伝統芸能が存在していました。
これは、琵琶の音に合わせて物語を口で語るという芸能のことで、琵琶法師が語る“平曲”がその始まりとされています。
室町時代末期に中国から沖縄経由で三味線が渡来してきたことにより、語り物は急速に発達しました。
その演目の中でも『浄瑠璃姫』という物語が人気を集めたことから、浄瑠璃姫を含めた語り物全般が「浄瑠璃」と呼ばれるようになりました。
江 戸時代:浄瑠璃と人形芝居の誕生
浄瑠璃にはさまざまな種類があり、たとえば江戸にも常磐津節※や新内節※などの浄瑠璃が今も残っていますが、大阪の、特に文楽で使われる浄瑠璃は、江戸時代前期に竹本義太夫が始めた「義太夫節」です。
西国を放浪して各地のさまざまな芸能を習得してきた義太夫は、貞享元年(1684年)に大坂・道頓堀に竹本座を開場します。
この竹本座に座付き作者として加わったのが、近松門左衛門です。
近松は『曽根崎心中』や『心中天網島』などの心中物や、『女殺油地獄』など、実際の事件を題材に脚色を加えて町人社会の世相や風俗を赤裸々に描き出した「世話物」の傑作を次々と世に送り出しました。
こうして人形浄瑠璃(文楽)は全盛期を迎え、歌舞伎を圧倒するほどの人気を獲得していきます。
歌舞伎で上演される演目の中に、もともとは文楽のために書き下ろされた作品がたくさんあることからも、その隆盛ぶりが見て取れますね。
常磐津節:大夫と呼ばれる語り人と三味線を演奏する三味線方で構成される浄瑠璃の一種。
新内節:浄瑠璃の一流派。豊後節から分派した中でも、鶴賀新内が始めた流派のこと。
明 治~大正時代:人形浄瑠璃といえば“文楽”
その後、明治時代末から大正時代の初めにかけて、プロが演じる人形浄瑠璃は大阪の文楽座でしか上演されなくなったため、「文楽」と呼ばれるようになり、今ではそれが人形浄瑠璃の代名詞になっています。
人形劇は世界各国にありますが、それらと異なる文楽の最大の特色は、浄瑠璃の語り手である太夫と、その伴奏の三味線弾き、それに人形遣いの「三業」が拮抗し、時には三者の緊張関係の中で迫力ある舞台を生み出す総合芸能であるという点です。
各地で上演されていた人形浄瑠璃の中で、江戸時代中期の大坂(今の大阪)ではその新しい形が確立し、当時の世相を反映した演目が次々に上演されて、最先端の芸能として町人たちの間で人気を集めました。
このため文楽は、日本を代表する古典芸能であると同時に、浪速※の町人文化の中で発展し、洗練されていった大阪の芸能としての側面を強く持っています。
※浪速:大阪市域の別称・古称。
昭 和~現在:人形浄瑠璃(文楽)の衰退と再生
江戸時代中期には、時代の最先端を行く娯楽として歌舞伎をしのぐ勢いのあった文楽。
しかし、その後の道のりは決して順風満帆だったわけではありません。
なかでも最大の難局だったのが、戦後に起きた分裂騒動でした。
明治時代末期から文楽の運営は、今の大歌舞伎と同じように“松竹※”が担うようになりましたが、戦後、演者たちが松竹派と反松竹派に分裂し、混乱の中で人気も低下。
ついに松竹は昭和38年(1963年)に手を引き、文楽の運営は大阪府や大阪市などが出資する文楽協会に移管されます。
演者はすべて同協会所属の技芸員ということになり、分裂状態はようやく解消されました。
何度かの浮き沈みを経験してきた人形浄瑠璃(文楽)ですが、平成20年(2008年)にユネスコ無形文化遺産に認定され、海外公演も行われるなど、日本を代表する伝統芸能として世界に知られるようになりました。
今では、主な上演場所の国立文楽劇場(大阪)や国立小劇場(東京)では、チケットがなかなか入手できないほどの人気を集めています。
このように独自の洗練を遂げた文楽ですが、今もなお野外で上演されていた素朴で土の香りのする人形浄瑠璃が各地に残っています。
中でも淡路島と四国の徳島には常設の劇場があり、文楽よりも短い時間と低価格で気軽に楽しむことができます。
文楽とは異なった人形浄瑠璃の世界も、覗いてみてはいかがでしょうか?
※松竹:松竹株式会社。日本の演劇や映画の制作・配給・興行を行っている。

兵庫県の淡路島や四国の徳島市に観光旅行に行ったら、ぜひ足を延ばして人形浄瑠璃を見に行ってください。「人形浄瑠璃なんて知らない」「見たこともないし、興味もない」という人でも、30分から45分の短い上演時間と手ごろな料金で気軽に楽しむことができます。
義太夫と人形遣い
義 太夫節の語り手「太夫」
義太夫節の語り手を「太夫」と言います。
太夫は原則として1人で、時には2時間以上に及ぶ劇中の老若男女の登場人物の会話を語り分け、物語の筋や情景を、節を付けて力強く描写します。
太夫としての力量を身につけるには長年の厳しい修業が必要で、還暦を過ぎてからようやく一人前と認められるほどです。
歌舞伎の世界と違って文楽は世襲制ではなく、太夫の子供が必ず太夫になるとは限りません。
これは、あまりに厳しい修業が長年にわたり続くため、自分の子に後を継がせたがらない名人が多いためとも言われています。
義太夫節は、三味線の演奏と合わせて語られます。
この三味線は義太夫専用の太棹で胴体も大きなものなので、弾きこなすのは大変ですが、ボリュームのある重厚な音から、すすり泣くような繊細な音色まで、多彩な表現で場面を盛り上げます。
言葉以上に厳しい世界である、人形浄瑠璃。
現在、太夫の第一人者である、豊竹咲太夫氏がいますが、そんな人物ですら兄弟子に認められたのは50歳です。
下記の記事では、太夫含む人形浄瑠璃界の第一人者をご紹介しています。
ぜひご覧ください。

人形浄瑠璃は「三業」から成る、と言われます。義太夫節を語る「太夫」、音楽を奏でる「三味線」、人形を操る「人形遣い」の三者が一体となって、ひとつの舞台がつくられるのです。ここでは人形浄瑠璃の魅力と現代の代表的な演者をご紹介します。
“足10年、左10年”といわれる「人形遣い」
文楽の人形遣いは、1つの人形を3人で操るのが特色です。
この3人遣いは享保19年(1734年)に、竹本座で初めて行われたと伝えられています。
3人の中のリーダーが「主遣い」で、胴体と右手、顔の表情を操ります。
2番手が左手を操る「左遣い」、3番手が「足遣い」です。
人形遣いにも「足10年、左10年」と言われる、長年の修業が必要とされています。
おわりに
今回は人形浄瑠璃(文楽)について、歴史と豆知識を詳しくご紹介しました。
日本の伝統芸能として名高い人形浄瑠璃(文楽)ですが、一方で課題となっているのが、後継者問題です。
ここ数年の間に、太夫で人間国宝の竹本住太夫氏が平成26年(2014年)に引退(その後、平成30年に死去)したのに続き、竹本源太夫氏(平成27年死去)、豊竹嶋太夫氏も相次ぎ引退し、太夫の人間国宝はいなくなりました。
さらに人形遣いの人間国宝・、吉田文雀氏が平成28年(2016年)に、三味線弾きの人間国宝・鶴澤寬治氏が平成30年(2018年)にそれぞれ死去するなど、人形浄瑠璃(文楽)を背負ってきたベテラン勢が次々に舞台から去り、次世代育成が急務となっています。
亡くなられた人間国宝・竹本住太夫氏は自伝の中で、文楽を太夫・三味線・人形遣いの三者間の「真剣勝負」だと語っています。
太夫と三味線は付きすぎてはいけない。
人形遣いは太夫と三味線の様子をうかがっていたら、思い切り人形が遣えない。
三業それぞれが舞台の上で勝手にやって、どこかで不思議にぴたりと合う。
そんな気迫と緊張関係から生まれる人形浄瑠璃(文楽)の妙味を、劇場に足を運んで体感してみてはいかがでしょうか。
観客として足を運ぶことが、人形浄瑠璃(文楽)という文化を守る、一つの手助けになるかもしれません。

人形浄瑠璃と聞くと、「お上品でお堅いもの」と敷居が高いように思う方も多いのではないでしょうか。しかし、もともと庶民の娯楽だった人形浄瑠璃が、面白くないはずがありません。現代を生きる私たちにも十分共感できる思いが人形に託されて、より熱く激しく、華麗に演じられます。
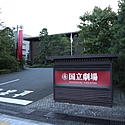
人形浄瑠璃の面白さを味わうためには、実際の舞台を見るのが一番です。しかし初心者にとっては、いつ、どこへ行けば人形浄瑠璃を見ることができるかさえ分からないでしょう。
ここではおもな年間スケジュールと、開催されている場所、また知っておけば舞台が10倍楽しめるお役立ち情報をご紹介します。

初めて人形浄瑠璃を見る人は、その人形の美しさに驚くことでしょう。可憐な面立ちの人形が、生身の人間のように動き、喜び、悲しむのを見ているうちに、いつのまにか3人の人形遣いが操っていることをなど忘れてしまいます。
ここではそんな人形浄瑠璃の人形について、ご紹介します。
















