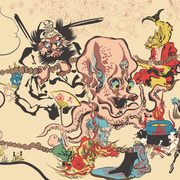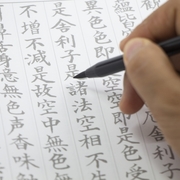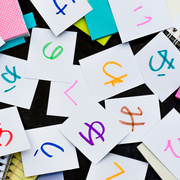盆栽は、長きにわたり日本人に愛され、大切に継承されてきた日本の伝統文化です。
近年、盆栽は、海外でもその芸術性が高く評価されており、愛好家や富裕層のコレクターも増加しています。
盆栽を楽しむためには、基本的なポイントや歴史、そして盆栽の樹種の種類についての基礎知識があると、その美しさが一層身近に感じられるはずです。
この記事では、盆栽とは何か、盆栽の種類や歴史、育てる際のポイントや初心者の方にオススメの盆栽など、盆栽の基礎知識をご紹介します。
盆栽とは?

「盆栽」とは、小さな鉢の中で樹木を育て、大自然の壮大さを再現する日本の伝統芸術です。
“盆”は鉢のこと、“栽”は植物のことを指し、鉢と樹木の調和が重要とされています。
鉢という限られた空間の中で、生きた植物が織りなす自然の風景は、鑑賞する者の心を癒してくれます。
自然に感謝しながら共に生きようという、日本人の心が現れた趣味で、長く人々に愛され続ける日本独自の伝統文化です。
その美しさから、海外でも愛好者が増加し続けており、今や“BONSAI”は世界共通語。
令和元年(2019年)に約4億8000万円だった盆栽の輸出額が、令和5年(2023年)には、倍近い9億円以上にもなっているほどです。
盆 栽の魅力
先ほどもお伝えした通り、盆栽の魅力は、小さな空間に凝縮された自然の壮大さにあります。
室内でも外の自然を盆栽の中に感じることができ、自分でその自然を育てることもできます。
鉢も含めた全体で、四季の移ろいや生命の躍動を感じられるのは、盆栽ならではの魅力といっても過言ではありません。
また盆栽は、水やりや剪定、植え替えなどの丁寧な世話が必要で、私たちの思いに応えるように育っていきます。
日々の手入れが欠かせないため、育てる時間を重ねるほど、どんどん愛着も芽生えていきます。
時には枯れてしまったりすることもありますが、盆栽の世界ではそれさえも詫び寂びとして捉えられるため、より自然と共存する気持ちが芽生えるはずですよ。
盆 栽を楽しむための鑑賞ポイント

「盆栽美」を鑑賞する際には、意識したい見どころがいくつかあります。
ここからは、その中からいくつかをピックアップしてご紹介します。
根張り

「根張り」とは、その名の通り、土の上に見えている根っこの張り具合のことです。
盆栽の土台となる部分で、生命力をダイレクトに感じられる要素の一つでもあります。
立ち上がり
「立ち上がり」は、根本から最初の枝まで伸びる幹のことです。
根張りから立ち上がりまでの流れを感じると、より盆栽の迫力に気が付けるはずです。
葉

「葉」の部分も、もちろん大切な盆栽の一部です。
モミジのように、樹種によっては四季を感じさせてくれるものもあり、盆栽の個性が現れる大きな要素の一つでもあります。
枝ぶり

幹から伸びる「枝」も、見どころの一つ。
太い枝がバランスよく伸びていることが、良い盆栽の特徴だといわれています。
これらの見どころのほかに、盆栽鉢と樹草の調和を気にかけること、そして自然の美しい風景を思い浮かべながら観賞することも大切です。
盆栽鉢と樹草が一つに調和している盆栽は、盆栽鉢も同じように引き立っています。
盆栽を見るときには、そういったすべての要素を含めて全体のバランスも楽しむことが大事です。
また、自然の中で自生している樹草の姿が盆上に表現されているため、日頃から自然の美しい風景に触れていると、より盆栽の美しさを実感できるはずです。

盆栽は日本の伝統文化の1つなので、“いつか”自分で育てて楽しんでみたいと思っている人は、多いはずです。
しかし、実際に盆栽を育てた経験や知識がない初心者は、盆栽をどのように楽しんだら良いのでしょうか。
初心者が盆栽を楽しむ場合、余計な理屈は不要です。
盆栽は、自由に “自分流”で気軽に楽しむことが、1番です。
盆栽の種類
盆栽は、樹木の種類、大きさ、樹木の形状によって分類されます。
分類は、盆栽の特徴や育て方、鑑賞方法を理解するための重要なポイントです。
ここでは、それぞれの分類に基づいて、盆栽の種類をご紹介します。
樹 種別の種類
まずは、樹種別の種類についてです。
盆栽は大きく分けると、葉が落ちる“落葉樹”と、常に葉が付いている“常葉樹”の2種類に分類されます。
そしてそこからさらに、鑑賞上の分類として、松柏類盆栽、雑木類盆栽、花物盆栽、実物盆栽、草物盆栽の五つに分けられています。
松柏類盆栽

「松柏類盆栽」は、その名の通り、松と柏をまとめたもので、盆栽界の王様とも呼ばれる樹種です。
松柏類盆栽の主な種類には、
・黒松
・赤松
・錦松
・五葉松
・蝦夷松
・米栂
・杜松
・杉
・真柏
・檜
・一位
などがあります。

松の盆栽は、真柏(しんぱく)の盆栽と並んで日本の盆栽界の主流の1つです。盆栽に使われている松の主な樹種は、6種あります。
日本一の生産県は、「うどん県」として知られている香川県ですが、その生産地の中心は高松市です。
雑木類盆栽

「雑木類盆栽」は、落葉樹が盆栽に仕立てられていたものが多く、美しい四季の変化を身近で楽しむことができる樹種です。
雑木類盆栽の主な種類には、
・紅葉
・欅
・楓
・姫沙羅
・榎
・銀杏
などがあります。
花物盆栽

「花物盆栽」は、花をつける木を盆栽にした樹種です。
花物盆栽の主な種類には、
・梅
・桜
・躑躅
・木瓜
・皐月
・藤
・桔梗
・百日紅
などがあります。
実物盆栽

「実物盆栽」は、実がつく樹木を盆栽にしており、ついた実を食べることができるものもあるという一石二鳥の樹種です。
実物盆栽の主な種類には、
・姫林檎
・蔓梅擬
・山桜桃
・梨
・花梨
・石榴
・柿
・梔子
などがあります。
草物盆栽

「草物盆栽」は、山に自生している山草や、野に自生している野草を使って仕立てられた盆栽です。
草物盆栽の主な種類には、
・岩檜葉
・常盤忍
・猩々バカマ
・蘭
・シダ
などがあります。
大 きさ別の種類
つづいて、大きさ別の種類についてです。
大きさ別で分類する際には、それぞれ樹の高さによって大きく以下のように分けられます。
| 分類 | 樹高 |
| 大品(だいひん)盆栽 | 50cm以上 |
| 中品(ちゅうひん)盆栽 | 20~50cm |
| 小品(しょうひん)盆栽 | 20cm以下 |
大品盆栽は、一つあるだけでも部屋全体に庭園の雰囲気を作ってくれるような存在感があります。
小品盆栽は、繊細な美しさが特徴で、初心者でも作りやすいサイズです。
また小品盆栽は大きさによってさらに細分化されており、中でも、キッチンやトイレなどの限られたスペースでも楽しめる3~4cmの豆盆栽は、近年人気が高まっています。
どの分類にも魅力があり、自分好みや環境にあわせて作ることができますよ。

樹 形別の種類
盆栽を樹形別に分類することもあります。
幹の姿や数、配置によって多彩な姿があり、その特徴に基づいて、いくつかの基本的な形に分類されます。
以下で一部紹介しますので、詳しく見ていきましょう。
箒立ち

「箒立ち」は、根元から天にむかってまっすぐに伸びて箒のように広がる、複数の幹が特徴的な樹形です。
幹の上部で枝が広がり、半円形になっていることが特徴です。
全体的に調和がとれた、優雅で凛々しい盆栽になります。
直幹

「直幹」は、根元から樹冠まで、まっすぐに伸びる力強い樹形です。
根と枝が四方向にバランスよく伸びているものが理想とされており、幹は上に向かうほど細くなります。
神社でよく見られるスギやイチョウがこの樹形の代表例といえるでしょう。
模様木

「模様木」とは、幹が模様のように曲線を描いている樹形のことです。
幹の曲がりを“模様”と呼び、四季ごとの風向きや寒暖差など、自然の影響を受けて作られます。
直幹以外のほぼすべての樹形に見られ、日本の風土を映した造形美を楽しむことができる樹形です。
斜幹

「斜幹」は、幹が左右のいずれかに傾斜した樹形です。
自然界では、海岸や山の斜面など、傾斜地に生える樹木によく見られます。
一定方向からの強風や光を求めて成長した結果、斜めに伸びた姿になり、45°~60°の傾斜が理想的とされています。
懸崖

「懸崖」は、幹や枝の先が下方に伸び、根よりも低くなっている独特の樹形です。
断崖絶壁や渓谷に生えた樹木を模しており、強風や雪に耐えて生き続ける姿を表現しています。
松柏類のほかに花物盆栽にも見られる樹形で、一位や梅、菊などさまざまな樹種に向いています。
盆栽の歴史
盆栽は、いまから約2500年前の中国で誕生したと伝えられています。
当時の盆栽は、盆の上に石や砂、草木を置いて自然の風景を楽しむ“盆景”と呼ばれるものでした。
その後、平安時代から鎌倉時代の間に盆景は日本に伝わり、身分の高い貴族、僧侶や武士などの間で親しまれるようになります。
江戸時代には、一般庶民の間でも盆栽が普及したことで、多くの樹種が盆栽として仕立てられたり栽培されたりしはじめました。
江戸時代の終わり頃に、「盆栽」という言葉が使われるようになった後、明治時代には、茶の湯文化の流行によって床の間に盆栽が好んで置かれるようになり、さらに盆栽は人気を集めます。
昭和39年(1964年)の東京オリンピックや、昭和45年(1970年)の大阪万博で開催された盆栽展を通し、海外でも注目されるようになった盆栽は、”BONSAI”と英語で表記されるように。
今日、“生命ある芸術”として人気のある盆栽は、日本の誇る一大文化といっても過言ではないほど多くの人に親しまれています。
盆栽の育て方は?おさえておきたいポイント

盆栽の育て方の要は、適切な水やり、施肥、そして定期的な植え替えです。
樹種や季節に応じたこまめな観察と手入れが、美しい盆栽を育てる秘訣なのです。
ここからは、実際に盆栽を育てる際に知っておきたいポイントをいくつかご紹介します。
水 やりのポイント
盆栽の水やりには、水分補給以上の役割があります。
水やりをすることで、鉢の中の老廃物や古い空気を押し出し、新鮮な空気に入れ替えることができます。
鉢の表面が乾いてきたら、乾ききる前に、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えましょう。
水やりの量や回数は、樹種や季節によって変化します。
水やりのポイントについてさらに詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください!

初心者が盆栽管理をする場合、特に注意すべき点は「置き場所選び」と「水やり(灌水)」の管理です。
盆栽は「生きもの」なので、盆栽鉢の置き場所選び、生育の良い盆栽を育てるための基本的条件で注意が必要です。
また、初心者が水やりをする際の注意点は一般的に水のかけ過ぎが知られていますが、それ以外にも注意すべき点があります。
肥 料をあげる際のポイント

盆栽は鉢が小さく土の量が限られるため、適切な施肥で栄養を補う必要があります。
鉢の中に納まっているので根の量も少ないため、肥料を過剰に与えすぎると根を傷めてしまう恐れがあります。
肥料には、効果がゆっくり現れる緩効性肥料と効き目の早い遅効性肥料があり、その中でもそれぞれ特徴があります。
育てる盆栽の種類や目的にあわせて、適切な肥料を選ぶことが大切です。
肥料の種類についてもっと知りたい方は、下記の記事をご覧ください!

盆栽初心者にオススメの肥料には、「粉肥」・「水肥」・「玉肥」・「化学肥料」の4種があります。盆栽をはじめたものの、花が咲かなかったり、思うような色にならない時は、肥料を見直してみてはいかがでしょうか。この記事では盆栽の肥料や、盆栽の生育に欠かせない「施肥(せひ)」についてご紹介します。
植 え替えのポイント

盆栽の植え替えは、樹木の健康と若返りに必要な作業です。
鉢の中で根が生長しすぎると、根と古い土が固まった「根鉢」の状態になり、水や空気が通りにくくなってしまいます。
これにより、盆栽がうまく成長しなかったり、根腐れを起こすことがあるため、植え替えの作業を行うことが大切なのです。
植え替えでは、古い根を約3分の1程剪定し、新しい根の生長を促すとともに、土を新しいものに入れ替えます。
適期は樹種によって異なりますが、一般的には新芽が出る前の2~3月頃が適していると言われています。
植え替えの際の注意点についてもっと知りたい方は、下記記事をご覧ください!

盆栽を始めようと思った時に、まず気になるのが管理方法。
何をすればいいのかネットで調べてみると、水やり、肥料、剪定、針金掛け…など、少し専門的な用語がずらり。
ここでは、最初に知っておくとより盆栽を楽しむことができる、盆栽の基本の管理方法について分かりやすくご紹介します。
おわりに
盆栽は一見難しく感じても、基本さえ抑えれば、誰でも楽しめる日本の伝統芸術です。
盆栽の知識を深めると、日本人特有の繊細な美意識や、自然への思いやりを感じることができるはずです。
心に浮かぶ自然の景色を再現したり、好きな花を愛でたり、自由な発想で、自分だけの小さな世界をつくる喜びを、ぜひ味わってみてくださいね♪

盆栽の始め方や作り方をわかりやすく解説!はじめての盆栽にオススメの盆栽、盆栽の選び方や土選び・鉢選びの注意点、育て方のポイントや盆栽づくりに必要なもの、手順や良い種木の増やし方など、盆栽初心者・ビギナーの方必見の内容です♪