日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。
技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。
そんな伝統工芸品ですが、追い詰められながらも奮闘し、世の中に新しい風を生み出そうとしています。
今回は、古くから続く技術を継承して作られる、伝統工芸品についてお話をしたいと思います。
伝統工芸品と伝統的工芸品の定義の違い

よく耳にする「伝統工芸品」という呼び方とは別に、「伝統的工芸品」と呼ばれるものがあることをご存知でしょうか。
この二つの違いについて、まずは説明しましょう。
伝 統工芸品とは
そもそも「伝統工芸」とは、長い年月にわたり継承している技術が用いられた、工芸や美術のことを指します。
そして、伝統工芸を用いてできた作品が「伝統工芸品」となります。
明確な定義はないのですが、各都道府県や自治体が「伝統工芸品」である、と認めたものは伝統工芸品です。
承認される工芸品の特徴は、
・長い歴史があること
・日常生活で使用されていること
・熟練の技術で作られていること
・主要部分が手作業で作られていること
があげられます。
また、都道府県や自治体等、誰か固有の人物が決めるのではなく、手作業で作られる工芸品を多くの人が認めれば、それが「伝統工芸品」であるという見方もあります。
現在、伝統工芸品は日本全国で約1200種類もあると言われていますが、伝統工芸品と伝統的工芸品の区別を付けずに、全部をひっくるめて「伝統工芸品」と言っている場合もあります。
伝 統的工芸品とは
伝統的工芸品とは、経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指します。
この「的」には、
工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品出典: 一般社団法人・伝統的工芸品産業振興協会HP
という意味が込められています。
「伝統的工芸品」に認定されるには、いくつかの要件をクリアする必要があります。
その要件とは、
・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること
・日常生活で使用されていること
・主要部分が手作業で作られていること
・一定の地域で産業が成り立っていること
です。
しかし、工芸品を作っている産地が経済産業大臣に申請をしなければ、審査をしてもらうことができません。
そのため、「伝統的工芸品」の要件をすべてクリアしている工芸品でも、申請をしていない工芸品もあるというのが現状です。
伝統工芸品の種類
伝統工芸品と一言にいっても、種類は様々です。
織物、染織品、その他繊維、陶磁器、漆器、木工品、竹工品、金工品、仏壇・仏具、和紙、文具、石工品、人形、その他の工芸品、工具用具・材料などの種類に分かれています。
一般の方からすると、陶磁器などの花瓶や漆器のお椀などは、伝統工芸品であるというイメージが強いかもしれません。
しかし、うちわ(その他の工芸品)やタンス(木工品)も伝統工芸品に含まれるということを知らない方も多いのではないでしょうか?
日本人が普段使っている身近な物の多くが、実は伝統工芸品なのです
今ある240品目の伝統的工芸品
経済産業大臣が指定している「伝統的工芸品」は、令和4年(2022年)11月現在、240品目あります。
北海道・東北地方の伝統的工芸品


「伝統的工芸品」とは、『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』に基づいて経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。それぞれの産地では、伝統的工芸品の技術を継承し発展させるべく、さまざまな取り組みが行われています。今回は、北海道・東北地方の伝統的工芸品を紹介します。
関東地方の伝統的工芸品


日本には、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、日用品の伝統工芸品が多数存在します。全国では200品目以上ありますが、関東地方ではそのうちの35品目が伝統的工芸品として認定されています。本記事では、今も脈々と継承されている関東地方の伝統的工芸品をご紹介します。
中部地方の伝統的工芸品


伝統工芸品とは、その地域で長年受け継がれてきた技術や匠の技を使って作られた伝統の工芸品のことを指します。その中でも今回は、北陸や東海といった中部地方の新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、富山県、石川県、福井県の伝統的工芸品73品目を紹介します。
近畿地方の伝統的工芸品


日本には、各土地に古くから受け継がれてきた多くの伝統工芸品が存在します。全国で230品目以上ある伝統的工芸品。今回は、日本の歴史の中で長く政治や文化の中心地であった、近畿地方の伝統的工芸品45品目をご紹介します。
中国地方の伝統的工芸品


日本海と瀬戸内海に挟まれ、温暖で過ごしやすい気候の中国地方では、豊かな文化が育まれてきました。その地の地場産業でもある伝統的工芸品を知ることは、中国地方の歴史や風土をより理解することに役立つでしょう。今回は、中国地方5県の伝統的工芸品16品目についてご紹介します。
四国地方の伝統的工芸品


日本各地には、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いて作られる工芸品や美術品がたくさん存在します。日本に数多くある伝統的工芸品のうち、ここでは四国地方に伝わる9品目をご紹介します。
九州地方の伝統的工芸品


温暖な気候と豊かな自然に恵まれた九州地方では、工芸品の素材となる原材料が豊富で、陶磁器(焼き物)や織物、竹細工などさまざまな伝統工芸が発展を遂げてきました。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている38品目をご紹介します。
県が指定する伝統工芸品
県が指定している伝統工芸品で、特に有名なものをご紹介します。
東 京都 41品目(伝統的工芸品含む数)
江戸つまみ簪
歴史江戸つまみ簪が誕生したのは江戸時代。
江戸つまみ簪は、京都にある花びらのかたどった「花つまみ簪」がルーツだと言われています。
つまみ簪は江戸で大流行となり、そのままこの地に根付きました。
正方形に切られた薄いシルクの生地をピンセットでつまんで折り畳むことで立体的な花や鳥などの形を生み出します。
日本の職人さんだからこそできる指先の繊細な作業で作られたパーツは、日本人ならではの繊細さと自然観が表れています。

つまみ細工は、小さな正方形の布で作った花びらなどを組み合わせて作品にしていく、日本の伝統工芸品です。
この記事では、つまみ細工の歴史をはじめ、つまみ細工の作り方や体験ができる工房、初心者の方でも気軽につまみ細工のアクセサリー作りに挑戦できるつまみ細工キットなどをご紹介します。
江戸簾(えどすだれ)
歴史すだれ自体の歴史は古く、万葉集の中にも出てきています。
江戸時代になり、江戸にある武家屋敷や神社仏閣などでも使用されるようになり、江戸に定着しました。
江戸すだれの特徴は、大きく分けると4種類の用途があるということです。
「外掛け簾」「内掛け簾」「応用簾」「小物簾」とあり、熟練の職人であれば、オーダーによって自由自在に作ることができます。
京 都府 34品目(伝統的工芸品含む数)
京象嵌(きょうぞうがん)
歴史象嵌の技法はシルクロードを経て、奈良時代に中国から仏教とともに日本に伝わったものです。
1000年以上の歴史があり、刀の金具や宗教的な道具として使われてきました。
現在は細密な象嵌を駆使した花瓶やアクセサリーなどに姿を変えています。
鉄生地に金や銀をはめ込んで作り上げるものです。現在は大変細かい作業が必要となっています。
丹後ちりめん(たんごちりめん)
歴史丹後の地でちりめんが作られ始めたのは711年といわれていますが、「丹後ちりめん」という名前になったのは1722年だと言われています。
ちりめんは絹でできているので、糸作りから始まります。
生地にシボがついており、生地が純白なのが丹後ちりめんです。
大 阪府 24品目(伝統的工芸品含む数)
大阪張り子
歴史張り子は元々中国の技法が京都に伝わり、その後全国に広がりました。
江戸時代には大阪でも作られていたことが書かれている書物が残っています。
張り子は、中が空洞になっている紙の置物で、トラやダルマなどの形のものが多くあります。
堺線香
歴史16世紀の終わりに中国から製法が伝わったと言われています。
堺市はその頃日本の中でも有数の貿易港だったということと、原料の香木が集まりやすかったということで作りはじめました。
堺線香は、すべて天然の香料の調合で作られているため、「香の芸術品」と呼ばれるほどです。
調合の仕方は、その家々の秘伝のため他ではまねのできない香りとなっています。
石 川県 36品目(伝統的工芸品含む数)
七尾和ろうそく
歴史昔から七尾で和ろうそくが作られていましたが、江戸時代になると寺院での使用が増え、この地に定着しました。
また信心深い人が多かったため、各家庭でも宗教道具としてろうそくが用いられていたようです。
和ろうそくは、西洋ろうそくとは違い、米ぬかや菜種などの自然のものから作られています。
また、西洋ろうそくよりも長く火を灯せるのも特徴です。
加賀毛針
歴史江戸時代、大名や武士たちは堂々と鍛錬をすることができませんでした。
鍛錬をすれば、江戸から謀反を起こすのではないかと思われてしまうためです。
そのため、足腰を鍛えるために釣りをし、その道具が栄えたのです。
毛針は釣りに使う餌の代わりに使われます。
テグスの下に金の玉があり、その下に蓑毛が数本あり、その中に胴巻き針、角が隠れています。
沖 縄県 36品目(伝統的工芸品含む数)
琉球焼
歴史琉球王国があった時代に作られていた陶器です。
現在に至るまで作られ続けています。
琉球焼には二種類ありダイナミックな上焼と、釉薬をかけずに作られる荒焼。
最近は改めて琉球焼に魅了される人が増えているそうです。

やちむんとは、沖縄の伝統工芸品で、沖縄らしい模様が描かれた重厚感のある焼き物です。近年では沖縄県内に留まらず、県外にもやちむんファンが増えており、やちむんが出品される陶器市には多くの方がやちむんを求めて足を運ぶ人気ぶりです。歴史や魅力、種類などを知り、更なるやちむんの魅力に迫っていきましょう!
琉球ガラス
歴史琉球ガラスの歴史は明治中期から始まります。
長崎県や大阪府から来た職人によって作られ始めました。
他のガラス製品に比べるとカラフルで、沖縄にある原色のイメージをそのまま具象化したようなものになっています。

沖縄の青い海、そして色とりどりの花を思わせるカラフルな「琉球ガラス」。
琉球ガラスは沖縄の「チャンプルー文化」から生まれたことをご存知でしょうか。
沖縄の人々に加え、南蛮渡来のビードロ技術を持つ長崎の職人、大阪の商人、アメリカ文化がチャンプルー(混ざり合い)してできた伝統工芸品なのです。

琉球ガラスの歴史は、第二次世界大戦後、在留米軍によって持ち込まれたコーラやジュースの廃瓶を原料として、ガラス製品を作ったことから始まりました。
厚みや気泡のある独特な風合いで、温かみのあるデザインが人気となり、平成10(1998)年には沖縄県の伝統工芸品に指定されています。
おわりに
日本の伝統工芸品に、これだけたくさんの種類があることに驚いた方も多いのではないでしょうか?
普段、私たちの生活の中で何気なく使用している伝統工芸品たち。
日本には、まだまだ日本人が忘れかけている伝統工芸品がたくさんあります。
そのどれもが、素晴らしい魅力を持っており、日本が誇るべきものです。
忘れ去られてしまう前に、国内外問わずより多くの方に認知してもらい、この伝統文化を継承していきたいですね。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

大正12(1923)年創業の清水硝子で働く中宮涼子さんは、江戸切子初の女性伝統工芸士。
今回は、職人になったきっかけや一つ一つの作品に込められた想い。
この仕事をしている上でのこだわりなどを詳しく伺った。


























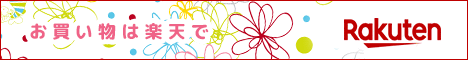





















![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)
![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)













