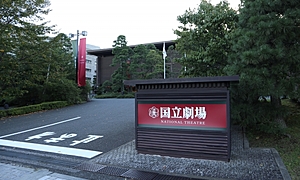人形浄瑠璃は「三業」から成る、といわれます。
義太夫節を語る「太夫」、音楽を奏でる「三味線」、人形を操る「人形遣い」の三者が一体となって、一つの舞台がつくられるのです。
ここでは人形浄瑠璃の魅力と現代の代表的な演者をご紹介します。
太夫 全ての語りを担当
舞台上手に三味線弾きと並んで座っている太夫。
ところが、三味線弾きと体の大きさがまるで違って見えます。
それは、太夫が膝立ちになり、つま先を立て、「尻引」という小さな椅子に腰を載せているからです。
さらに太夫はお腹からグッと声が出せるように、腹帯を巻き、帯をしめた懐に「オトシ」という重りを入れます。
足首を立て、足指の力と腹力で語るのです。
たった一人で、男も女もナレーションも、すべての語りをやってのける太夫は、指揮者のいない人形浄瑠璃で、三味線や人形をまとめ上げる存在です。
豊 竹咲太夫 太夫の第一人者
そんな太夫の現在の第一人者が、豊竹咲太夫です。
咲太夫は明治77年(1944年)生まれ。
同じく太夫の八世、竹本綱太夫の息子として生まれ、9歳で明治・大正・昭和の三代に渡って活躍した名人の豊竹山城少掾に入門して人形浄瑠璃の世界に入ります。
50歳に入った頃に、やっと兄弟子から「子供の頃からやっていて、やっと(義太夫らしい)声が出るようになったなあ」と言われるような、厳しい世界です。
咲太夫も「55から70ぐらいまでが勝負の世界です」と言います。
「70歳が体力の限界」という咲太夫も、その70歳を超えました。
その壁を破るのに必要なのは、「芸の貯金」と咲太夫は言います。
小さな頃からこの世界に入って、厳しい稽古を重ねただけでなく、中学生ぐらいの多感な時期に、土曜日の夜、夜行電車で東京へ行き、歌舞伎を始め様々な演劇を見て、日曜日の夜行で大阪に戻るということを繰り返しました。
そうした幅広い肥やしがあってこそ、今日の咲太夫があります。
「公演を3回やらないと自分のものにはならない。3回やれば、ある程度自分のものになる」と咲太夫は言いますが、1回の公演期間というのは、だいたい1ヶ月、つまり稽古を重ね、本番の舞台を30回×3回、100回近く重ねて、やっと自分のものになるということです。
人形浄瑠璃の技芸員(「太夫」「三味線」「人形遣い」の三者を総称してそう呼びます)の研修所でも教えている咲太夫は、そこで「24時間ではなく、25時間、この世界に浸かっていなさい」と教えるそうです。
イケメン太夫として話題の豊竹咲寿太夫も、咲太夫のお弟子さんです。
厳しい精進を重ねて伝統を受け継ぐ名人芸。
ゆったりとしたマクラ(冒頭部分)から、疾走感あふれる段切り(クライマックス)まで、たったひとりで語られるオペラに、ぜひ耳を傾けてください。
三味線弾き
表情豊かに全身全霊を傾けて語る太夫の隣で、無表情なまま、常に前を向いて静かに端座しているのが三味線弾きです。
太夫に比べて小さく見えるのは、太夫のようにつま先立ちで座っていないだけでなく、両足を逆ハの字に広げて腰を落として「ぺたんこ座り」しているからです。
太夫は床本を見ながら語りますが、三味線はすべて暗譜です。
太夫の語りを支え、ときにリードする三味線は、いわばひとりオーケストラ。
鶴 澤燕三 三味線の第一人者
そんな三味線の第一人者が鶴澤燕三です。
歌舞伎や能の世界とは異なって、人形浄瑠璃の世界は世襲ではなく、実力主義です。
一般家庭の出身者でも養成所で研修を受け、技芸員になることができます。
昭和33年(1959年)生まれの鶴澤燕三はなんと高校時代をハワイで過ごした帰国子女。
帰国後、テレビで三味線を見たのがきっかけで、三味線に興味を持つようになったといいます。
従弟の紹介で研修所を知った燕三は、たちまち義太夫の太棹三味線の音に魅せられ、受験の書類の第一志望、第二志望、第三志望の欄を、すべて「三味線」で埋めました。
実際、義太夫用の三味線のバチは非常に大きく、最初はバチを持つだけでも指が痛く苦労するし、そこからさらにバチを糸に当てるのも一苦労なのですが、燕三は最初からバチを持つことができ、糸にも当たったのだそうです。
義太夫三味線の自然な手の動きを体得するためには、「腕固め」という練習をしなければなりません。
三味線の「三の糸」という最も細い糸を左手の人差し指で強く押さえ、バチを持った右手で「テテテッ、テテテッ」と同じ音ばかり延々と打ち続けるのです。
研修が始まって最初の3ヶ月は、来る日も来る日も腕固めばかりです。
それが、その時期が過ぎると突然、自分の手が別の生き物のように動き出す感覚がやってくるといいます。
そんな基礎中の基礎のトレーニングを、燕三は今でも毎日続けているといいます。
人形浄瑠璃の三味線は、様々なドラマの中で季節や情景を表現し、登場人物それぞれの感情や心の揺れまでも音色や弾き方で表現するものです。
たった一つの音を鳴らすだけで登場人物の内面を伝え、かと思えば右手に持ったバチだけでなく、左手でも三味線の弦を激しく弾くこともあり、一つの楽器から、信じられないほど多彩な音が奏でられます。
目にも止まらぬバチさばきだけでも一見の価値があります。
人形浄瑠璃の舞台を観るときは、どうしても人形の動きに目を奪われてしまうのですが、皆さんもぜひ舞台上手、太夫の右手で端座する三味線弾きの名人芸を堪能してみてください。
人形遣い 一体の人形を3人で操る
人形浄瑠璃では一体の人形を、3人で操ります。
人形の首(かしら)と右手を操る「主遣い」、左手を操る「左遣い」、そして足を動かす「足遣い」、この3人が息を合わせて動かすことで、人形に命が宿ります。
新入りは、まず足遣いの修行から。
足遣い10年、左遣い10年、それからやっと主遣いができるようになるといいます。
人形の全身の動きや形をイメージしながら、それぞれの役割を徹底的に果たすことで、美しい人形の動きが生まれるのです。
桐竹勘十郎 人形遣いの第一人者
そんな人形遣いの第一人者である桐竹勘十郎もまた、足遣い10年、左遣い10年を経て主遣いの一人者となりました。
桐竹勘十郎は昭和28年(1953年)、二代目桐竹勘十郎の息子として生まれました。
しかし、この世界に入ったきっかけは、お父さんから「アルバイトせえへんか」と声を掛けられたことだったといいます。
同じく人形遣いの第一人者である二代目吉田玉男も勘十郎と同年の生まれ。
玉女の方は、一般家庭に生まれたのですが、中学の友達である勘十郎から声をかけられ、黒衣を身に付け、足遣いならぬ足持ちや、舞台周りの雑用を始めました。
そんな2人が共に人形遣いの第一人者となったのですから、歴史というのはおもしろいものですね。
その勘十郎も、30歳になるまで足遣いをしていました。
足遣いは、二尺八寸(約85㎝)の手すりが人形にとっての地面に当たるため、常に姿勢を低く保っていなければならないきつい仕事です。
人形がじっと座っていれば、中腰のまま両手を差し出し、頭を後ろにのけぞらせた姿勢を維持していなければなりません。
しかし、勘十郎は、足遣いも左遣いも好きだといいます。
特に、「主遣いと体を付けている足遣いは、人形と一体になれて楽しい」と。
しんどいけれども楽しい、好きだという気持ちが、勘十郎の日々の舞台を支えています。
このほかにも、勘十郎は人形浄瑠璃のすそ野を広げる活動を精力的に行っています。
その一つが国立文楽劇場のすぐ近くにある高津小学校での文楽の授業です。
足遣いから人形遣いの練習を始め、7ヶ月練習を重ねて「子ども文楽」発表会を開きます。
太夫から義太夫を習う太夫チームや、三味線チーム、そのほかお囃子チームも加わって、小学6年生と一緒に本格的な舞台を作り上げます。
そんな中から実際に太夫となった豊竹咲寿太夫も生まれました。
江戸時代から続いてきた人形浄瑠璃が、こうやって次の世代に受け継がれています。
3人の人間が動かしていることを忘れ、あたかも人形が自分の意思を持って動いているかのような、見事な人形の動きを見せる勘十郎ですが、実は動かない人形が一番難しいといいます。
ただじっと人形を持っている間も、人形に命を吹き込み続けなければ、人形も息をしなくなり、死んでしまうそうです。
そうやって息を吹き込まれ、命を持った人形たちの姿を、舞台で味わってはいかがでしょうか。
おわりに
人間が演じる舞台は生き物なので、二度と同じものはありません。
太夫の語りも、三味線の音も、人形の動きも、伝統の型を忠実に再現しながらも、毎回少しずつ違います。
人間国宝とされる人々が、それでもなお、深く掘り下げていく人形浄瑠璃の芸。
皆さんもぜひ一度、生の舞台をご覧ください。

初めて人形浄瑠璃を見る人は、その人形の美しさに驚くことでしょう。可憐な面立ちの人形が、生身の人間のように動き、喜び、悲しむのを見ているうちに、いつのまにか3人の人形遣いが操っていることをなど忘れてしまいます。
ここではそんな人形浄瑠璃の人形について、ご紹介します。

人形浄瑠璃と聞くと、「お上品でお堅いもの」と敷居が高いように思う方も多いのではないでしょうか。しかし、もともと庶民の娯楽だった人形浄瑠璃が、面白くないはずがありません。現代を生きる私たちにも十分共感できる思いが人形に託されて、より熱く激しく、華麗に演じられます。
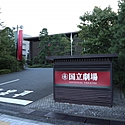
人形浄瑠璃の面白さを味わうためには、実際の舞台を見るのが一番です。しかし初心者にとっては、いつ、どこへ行けば人形浄瑠璃を見ることができるかさえ分からないでしょう。
ここではおもな年間スケジュールと、開催されている場所、また知っておけば舞台が10倍楽しめるお役立ち情報をご紹介します。