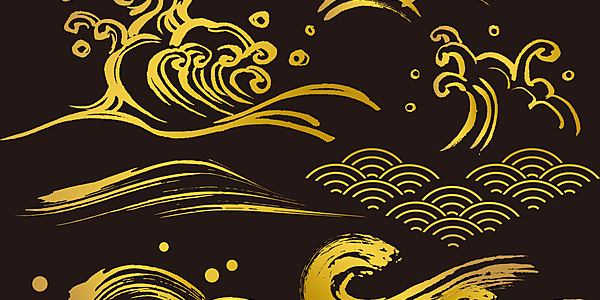歌川国貞(三代豊国)とは?天明6年~元治元年(1786年~1865年)
江戸時代後期の浮世絵師国貞は、初代歌川豊国の門下生です。
門下生の中でもとくに役者絵・美人画に優れた才能を発揮し、幕末最高の人気絵師となりました。
10代半ばの早い頃から初代豊国に弟子入りし、その才能の片鱗を見た豊国が大いに驚いたという話もあります。
そして着々と豊国の技術を吸収していった国貞は20代という若さで浮世絵師としてデビューを果しました。
最初の頃は一雄斎の号を名乗っていましたが、実家の家業は五ツ目の渡し場(船着き場。現在の東京都江東区亀戸五の橋)を経営する角田屋でしたので、それにちなんで「五渡亭」という号を名乗るようになります。
この五渡亭時代が国貞の人気絵師の道のはじまりでした。
国貞の画風の特徴は、その鋭い観察眼から生まれる人間の粋や生き生きとした動きや表情のバリエーションです。
当時の美人画は顔が細長く、首は太く短い面長猪首に描かれている特徴があります。
国貞は多数の美人画を描いていますが、それぞれの息づかいやにおいなどリアルに感じさせる画力があります。
歌川国貞の作品
「 大当狂言ノ内梶原源太」大判錦絵 文化11年~12年頃(1814年~1815年)
「大当狂言ノ内」とは、幕末の人気役者の首絵(似顔絵のバストショット)を描いたシリーズで、国貞の初期の代表作です。
3代目坂東三津五郎という人気役者が舞台上で、鎌倉時代の武将である梶原景季をモデルにした廓通いの色男を演じたものです。
この衣装、よく見てみると甲冑の大袖部分の柄をしているのですが、この時代の衣装のこだわりを感じますよね。
また、この作品は保存状態が極めて素晴らしく、背景の雲母摺は剥落らくせず、衣装の退色しやすい紫色も当初の状態のままを保ったまま見ることができます。
雲母摺とは色を塗った下地の上にキラキラとした雲母の粉(多くは貝殻の粉で代用)を振りかけたものです。
実際の展示物を見る際は、ぜひ背景や衣装の色に注目して見てみてください。
「 当世美人画 梅好きどり」大判錦絵
「きどり」とは真似をするという意味です。
「梅好」は、3代目尾上菊五郎という歌舞伎役者の俳名(俳句を書くときのペンネーム)で、芸名としても使っていました。
つまりこの作品は、人気歌舞伎役者をきどってポーズをつける美人遊女というテーマで描かれたものです。
客の相手をするのに疲れて部屋で一息つくところでしょうか。
加えた楊枝と気だるげに崩した体勢に色気を感じます。
当時の人は、美しい遊女の誰にも見せない姿を見てしまったような、今でいう女優のオフショットを見たような気持ちになったのかもしれませんね。
国貞の発想や着眼点には人間のリアルな美しさを感じます。
「 当世三十弍相 しまひができ相」大判錦絵 文政4年-5年(1821年-1822年)
三十弐相とは、女性の容姿に備わる美しさのすべてのことをいいます。
国貞はこの言葉をテーマにして、美人の何気ない動作を描きました。
「しまひ(い)」とは仕舞と書き、身仕舞い、つまり化粧をしていることを意味します。
この時代の化粧は首元まで白粉を塗りますから、着物をはだけさせたまま化粧の出来映えをしっかり確認しています。
合わせ鏡を使って後ろからの見え方も気にしていますから、きっとこの女性はおしゃれにとても気を配る人物だったのでしょう。
鏡台に注目してみると、白粉の容器と筆が見えます。
女性の方は、こんな小さな筆で顔全体を塗っていたのかとか、容器のデザインが素敵だなあと考えてしまうのではないでしょうか?
小道具に注目するのも浮世絵の楽しみ方の一つです。
「 今風化粧鏡 楊枝」大判錦絵 文政6年(1823年)
手鏡に映る女性を描いた10枚揃いのシリーズで、国貞の美人大首絵の代表作です。
この作品は江戸時代の歯ブラシ・房楊枝という、片方がつま楊枝でもう片方が筆のような形状をしたもので歯を磨いている様子です。
手に持っているのは歯磨き粉です。
この時代は紅入り歯磨き粉や塩や砂がよく使われていたようです。
驚くことにすでにこの時代には口臭ケアのために舌まで磨くという習慣ができていたようです。
このシリーズは様々な年代の女性をモデルにしており、他にも自分の眉に紙を隠しあてて、自分が既婚女性になって眉を剃ったときの姿を想像する可愛らしい少女の姿をした作品(「今風化粧鏡 眉かくし」)や、江戸で一番人気だった白粉「美艶仙女香」を塗ったあと、合わせ鏡で首の後ろまで丁寧に確認する女性描いた広告ポスターのような作品(「今風化粧鏡 合わせ鏡」)もあります。
「 隅田堤花盛の光景」大判錦絵3枚続 安政2年(1855年)
隅田堤とは、現在の東京都墨田区向島の三囲神社から墨田区堤通の木母寺のことを指し、現在は墨堤通りという名前になっています。
8代将軍徳川吉宗は享保2年(1717年)に桜100本を植え、享保11年には桃、柳、桜の計150本を追加して植えさせました。
当時から江戸を代表する桜の名所だったこの場所は、吉原にも近く、飲酒や鳴り物の許可も出ていたため花見をする人達で大変賑わいました。
奥をよく見てみると、隅田川の向こうの対岸には船着き場や三囲神社の鳥居が見えます。
他にも、茶屋でくつろぐ客や、桜を見物しながら楽しむ人達も見えます。
手前の遊女達は絶好の場所で桜を楽しみつつ、くつろいだ姿で馴染み客に手紙を書いているのでしょう。
人々の楽しそうな話し声が今にも聞こえてきそうな作品です。
「 揚巻の助六 八代目市川団十郎」大判錦絵 文久3年(1863年)
弘化元年(1844年)に絶大な人気を背景に3代目豊国となった国貞は大御所として君臨し続けました。
この作品は国貞晩年のシリーズである、人生最後の華を飾るように贅の限りを尽くした「役者大首絵 六○図」シリーズの一つです。
助六とは、歌舞伎演目「助六所縁江戸桜」に出てくる主人公の名前で、揚巻は助六の愛人です。
この助六所縁江戸桜は歌舞伎十八番の一つであり、上演するとなれば必ず満員になる大人気の演目です。
また、市川団十郎のお家芸でもありました。
この時モデルとなった8代目市川団十郎は人気絶頂の32歳です。
迫力とスター性のある顔立ちを存分に描き上げた一枚です。
おわりに
図らずも今回美人画を多く取り上げてしまいましたが、注目して欲しいのはその美人画のパターンの豊富さです。
筆者が感じたのは、国貞は「美しい女性モデル」として見るだけではなく、この時代を生きる女性のそれぞれの個性や生き様を描くのが上手いということです。
今にも話し声や息づかいが聞こえてきそうですよね。

今や海外でも大人気の浮世絵。海外の美術館などには「国宝級」とも称される、浮世絵の名作が所蔵されていることも珍しくありません。さらに展覧会が開かれれば大盛況。

鈴木春信(すずきはるのぶ)は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師です。春信の画風の特徴は、色っぽいというよりはどちらかというと可愛らしく、まろやかな雰囲気の繊細で優しげな甘い美人を描きます。本記事では、そんな人気浮世絵師・鈴木春信の代表作をご紹介します!

江戸時代後期の浮世絵師国芳は、初代歌川豊国の門下生です。幼少期から絵に興味を持っていた国芳は、北尾重政などの絵師の絵柄をまねて人物描画を練習したと言われています。

「富嶽三十六景」などで有名な浮世絵師・葛飾北斎。
世界で最も知られた浮世絵師といっても過言ではない葛飾北斎ですが、実は江戸時代後期を代表する奇人としても知られています。
特に引っ越しの回数は、生涯でなんと93回!
彼の奇人ぶりを語るエピソードとしてよく語られます。

葛飾北斎は生涯に渡り、表現を変えて波の絵を何点も描いています。中でも「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」は、北斎の傑作「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」の一つであり、海外でも広く知られています。今回は、葛飾北斎の描いた波の変遷をたどり、またなぜ葛飾北斎が波の表現を追求したのかについて迫ります。
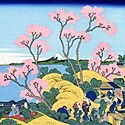
「富嶽三十六景」で有名な葛飾北斎を支えた娘・葛飾応為をご存知でしょうか?
自分自身も類まれなる絵画の才能を持ち、絵師として生涯を過ごした葛飾応為の画業人生とはどのようなものであったのか、代表作品などと共に見ていきましょう。