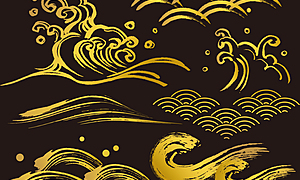歌川国芳とは?寛政9年~文久元年(1797年~1861年)
江戸時代後期の浮世絵師・歌川国芳は、初代歌川豊国の門下生です。
幼少期から絵に興味を持っていた国芳は、北尾重政などの絵師の絵柄をまねて人物描画を練習したといわれています。
豊国の門下として日々技術を学んでいた国芳でしたが、兄弟子の国貞が名声を高めていた間、10年あまりも日の目を見ることがありませんでした。
しかし、文政10年(1827年)頃に発刊された「通俗水滸傳豪傑百八人之壹人」シリーズが大当たりし、一躍大人気の絵師へと変貌。
このとき、国芳の力になったのは狂歌※も詠む尾張家御用商人・梅の屋鶴寿という人物でした。
※狂歌:洒落や風刺を効かせた滑稽な短歌
鶴寿は国芳の活発な江戸っ子気質と画風を気に入り、衣服を買い与えるなど様々な形で国芳を支えました。
この国芳の気質は作風にも現れており、反骨と風刺の効いた気持ちの良い描写は見る者を圧倒しました。
こうした斬新な国芳の感覚は人々の圧倒的支持を獲得し、多くの門下生を集め浮世絵師最大の派閥へと成長させました。
歌川国芳の代表作品
では、そんな歌川国芳はどんな作品を残したのでしょうか。
その一部をご紹介します。
「 通俗水滸伝 豪傑百八人一人 短冥次郎阮小吾」大判錦絵 文政10年~天保元年(1827年~1830年)
中国の小説「水滸伝」をテーマにしたシリーズの作品です。
本来は108人の豪傑を描いたと思われますが、現在確認できるのは74図です。
この作品は、中国の梁山泊という大沼沢の入り江で阮小五という人物が戦う姿を描いたものです。
水中に敵を引き込み、首をしっかりと捕らえたまま激しく戦う姿は今にも動き出しそうな迫力があります。
この作品の注目ポイントとしては、やはり上半身に緻密に描かれた刺青でしょう。
刺青には松と竹から鋭い視線を見せる豹が描かれています。
国芳の描いた水滸伝シリーズの惚れ惚れする刺青が若者達の間で話題を呼び、江戸で一躍刺青ブームが訪れたという背景もあります。
「 東都首尾の松之図」横大判錦絵 天保2年~3年(1831年-1832年)頃
「首尾の松」とは、隅田川の両国橋と吾妻橋の間にある堀にある松のことを指します。
この松は、吉原に向かう舟が通る場所にあるので、吉原へ行く人がこの松に「首尾良くいきますように」と験担ぎをしたことから名づけられたといいます。
しかし、国芳はこの松を主役にせず、隅田川に住むカニやフナムシを地面に近い視点で手前に大きく描いた奇抜な構図にしました。
すでに北斎や広重という絵師によって風景画は大成されたと思われていた時代に、新たな風を吹き込んだのが国芳だったのです。
さらに、国芳の風景画を鑑賞する際は、雲の表現にも注目していただきたいのですが、この波のようにゆるやかな雲の表現も国芳独自のものでした。
「 近江の国の勇婦於兼」大判錦絵 天保初期頃
平安時代末期、近江国の遊女お兼が川で洗濯をした帰りの途中で、激しくあばれていた馬の手綱を足駄で踏み押えて鎮めたところ、怪力が評判になったという説話をテーマに描いた作品です。
この陰影表現を強調した作風は洋風の絵画を彷彿とさせ、国芳独特の近代的造型感覚を味わうことができます。
国芳が得意とした山が奥に連なる遠近法や、漫画的にも見えるもくもくとした雲、飛び上がる馬の獰猛さと対照的に華奢な美人が描かれていますが、この美人が馬を鎮めさせるほどの強さを持っているという、見れば見るほど飽きのこない良さを感じる作品です。
「 東都富士見三十六景 山王神事 雪解の富士」大判錦絵 天保中頃
三十六景とタイトルがつけられていますが、現在確認できているのは5枚のシリーズになります。
この「山王神事 雪解の富士」という作品では、左奥に凜々しくそびえ立つ旧暦6月の富士を描き、手前には山王祭の山車が堂々とした姿で描かれています。
山王祭とは、東京都千代田区の日枝神社で現在も行われている大祭のことで、氏子の各町から山車や練り物を48台出して行列をおこないます。
日本橋本町を通過する春日龍神と浄妙坊・一来法師の山車を描いたもので、富士の手前で片手をついて飛び上がっているのが一来法師です。
また、右下の看板の「江戸の水」とは、式亭三馬の店が売り出した化粧品のことで、広告ポスターの要素もあります。
「 相馬の古内裏」大判錦絵3枚続 弘化元年(1844年)頃
本来の作品名は「相馬の古内裏に将門の姫君 瀧夜叉妖術を以て……」と続きますが、通称「相馬の古内裏」と呼ばれています。
江戸時代の読み物「善知鳥安方忠義伝」のワンシーンを大迫力に描いた作品として有名で、平安時代古内裏の地で大宅太郎光国が瀧夜叉姫の呼び出した骸骨の妖怪を倒そうとする緊迫の場面です。
実は、原作では等身大の骸骨がわらわらと現れる場面ですが、国芳はこのシーンを巨大な骸骨が現れるという構図で描き上げました。
「 みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」大判錦絵 嘉永頃
この作品を見ただけで国芳だ、とわかる人も多いのではないでしょうか。
国芳の遊び心があふれる人体合成画シリーズの一つで、人が寄り集まって人間の顔のかたちになった作品です。
裸の男達を大勢集めて造形したもので、眉毛は黒いふんどし、髷は棍棒をもった色黒の人で、唇はよく見てみると赤いふんどしということがわかります。
からだと襟は大男のうしろ姿ということですが……わかりますか?
左上には「大勢の人がよってたかって、とうとういい人をこしらえた。
とにかく、人の事は人にしてもらわないと、いい人には成らない」と書かれています。
お わりに
遊び心に富んだユニークな発想を持つ国芳は、近年大注目されている絵師です。
美人画や洋風画、武者絵に戯画など幅広いジャンルを得意とした国芳の発想は江戸時代から多くの人々を楽しませたことでしょう。
その想いは今日まで継がれ、現代人の心までもつかんで離しません。

今や海外でも大人気の浮世絵。海外の美術館などには「国宝級」とも称される、浮世絵の名作が所蔵されていることも珍しくありません。さらに展覧会が開かれれば大盛況。

鈴木春信(すずきはるのぶ)は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師です。春信の画風の特徴は、色っぽいというよりはどちらかというと可愛らしく、まろやかな雰囲気の繊細で優しげな甘い美人を描きます。本記事では、そんな人気浮世絵師・鈴木春信の代表作をご紹介します!
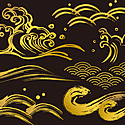
江戸時代後期の浮世絵師国貞は、初代歌川豊国の門下生です。門下生の中でもとくに役者絵・美人画に優れた才能を発揮し、幕末最高の人気絵師となりました。10代半ばの早い頃から初代豊国に弟子入りし、その才能の片鱗を見た豊国が大いに驚いたという話もあります。

「富嶽三十六景」などで有名な浮世絵師・葛飾北斎。
世界で最も知られた浮世絵師といっても過言ではない葛飾北斎ですが、実は江戸時代後期を代表する奇人としても知られています。
特に引っ越しの回数は、生涯でなんと93回!
彼の奇人ぶりを語るエピソードとしてよく語られます。

葛飾北斎は生涯に渡り、表現を変えて波の絵を何点も描いています。中でも「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」は、北斎の傑作「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」の一つであり、海外でも広く知られています。今回は、葛飾北斎の描いた波の変遷をたどり、またなぜ葛飾北斎が波の表現を追求したのかについて迫ります。
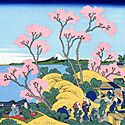
「富嶽三十六景」で有名な葛飾北斎を支えた娘・葛飾応為をご存知でしょうか?
自分自身も類まれなる絵画の才能を持ち、絵師として生涯を過ごした葛飾応為の画業人生とはどのようなものであったのか、代表作品などと共に見ていきましょう。