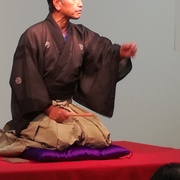舞妓の特徴といえば、白塗りのお化粧。
普通の人がやると大抵は馴染まないものですが、舞妓さんがするとなぜかとても綺麗ですよね。
当初は薄暗い室内で顔を目立たせるために始まったのですが、今では舞妓に欠かせないメイクとなっています。
この特徴的なメイクは「子どもっぽさ」を出すために、いろいろな工夫がされているのです。
今回はそんな舞妓のお化粧について、詳しくご紹介します。
メイクと一緒に合わせて注目したい、舞妓の髪型についても解説します。

子どもっぽさが大切な舞妓のお化粧とは
舞妓のメイクは基本的に毎日自分でおこないます。
メイク時間は慣れている舞妓で30分、新人舞妓だと1時間近くかかることもあるのだとか。
後ほどご紹介しますが、舞妓は襟足に「足」と呼ばれる特殊な塗り方をします。
襟足に細かいメイクをするのは難しいので、舞妓同士で塗り合ったり、下の舞妓が先輩舞妓の分を塗ったりするそうです。
それ以外は自分でおこなう舞妓のお化粧。
毎日していく中で、徐々に自分に似合うお化粧を見つけていくそうです。
冒頭でもお話ししましたが、舞妓のメイクは「子どもっぽさ」を演出する工夫がされています。
舞妓はもともと10代前半の子どもがなる職業でした。
そのため、メイクもお客様から「おぼこい(かわいらしい)」と感じてもらえるような子どもらしさを強調したものが良いとされています。
義務教育の関係で10代後半の舞妓が増えてきた現在は、ますます「子どもっぽく見せる」というメイクが重要となりました。
そんな舞妓のお化粧のやり方について、次章から見ていきましょう。
舞妓のお化粧のやり方

舞妓のお化粧は、4つの手順で進めていきます。
(1)下地を塗る
(2)おしろいを塗る
(3)アイライン、眉毛をかく
(4)唇に色をのせる
単純な作業に見えますが、それぞれとても慎重さ・正確さが必要。
いつもはおしゃべりな舞妓さんでも、お化粧の時だけは静かになるのだそうです。
それでは順番に詳しく見ていきましょう!
( 1)下地を塗る
舞妓のお化粧は、まず下地を塗るところから始めます。
下地を塗ること自体は女性の一般的な化粧と同じですが、舞妓の下地はちょっと違います。
舞妓メイクの下地に使うのは「鬢付け油」と呼ばれるもの。
お相撲さんや舞妓さんの髪を結うときに使われる油です。
鬢付け油は油なので、そのままではなかなか伸びません。
そのため、まず手の上で温めてから塗り広げます。
一般的な女性は、顔だけに下地を塗りますよね。
一方で舞妓の場合は、首や背中の方までおしろいを塗るので、首や背中にも下地を塗ります。
化粧ノリをよくするためにも下地は必須です。
( 2)おしろいを塗る

鬢付け油の下地を塗り終えたら、おしろいを塗っていきます。
普通はファンデーションなどを使いますが、舞妓の場合は「練り白粉(ねりおしろい)」を使います。
練り白粉はとても濃く、歌舞伎のメイクにも使われている白粉です。
練り白粉を適量、へらを使って容器に出し、水で溶いて使います。
必要な白粉の量は人によって変わるので、感覚を覚えるまでには少し時間がかかるようです。
白粉を塗るときには「板刷毛」という先が平らになっている筆を使います。
白粉を塗ったらパフを使って顔になじませていくのですが、やり直しができないのでどの舞妓さんも真剣です。
普段はお喋りな舞妓さんも黙ってしまうのだそう。
背中や首も、顔と同じように板刷毛で白粉を塗り、パフを使ってなじませていきます。
舞妓によっては、おでこや頬に薄く赤色を足す人もいるようです。
この時に使う赤は、一般的に売られているチークではありません。
次に紹介するアイラインで使う「棒紅」と呼ばれる固形状の紅です。
水で溶いて、白粉の上からのせていきます。
ここまで終わったら、1人でできるメイクは完成です。
次は襟足にも白粉を塗っていきます。
冒頭でもお話ししたように、襟足にメイクをするのは自分では難しいため、舞妓同士で協力し合います。
着物から見える襟足の部分は、首が長く見えるよう「足」と呼ばれる線をつくるのが決まり。
通常のお座敷のときには2本足を、紋付を着るようなときには3本足になるように塗っていきます。
綺麗な線を作るためには、とても慎重に行うことが必要です。
( 3)アイライン、眉毛をかく

白粉を塗り終わったら、次はアイラインと眉毛をかいていきます。
舞妓メイクのアイラインと眉毛は、黒だけではなく赤も入れます。
人によってはほとんど赤の場合も。
目じりに赤、眉毛にも赤を入れて、最後に少しだけ黒を足すことで、さりげなく子どもっぽさを演出しています。
舞妓のお化粧で使う赤は、「棒紅」と呼ばれる細く小さな固形状の紅です。
棒紅はその名の通り固形なので、容器にとり、水で溶いて塗っていきます。
ちなみに、まつ毛については自由で、黒のマスカラをする舞妓が多いようです。
( 4)唇に色をのせる
顔のお化粧が済んだら、最後に唇に紅をいれます。
使うのはアイライン等と同じく棒紅。
唇の荒れ防止や、つや出しのために、紅を塗った上から飴を溶かしたものを塗ることもあります。
一般的なお化粧のように唇全体に塗りたくなりますが、1年くらいの駆け出しの舞妓は下唇にしか紅をさしません。
新人舞妓だということを伝える意味と、おちょぼ口を演出し、子ども感を出すためなのだとか。
舞妓になってから1年以上たった舞妓は、上下とも赤を入れます。
メイクと同じくらい大切な舞妓の髪型とは

ここまで舞妓のお化粧についてご紹介してきました。
次はメイクと同じくらい大切な髪型についてご紹介しましょう。
舞妓の日本髪は地毛で結っています。
もともと短髪だった場合には、見習いのうちに伸ばす決まりです。
基本的には髪結いさんに結ってもらいます。
一度結ったら1週間くらいはそのままなので、できるだけ崩れないように過ごします。
普段お風呂に入るときもそのまま。
シャンプーは次の髪結いまでお預けです。
寝るときには「箱枕」と呼ばれる、高台の枕を使います。
時代劇でよく見かける箱のような枕です。最初は寝づらいようですが、慣れると問題なく寝られるそうです。
髪が崩れないようキツく結うので、舞妓期間が長いと結っている部分がハゲる人も多いのだとか。
芸妓になるとかつらになるため、伸ばしていた自分の髪の毛を切ることができます。
舞妓の中には、髪を切ることを楽しみにしている人もいるそう。

京都では、華やかな着物を着て歩く舞妓さんが観光客の注目を集めています。
かわいらしく、華のある舞妓は絵になりますよね。
しかし、実は舞妓は半人前の状態。舞妓を卒業して芸妓になって初めて、一人前の女性として活躍できるのです。
舞妓の髪型の種類

地毛で結う舞妓さんの髪型。
1種類しかないように思うかもしれませんが、実はいくつかあるのです。
期間限定の特別な髪型など、5種類の結い方をご紹介しましょう!
割 れしのぶ
最初にご紹介するのが「割れしのぶ」。
これは舞妓になってから1~2年の間だけの期間に限られた結い方です。
新人舞妓だということがわかる、かわいらしい髪型になっています。
お ふく
割れしのぶを卒業したら、「おふく」という結い方になります。
まげの下の部分を「おふくがけ」と呼ばれる布でおさえるために「おふく」と呼ばれます。
おふくがけは舞妓の年数によって決まりがあり、最初は赤い色のおふくがけしか使えません。
徐々に色が薄くなってピンク色になり、最終的には他の色も許されるようになります。
おふくがけの色によって、どのくらいの舞妓なのかがわかるのですね。
奴 島田

「おふく」が結える舞妓になると、「奴島田」が結えるようになります。
お正月と8月にある八朔のご挨拶回りのとき、黒紋付の正装をするときだけに結う髪型です。
ご挨拶回りとは、お姐さん芸妓や舞妓が連れ立って、ご贔屓にしているお茶屋さんや置屋へ挨拶をして回る行事のこと。
お正月には「今年もよろしくお願いします」というご挨拶を、8月の八朔の時期には「これからもよろしくお願いします」というご挨拶をしてまわります。
年に2シーズンしかしないので、見られたらラッキーです。

皆さんは、8月1日が「八月朔日」や「八朔」と別の呼び方をされることをご存知でしょうか?京都・祇園では「八朔」は特別な日であり、夏の風物詩としても知られています。この記事では、八朔とは何か、どのような歴史があるのか、そして舞妓さんとの関係やどのようなことが行われるのか、八朔についてご紹介します!
勝 山
祇園祭の前後の時期にだけ結える、特別な髪型が「勝山」です。
普段の髪型よりも豪華で、大きく見える髪型。
奴島田よりも期間が限定されているので、稀少です。
他にも、節分の時にはいつもと違うかんざしをつけて楽しむこともあるのだとか。
先 笄
舞妓をやめるときになったら結うのが「先笄」という結い方。
卒業前の2週間くらい、この髪型になります。
「舞妓をやめます」というときに舞う「黒髪」という舞と合わせて、大人になったということを表しています。
おわりに
舞妓さんは毎日30分~1時間もかけて、舞妓に変身しています。
使っているメイク道具も特別なものが多く、数日で完璧に使いこなせるものではありません。
化粧を落とすにはベビーオイルを塗り、少しずつ落としていくそう。
メイクにも、メイク落としにも時間がかかる大変な作業なのです。
同じく髪型も興味深いものでした。
季節や舞妓さんの位によって結える髪型が変わるので、見かけたら結い方の種類を当ててみるのもおもしろいかもしれません。
実際にメイクや着物を着て、舞妓体験ができる写真館などもあります。
ご自身で舞妓体験をすることで、文化に触れることができるはずです。

女の子なら一度は舞妓さんに憧れるかもしれません。
しかし実際に舞妓になるには、厳しいお稽古だけでなく年齢の制限もあります。
1日だけでも舞妓さんになってみたい!という方にオススメなのが「舞妓体験」です!
京都には、舞妓さんと同じメイクをして、同じ着物を着られる体験ができるお店が多くあります。

京都といえば舞妓が思い浮かぶほど、舞妓の存在は広く知られています。
しかし、舞妓の先にいる「芸妓」の存在に注目する人は少ないのではないでしょうか?
舞妓は見習い期間の女性のことで、半人前の芸妓のことをいいます。