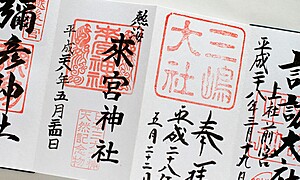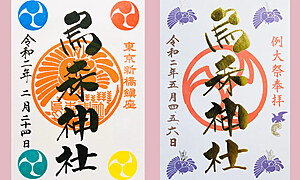生きていると、「縁を切りたい」と思う事柄に少なからず遭遇します。
それは人だけに限らず、悪運や悪い癖なども含まれます。
しかし、これらを自分の努力や意志だけで断ち切ることは難しいもの……。
そんな時は、縁切りで有名な神社やお寺を訪問してみてはいかがですか?
ここでは、東京都で最強の縁切り神社やお寺を紹介します。
高いご利益があるといわれている神社やお寺を厳選していますので、参考にしてみてください!
※本記事の内容は令和6年(2024年)7月時点のものです。
掲載内容は変更していることもありますので、正式な情報については事前に各社寺へお問い合わせください。
東京で最強の縁切り神社・お寺① 縁切榎
「縁切榎・榎大六天神」は、東京で最強!といわれている縁切り神社です。
そのご利益の噂は江戸時代にまで遡り、嫁入り前の女性は御神木である縁切榎の横を通ってはいけないと伝えられていました。
文久元年(1861年)に皇女・和宮親子内親王が都から地方へ赴く際には、縁切榎の横を通らなくても済むように迂回路ができたほど、その効果は大変強いとされています。
現在、縁切榎には囲いが作られていますが、これは縁切りのご利益を受けたいと願った多くの人たちが縁切榎の皮を剥いで持ち去ってしまうため、それを防ぐための対策です。
縁切榎は横を通るだけで充分なご利益が得られるとされていますが、縁切榎の皮を煎じて飲むと、より縁切りのご利益が強く現れると信じられていました。
また、縁切榎だけではなく、絵馬にも強い縁切りのご利益があるとされています。
絵馬を購入して願い事を書くと、どんな縁も断ち切られるとされ、縁切りを強く願う多くの人たちが訪れているんですよ。
なお、現在の縁切榎は三代目。
初代の縁切榎は境内に保存されているので、訪れた際はぜひご覧ください。
東京で最強の縁切り神社・お寺② 豊川稲荷東京別院
東京の港区赤坂にある豊川稲荷東京別院は、豊川ダ枳尼眞天をお祀りしているお寺です。
“稲荷”というと狐をお祀りしている印象があると思いますが、これは豊川ダ枳尼眞天が稲穂を担いで白い狐に跨っていたことに由来します。
豊川ダ枳尼眞天は悪縁切りのほか、商売繁盛や家内安全のご利益もあるとされ、多くの参拝客が訪れます。
ただ、豊川稲荷東京別院が縁切りに強いお寺だといわれているのは、豊川ダ枳尼眞天が御祭神だからという理由だけではありません。
豊川稲荷東京別院の境内の奥には、叶稲荷尊天をお祀りしているお社が安置されています。
悪縁切りのご利益では、こちらのお社の方が効果絶大といわれています。
あらゆる人間関係の悪縁切りに加え厄の縁切り、因縁除けのご利益もあるとされています。
お参りすることで、悪縁を切るとともに同じような悪縁から守ってくださるということです。
なお、境内奥には恋愛や縁結びのご利益で有名な愛染明王がお祀りされています。
さらにその両隣には、源頼朝と北条政子に縁りのある“縁結びのご神木”と呼ばれる梛の木もあるので、縁切りの祈願後に立ち寄るのも良いでしょう♪
東京で最強の縁切り神社・お寺③ 陽運寺
陽運寺は、“東海道四谷怪談”のお岩さんをお祀りしているお寺で、「於岩稲荷」や「於岩稲荷陽運寺」とも呼ばれています。
ご本堂にはお岩さんの木像を安置、そして境内には昭和32年(1957年)に新宿区から文化財に指定されたお岩さん縁りの井戸があります。
“東海道四谷怪談”は歌舞伎などの演目で行われることもあるため、歌舞伎興行の際に成功や安全を願って関係者が参拝に訪れます。
また、悪縁切りとしても大変有名なお寺です。
特に異性関係での悪縁切りに強く、悪縁を切った後、良縁をもたらしてくださるともいわれています。
悪縁切りと縁結びは一見正反対に感じますが、良縁を得るためには先に悪縁を切らなければなりません。
そのため、悪縁切りだけではなく、良縁を求める人たちが縁結びのご利益をいただくためにも訪れるのです。

江戸時代に一世を風靡し、今なお映画や小説で語り継がれる『四谷怪談』。貞女・お岩と色悪・伊右衛門の愛憎劇を発端とする怪談は、何故こんなにも私達の心を惹きつけてやまないのでしょうか?今回は、お岩の祟りは実在するのかなど、四谷怪談の物語や知られざる真実、その歴史をご紹介します。
東京で最強の縁切り神社・お寺④ 於岩稲荷田宮神社

「於岩稲荷田宮神社」は、陽運寺のほぼ向かいにある神社です。
豊受比売大神と怪談『東海道四谷怪談 』のお岩さんとして有名な、田宮於岩命を祀っています。
もともとこの神社は、幕府の先手組※である田宮家の邸内社でした。
この社を篤く信仰していた初代田宮又左衛門の娘・お岩が亡くなった際、夫・伊右衛門がお稲荷様にお岩の霊を合祀。
これを人々が“お岩さんの稲荷”と呼んで崇敬するようになりました。
お岩さんは夫を支え、家を再興したことから良妻賢母として地元の人々の崇敬を集めていた女性です。
当初は女性の守り神とみなされていましたが、彼女の死後200年たってから『東海道四谷怪談』が大流行。
浮気をされて幽霊として復讐を果たすお岩さんのイメージから、縁切りを祈願する人が増えたようです。
とくに自分に執着してくる人、つまりストーカーとの悪縁を断ち切りたい方からの人気を集めています。
しっかり縁切りをお願いしたい方は、御祈祷願札に願い事や悩みを書いて賽銭箱に入れておくと、あとで神主さんが御祈祷してくれますよ。
※先手組:江戸幕府の職の一つ。江戸城の門の警備や将軍外出時の護衛、市内警備などを行った。
東京で最強の縁切り神社・お寺⑤ 抜弁天厳嶋神社
抜弁天厳嶋神社は、正式名称を「厳嶋神社」といい、かつてはこの地域で最も高地であったため富士山を望むこともできたそうです。
平安時代後期の武将である源義家が、戦地の奥州(現在の岩手県)へ赴く途中のその場所で、富士山の方角にある安芸(現在の広島県)の厳島神社に向かい戦勝を祈願、その後、勝利の暁として創建された神社です。
厳嶋神社は市杵島姫命のほかに戦女神や縁結び・縁切りと恋愛成就のご利益でも高名な弁財天も祀ることから、江戸六弁天や新宿山之手七福神の一つとしても数えられており、通称を「抜弁天」といいます。
この通称が付いたのには諸説あり、一つは先ほどの源義家が苦難を切り抜けた逸話によるものと、もう一つは南北に伸びる参道があり境内を通り抜けられることからというもの。
いずれの説からも人間関係含む苦しい状況を“抜け出す”という点で、悪縁切りのご利益が強いとされる神社です。
打破したい状況や人間関係がある方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか?
東京で最強の縁切り神社・お寺⑥ 宝禄稲荷神社
宝禄稲荷神社は、宝くじ等の“外れくじ”を供養することができる一風変わった縁切りの神社です。
その昔、大変くじ運の悪い百姓がいました。
ある日、外れてしまった富くじ※を通りがかった祠に置いてみたところ、次に購入したくじが大当たり!
それ以降、何をしても良いことが起こった百姓は、祠の神様が助けてくださったに違いないと考え、立派なお社を建てました。
それが、現在の宝禄稲荷神社です。
以来、宝禄稲荷神社にお参りをすると、特に金運に関する悪運との縁切りができるといわれ、宝くじやギャンブルなどで悪運に取り憑かれてしまった人が福を呼び込むべく、外れくじと縁切りしに訪れます。
また、それ以外にも勝負事全般にもご利益があります。
何度挑戦しても合格しない試験や、どうしても勝てない試合などの前に訪れると悪い縁が切れて、幸運が舞い込むのだそうです。
なお、5月22日には“外れくじ供養”の宝禄祭が催されます。
勝運を授かることができる“宝禄狐”に触れられたり、普段は見られない“宝禄稲荷勝運札”などの縁起物を入手できる機会なので、日程を調整して訪れるのもオススメです。
現在は1,000円以上の金額を神社あてに振り込むと、宝禄祭で外れくじを供養していただけます。
神社に足を運ばなくても供養ができますので、遠方の方や参拝が難しい場合はぜひ活用してみてください。
※富くじ:江戸時代に神社仏閣で行われていた宝くじのようなもの。番号が入った木札等を販売し、当選者には賞金を支払っていた。
東京で最強の縁切り神社・お寺⑦ 井の頭弁財天

「井の頭弁財天」は、三鷹市と武蔵野市一帯に広がる“井の頭公園”内の小島に建つお社です。
平安時代末期、源経基が弁財天像をこの地に安置し、のちに源頼朝が社を建立したもので、徳川家康も訪れたといわれています。
現在では、池でボート遊びもできる人気の公園なのですが、「カップルでボートに乗ると別れる」という都市伝説があります。
これは、弁財天が七福神唯一の女神であることから、参拝に来たカップルに嫉妬し、別れさせたという江戸時代の噂の名残なのだとか。
そんなことから縁切りスポットとして有名になり、境内では縁切りのお守りやお札が販売されています。
悪縁立ちを望む方は、そちらを購入して弁財天に祈願するのがよいでしょう。
地元のカップルは今でも敬遠するとも言われていますが、「眉毛のついたオスのスワンボートに乗れば、その嫉妬を避けて別れない」とも言われていますよ。
なお、ご本尊である8本の手を持つ弁財天は、12年に1度、巳年の数日だけ御開帳される秘仏。
次の御開帳は、令和7年(2025年)に予定されています。
東京で最強の縁切り神社・お寺⑧ 明治神宮

「明治神宮」は、第122代明治天皇とその皇后である昭憲皇太后を祭神とする神社です。
三が日の参拝客が日本一多い神社で、毎年約300万人近くが初詣に訪れています。
敷地が広いことが特徴で、本殿や御苑のある“内苑”、神宮球場や絵画館のある“外苑”を、約70万㎡もの林が包んでいます。

国内最大級のパワースポットと言われており、縁結びのご利益が有名であることから、結婚式場としても人気があります。
一方で、神社全体のパワーが強いことから、厄除け、縁切りのご利益も絶大なのだそうです。
見どころは、戦国武将・加藤清正が掘ったとされる清正井。
絶えることなく水が出続けることから、悪い気を浄化して運気をアップさせるパワースポットとして話題を集めています。
悪縁を断ち切り、良い縁を呼び込みたい方にぴったりですね。
雨の日や夕暮れ時は逆に悪い気をもらってしまうそうなので、晴れた日の午前中に訪れるのがオススメです!
東京で最強の縁切り神社・お寺⑨ 赤坂氷川神社

「赤坂氷川神社」は、江戸時代に創建された後、震災や空襲に見舞われたにもかかわらず、当時の姿のまま残っているというその運の強さで有名な神社です。
さまざまなご利益がありますが、とくに恋愛系のご利益で知られており、東京三大縁結び神社の一つに数えられています。
月に1回の“縁結び参り”という神事では、縁結びのパワーアイテム“四合御櫛”が授与されることから、良縁を求め多くの方が訪れます。
一方で、悪縁を断ち切る縁切りのパワーも。
使い古したり破損したりした包丁を奉納し信仰するための“包丁塚”が境内にあることから、包丁の「切る」にちなんで、悪縁を断ち切る縁切り神社としても信仰されるようになりました。
その他にも、幕末志士・勝海舟が命名した“四合稲荷”や推定樹齢400年の“大銀杏”など、観光スポットとして楽しめる名物もありますので、縁切りをした後にあわせて回るのがオススメです。
東京で最強の縁切り神社・お寺⑩ 日比谷神社

「日比谷神社」は、東京都港区のビル街の一角にある神社です。
ご祭神は、農業の神である“豊受大神”と、穢れを祓う“祓戸四柱大神”という神様です。
祓戸四柱大神は、4人の神様の総称で、“瀬織津比売”・“速開都比売”・“気吹戸主”・“速佐須良比売”の4人を指します。
まず瀬織津比売が、この世のあらゆる災いや罪、穢れを川から海へと流します。
それを海の底にいる速開都比売が飲み込んで、気吹戸主が海低のさらなる底にある国へ一気に吹き放ちます。
最後に、その国にいる速佐須良比売が、これらをきれいさっぱり消し去り浄化してくれるのです。
神様4人がかりで、悪縁や悪い環境を浄化して消し去ってくれるとは、なんとも頼もしいですよね。
また、縁切りだけでなく、こちらでは運気アップも期待できます。
もともとは日比谷公園内にあった神社なのですが、過去に3度も移転しており、そのたびに復活したという奇跡的な歴史から“奇跡のお守り”がおかれています。
悪縁を断ち切り、良縁を運び込むパワーをしっかりいただいて帰りましょう!
おわりに
東京で最強の縁切り神社・お寺10選を紹介しましたが、いかがでしたか?
人生の中で、切りたいけれどもどうしても切れない悪縁というものには遭遇するものです。
自分ではどうしようもなくなった悪縁は、そのままにしておくとさらなる悪い状況を引き寄せてしまうかもしれません。
そんな時は、ぜひ、今回紹介した縁切り神社・お寺を訪れてみてはいかがでしょうか。
神様の力を借りることで、悪縁が切れて良縁が舞い込むこともあります。
お悩みの際には一歩踏み出し、ぜひ、紹介した神社やお寺を訪れてみてください。

京都最強の縁切り神社と名高い「安井金比羅宮」など、京都の縁切り神社・お寺・スポットをご紹介します。人間関係や男女関係、病気などの悪縁を断ち、良縁を結びましょう。

京都最強の「安井金毘羅宮」、東京で有名な「豊川稲荷東京別院」など、全国から選りすぐりの“悪縁”をバッサリ切ってくれると話題の縁切り神社・お寺を20選ご紹介!人との縁以外にも、病気との縁、煙草やアルコールといった辞めたくても辞められない縁などの縁切りにも効果的ですので、ぜひ参考にしてみてください。

「菊野大明神 きくのだいみょうじん」は、京都最強の縁切り神社として注目される知る人ぞ知るスポットです。 悪縁をスッパリと断ち切るそのご利益は、地元の方も恐れるほど強力だと語り継がれています。今回は、菊野大明神に古くから伝わる由緒や伝説、参拝方法や周辺散策にぴったりなオススメ観光スポットを詳しくご紹介していきます!

厄年の方必見!東京都内で最強の厄除け・厄払いにオススメの神社・お寺を紹介します。災難や不運に見舞われることが多いとされる節目の年齢、“厄年”。同じ厄除け・厄払いをするのなら、強いご利益のある神社で行いたいもの。アクセスの良い神社・お寺を厳選していますので、ぜひ参考にしてください。

お寺と神社の違いは宗教で、お寺は仏教、神社は神道の宗教施設です。お寺は「仏様」を祀り仏像やお墓があり、「神様」を祀る神社には鳥居やご神体があるなど建物も異なれば参拝方法も違います。この記事では、お寺と神社の違いについて徹底的に解説します!

神社には必ず、〇〇神社や〇〇神宮といった社号(名前)が付いています。社号の前半部分には、その神社に祀られている神に関わるもの、建っている土地に関するものなどの名称がきますが、社号の後半部分にくる神宮、大社、宮、神社などは一体どのような意味があるのでしょうか。謎だらけの神社を社号や祭神から解説します。
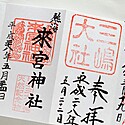
お寺や神社の御朱印とは、お参りした際の証しとして寺社から出される印を押した証明書です。1冊の御朱印帳に寺社の御朱印を混在させても問題はありません。今回は、御朱印の歴史やお寺と神社の御朱印の違い、もらい方や御朱印帳の入手法など、御朱印について詳しくご紹介します。

教科書にも載っている「平等院」はお寺?神社?それとも誰かの住居?初詣で有名な成田山って新勝寺とは違うの?など、疑問に思ったことありませんか?平等院も成田山もお寺です。同じお寺なのにどうして〇〇寺と付かない名前があるのでしょうか。ここでは、そんなお寺の種類に関する素朴な疑問を解き明かします。

日本にはかつて檀家制度というものがありました。
どこの家も、かならずお寺に所属し、お葬式や法事などを行ってもらう代わりに、お布施を払う、というものです。