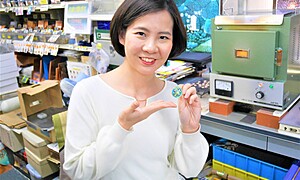古くから愛されてきた銀器。
その歴史は古く、現在日本では東京が主要な産地となっている。
「東京銀器」は昭和54年に経済産業大臣より伝統的工芸品として指定され、台東区や荒川区を中心に、アクセサリーや日用品など幅広い銀製品が作られている。
東京都台東区浅草に工房を構える銀泉いづみけんもその一つだ。
数々の大会でも受賞している銀泉いづみけんは、伝統の技術と江戸の粋さを現代的なデザインに落とし込んだ作品が特徴的だ。

一つひとつ、丁寧に作られた作品はHPや店頭、出張や通信などでも販売されており、現在は、銀製品をもっと身近に感じてもらうべく、工房内で体験教室を開催し、学生旅行の思い出作りとしても人気を集めている。
今回は、平成7年に東京銀器の伝統工芸士に認定され、文化学院金工非常勤講師も務めていた泉健一郎氏にお話を伺った。

ワゴコロ編集部による、東京都台東区浅草にある「銀泉いづみけん」さんでの“東京銀器のバングル作り体験”レポートです。
“黄金の茶道具”が伝統工芸士となるきっかけだった

独立する直前に勤めていた、金属加工会社でのこと。
ある日、”黄金の茶道具”の注文が入った。
器物は他の専門のところに依頼できたものの、台子だけは何処もできないということで泉氏自身が引き受けることになった。
「まるで死刑台に登るような気持ちでしたね。」
その言葉からは、どれだけ難しい作業であったかが伺える。
特に難しかったのが、茶道具を置いている天板。
中に木が入っており、その表面に薄い純金を巻いて貼っているのだが、広い面に気泡が入らないよう、ピタリと金を貼りつけることが、非常に大変だったそうだ。
何度も何度も練習しては失敗を繰り返すほどで、先輩や営業の方に相談をしながら試行錯誤の日々を送ったのだという。
そして、やっとの想いで完成した作品は、予想以上の評価を獲得することとなった。

そのとき、後から出来上がった記録誌末尾に、製作に関わった人達と自分の名前が書き連ねてあり、そこに伝統工芸士という称号が付けられていたのでこれはそうならねばと思ったそう。
伝統工芸士の国家資格を取るには、実務経験12年以上かつ、組合毎に行われる実技試験に合格しなくてはならない。-
現在も制限時間の中で、渡された図面をもとに作品も製作するというものである。
持てる力をすべて尽くし実技試験に合格をした泉氏は、鍛金職人という伝統工芸士の道を歩みはじめた。
そして、彫金も並行しながら今では実技試験の試験官も務めるようになった。
写真そっくり!銀で作るペットのレリーフ(彫金)

ペ ットのレリーフ制作に至った経緯
ある時、泉氏の友人のペットの犬が亡くなってしまった。
そこで、その亡くなってしまったペットの写真をもとにレリーフを作ってみたところ、友人がとても喜んでくれた。
「やはり、形に残るというのはすごく喜ばれましたね。」
もともと猫の作品作りは行っていたものの、犬は難しいだろうと挑戦していなかったそうだ。
しかし、この件をきっかけに、子犬を中心とした犬のレリーフも制作するようになったという。
作 品へのこだわり
特に、犬の「目」の部分にこだわりを持っているという。
銀板を打ち出し、黒く光らせることでより本物に近い「目」を作り出すのだ。
一枚の銀板だけで作り上げていく、まさに職人技である。
しかし「目」は作る者の心の状態が如実に現れてしまうので非常に難しい作業であるが、完成したときはホッと本来の自分に還るような気持ちになるそうだ。
泉氏自らの目で写真を見ながら、繊細なペットたちの表情や立体感を演出していくため、出来上がった作品は、まさに本物のペットそのものである。
世界的アーティストも着用!般若心経ブレスレット

東京銀器の技法は「鍛金」と「彫金」と「寄せ物」に分かれる。
鍛金とは器物の内側に鉄の道具を当て、外から金槌を打ち付けて金属の形を変えていく技法で、彫金とは先端の形状が様々な数㎝の鉄の棒である鏨を小さな金鎚で打ちつけて金属に彫刻や打ち出しをしていく技法。
寄せ物とは、部品を溶接合(ろう付け)して組み纏める技法で、箱もの等もこれに入る。
その鍛金、彫金の技術を組み合わせてうまれた作品が、『般若心経ブレスレット』。
般若心経の文字は大きな刻印鉄型をプレスしているが、その原型は手彫りにて彫金の技法で作られている。
2㎜四方の中に漢字一文字を書くだけでも大変なことなのに、先の細い鏨で彫り並べ、しかも深さが必要なため三度も彫りなぞるという、こちらも大変骨が折れる作業だ。
般 若心経ブレスレット制作のきっかけ
以前、新潟へ出張に行った際、「般若心経のブレスレットを持っているけれど、すごく薄くて、もっとしっかりしたものが欲しい」と、ある方からリクエストがあった。
こんな抹香臭いもの商品になれるだろうかと悩んだ末、最初はローマ字で彫った般若心経のブレスレットを制作。
とても喜んでくれたが、一年後にやはり漢字のものが欲しいという要望をいただき、翌年
この作品を完成させたという。
計らずもこれがやがてベストセラーとなるのだが、まさにお客様の言葉から生まれた作品なのだ。

エ リック・クラプトンがコンサートで着用!
この般若心経ブレスレットは、あのエリック・クラプトンも使用してくれたことがあるそうだ。
最初は、どうにか作品を届けたいという想いでコンサートに訪れた泉氏。
接点に苦労しながらもなんとかエリック・クラプトンの手に渡った数日後、事務所の担当者から「彼が般若心経の意味を知りたがっているので日本語でいいから手紙で教えてほしい」と電話がきたという。
さっそく書き綴って送付し、2回目に観に行ったコンサートでは、実際に右腕に付けているところをアリーナ席から拝むことができて、彼の優しさに感動したそうだ。
さ らに進化した「市松般若心経バングルブレスレット」作品へのこだわり

上記の般若心経ブレスレットの表面に、内側の文字が消えないよう市松模様を打ち出す。
不可能と思える提案を「東京手仕事」という促進支援団体のスタッフ方に頂いたのがきっかけであり、できませんとお断りしたものの悔しくてその晩、寝床で思い巡らしたところ妙案がひらめき可能となった次第だそうな。
二種の金槌を使い、小さく細かなチェッカー柄を淡々と打っていく。
平らな状態から打ち出す方が簡単であるのに、わざわざ丸めてから市松模様を打ち出すのは、丸めた状態で打った方が柄の美しさが出せるからだという。
その工程は以下、鍛金のぐいのみの項にて解説、実に繊細で、気が遠くなるような作業だ。
脱着の際に手首が痛くないよう、バングルにひとつも角がないことを再確認することも怠らないという。
市松紋打ちは手作業100パーセントの仕事、一日いくつも打てないからこそ、気が入っていくパワーを感じる。
東京都知事賞を受賞した名作【桜一枝】

制 作のきっかけ
泉氏が桜の木の下を歩いていた時にえらく枝ぶりの美しい桜があり、その一生懸命咲いている桜の姿を見て、「これだ!」と感じたそうだ。
なによりも、桜は咲く時間は短いが、日本人にとって特別な存在であることも理由の一つであった。
作 品へのこだわり
満開の花びらにしないということ。
そして、全ての桜の花の顔を正面に向けないということ。
初めに感動した大きな流線をいつも念頭に置くこと。
この3点にこだわったことで、より自然でリアリティのある桜に仕上がった。

本 物の花びらに近づけたからこその苦労
花びらの一つひとつは一枚の板から形を作っているため、接合は「はんだ付け」ではなく、「ろう付け」という手法で行った。
はんだ付けとろう付けはよく似た溶接手法であるが、450℃以下で液体となる錫と鉛の合金「はんだ」に対し、「ろう」は銀が主材で500℃以上で液体となり母体と融合しあう。
強い熱によって溶けるろうは、固着後に銀同士が強く接合されるため、接合強度ははんだを上回り、百年以上ももつのだ。
しかし、これがなかなか大変な作業だった。
一ヶ所を留めるだけなら難しくはないのだが、花と枝の接合部分を一気に留めなければならないので非常に苦戦したという。
銀は素早く温度を伝えるため、炙っていても熱が逃げてしまいなかなか温度が上がらない。
そのため、枝全体を温めてから桜の花を付ける根本の部分に集中して熱を当て、接合を行った。
桜の花びらは本物のように薄いため、すぐに溶けてしまう。
「どこかに溶けかかっているのがあるよ」と、笑って話をしてくださった。
イタリア・北欧視察を通して感じたこと・学んだこと

銀 製品の本場で得たもの
泉氏は平成5年に前職場を退職した後、イタリア・北欧に1ヶ月間ほど視察へ訪れた。
日本の陶磁器のように、現地では銀製品が日常的に溢れていたことに、大変感銘を受けたそうだ。
現地の図書館でさまざまなデザインの資料を見て、「これは良い」と思うものにたくさん出会えたのだという。
しかし、まったく同じデザインを作りたいとは思わないそうだ。
そもそも、”良いデザイン”は、”新たなデザイン”を閃かせてくれるもの。
「今あるものを真似するのでは意味がない。新しいものを作ることにしか興味がないから」と語る泉氏。
だからこそ、この本場(イタリア)に無い新しい物を日本で作りたい。
そんな気持ちが生まれたのだという。

今 に繋がっていること
イタリアでの奇抜なデザインとの出会いにより、「枠に囚われる必要なはい」ということを学んだそうだ。
その奇抜なデザインのひとつにはなんと、使い古したさまざまな形の“消しゴム”に穴を開けてネックレスにしているというもの。
「あの消しゴムネックレスを思い出すと、どんなに行き詰まったときでも、”デザインは無限なのだ”ということを思い出し、救われます。」と、笑顔で語ってくれた。
それは、現在においても泉氏の作品の中に活きている。
それ以来、常に自由な発想で作品作りを行うことを大切にしているのだそうだ。
泉健一郎×東京銀器

東 京銀器の職人になろうと思ったきっかけ
小さい頃から絵を描くことが好きで、画家という選択肢も考えていました。
しかし文化系の専門学校を卒業後、進路に迷いながら、歩いて日本列島の旅に出発しました。
とあるお寺で出会った和尚さんに、「あなたは絵が好きなの?画家になりたいの?」と言われて。
ハッとしましたね。
そうか、もし本当に画家になりたいのだったら、寝る間も惜しんで絵を描いているはず。
絵を描くことに対して、そこまで熱意があったわけではないことに気付かされました。
しかし、ものづくりをしたいという気持ちは変わらず、手放したくありませんでした。
このことに気付けたことが、私にとって人生のターニングポイントでした。
帰宅後に、工芸を扱うようなものづくりの仕事を探しましたが、ハローワーク(当時は職業安定所)ではなかなか求人が見つかりませんでした。
そこで、「モノ」を作る仕事に変わりないだろうと、近所にあった設計事務所への就職希望を面接官に出したところ、「設計は君がやってきたことと違うだろ。なぜ自分が耕してきた畑に種を蒔いて育てないんだ」と叱ってくれました。
素直にその通りだと思いトボトボと帰る道すがら、偶然立ち寄った本屋さんで買った就職情報誌に、たまたま募集をしていた東京銀器の求人を目にしました。
「貴金属工芸」という文字が目に飛び込んできて、すぐに見学へと向かいました。
しかし、銀製品というのは日常生活であまり馴染みのないもの、縁遠いものだと感じました。
もっと身近なものを作りたいと悩んでいると、「昔から籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人といってね、人それぞれに役目があって分担して世の中廻っているんだよ」と母が話してくれたんです。
なんだか少し気が楽になりましたね。
「まずは挑戦してみるか。」
母の言葉に奮い立たされ、東京銀器を扱う会社に就職を決めました。
修 行して初めてわかった銀器の世界

身を粉にして修行する毎日を送っているうちに、いつしか銀の魅力に取り付かれていました。
自分の命よりもはるか昔、地球が出来た頃からある銀。
それが集まって、今この手元にあるという感動は大きいですね。
熱や電気を伝えやすく、経年変化で使い込むほど味わいがでてくる。
銀はとても素直な素材で、たくさんの魅力があります。
修行中は辛いというよりも、ものづくりが好きだから楽しかったです。
ただ、最初の1年目は毎日いろいろな同じことの繰り返し。
その頃やっていたひとつが、炭研ぎという作業でした。
製作中についた傷などをとる仕上げ作業で、1日中地べたに座り、洗面器を置き、すり板に乗せ擦り続けていました。
すると4、5日で手が擦り剝けて血が出てきます。
しかし、それでも膿まないんです。
なぜなら、炭には殺菌作用があるから。
ちょっとした切り傷は、墨研ぎを行っている内に自然に殺菌・治癒できるんですね。
そんなことを毎日していました。
東 京銀器職人として譲れないこだわり

まず、第一に人の真似はしないということ。
そして、使う相手のことを考えること。
いくらデザインが良くても、実用性がなければ良作とは言えません。
失敗してもやり直しを続け、納得のいくまで作り込みます。
昔、とある方が「仕事は哲学を教えてくれる」と言っていたのですが、職人となった今、この言葉の意味が本当に良く分かります。
製造工程
1 、生し(なまし)
使用する地金を加熱し、加工しやすいように柔らかくする。
2 、地金とり
作品に必要となる寸法を割り出し、銀の板から鋏で切り出す。
3 、鍛金(絞り)
一枚の金属板を叩いて加工する、金属工芸の技法。
今回は鍛金「絞り」の中でも、市松紋仕上げ技法を見せてもらった。

先程切り出した地金を、L字形をした当金に被せ、その上から木槌や金槌を使って地金を叩き、立体的な形を作っていく。

地金は叩くと固くなるので、ガスバーナーで生してまた打ち続け、生しと打ち込みを繰り返しながら地金を絞り込んでいく。

ひととおり叩いては火で生し(なまし)徐々に形成していく。

写真は、木槌や金槌を使って地金を叩き、形成していったもの。
右にいけば行くほど深く絞っており、どのように一枚の銀が作品へと変化していくのかがよくわかる。
4 、市松模様打ち
形が出来上がったら、金槌打ちで模様を付けていく。
表面が光沢と荒らしの金鎚二本を用いて、一箇所40回程打ち続け、隣同士丸形が膨らみあいぶつかり合い、接点が直線となって市松紋になるという大変根気のいる作業。

こうして、何度も銀を叩き作品が完成するのだ。
とある一日の流れ

午前中
来客があれば対応し、それ以外の時間は基本的にパソコンを使った事務作業を行う。
13時〜17時
依頼されている作品を作ったり、体験教室になることがほとんどで、1人または2人程度を相手にして教えている。
通っている生徒さんは、将来、職人を目指している方や趣味でやっている方までさまざま。
県外など、遠方からわざわざ通いに来てくれている方もいらっしゃるそう。
18時半頃
作業終了。
自宅に帰り、今は老親の夕飯作りを。
Q&A

お 客さんに言われて心に残っている言葉は?
お客様からのオーダーにそのまま答えるのではなく、もう一歩その先をいくことが職人として大切なことだと思っています。
だから、ちょっとしたプラスαを加えて納品をしたときの喜びの言葉は忘れられません。
商品とはこうあるべきなんだと、実感した出来事でもありました。
や りがいを感じる瞬間は?
一つ目は、難しい注文に悩んだ末、その解決の糸口がみつかったとき。
「こうすればできる!」と、イメージが浮かんだときは、うれしいですね。
二つ目は、納品したときのお客様からの感謝の言葉。
自分の作品に喜んでくれる姿は、何にも代え難いやりがいであり、生き甲斐でもあります。

時 代の変化に合わせて工夫していることはありますか?
産業という熟語が、”うみだす”という字からできているように、やはり常に新しいものを生み出していかなくてはいけないと思っています。
しかし、流行に合わせるというのではなく、何か独自の新しい発想で作品作りをしていきたいと思っています。
このドクロのベルトは、デッサンから始めました。
かなり個性的だけど、たまたまスーッと入ってきたお客さんが「かっこいい!」って一目惚れして買って行ってくれたこともありますよ。
こういった遊び心は、これからも大事にしていきたいですね。

今 後挑戦してみたいことはありますか?
まずは現状を維持すること。
そして、今後もさまざまな出会いを通して、新しい作品を生み出していけたらなと思います。
そして、作ったものを多くの人に知ってもらうために、発信もしていかなければと思っています。
インタビューを終えて
今の時代は特にそうですが、銀器に触れる機会はめったにありません。
私も今回のインタビューまで、「銀器」と聞いてもあまりイメージが湧きませんでした。
しかし、実際に銀を熱している様子や、金槌で打ち付けている様子を見ていると、想像していたよりもはるかに銀は柔らかく、「こんなに簡単に形を変えられるのか」と驚きました。
泉さんが「銀は素直だ」とおっしゃっていたことにも頷けます。
そして、今回泉さんにインタビューさせていただいて、そんな銀という物質の魅力、泉さんのお人柄、職人としてのものづくりに対する想い、そういった様々なものが組み合わさって一つの作品になることが分かりました。
一番印象的だったのが、作っていると銀が「こうしてほしい」と語り掛けてくるとおっしゃっていたこと。
ものづくりを極めた方だからこそ、銀と会話ができるのだと思いました。
ひとり旅を通じ多くの人との出会いの中で人生の選択をし、お客様の難しい要望に応え、使う方を想って素敵な作品を生み出してきた泉さん。
その温かい気持ちがお客様に伝わり、たくさんの感動を生むのだと、お話してくださったエピソードから感じました。
銀器にはかんざしや箸、茶筒など、私たちの日常生活にも取り入れやすいアイテムがたくさんあります。
ぜひ、泉さんの工房を覗いてみてください。
きっと、気になるアイテムが見つかるはずです。

泉健一郎氏の略歴
1954 横浜出生
1976 文化学院美術科卒業
1977 一年間日本国内行脚の旅
1979 株式会社 白金 入社
1993 退社 一ヶ月間イタリア・北欧視察
独立開業
1994 伝統工芸士 文化学院<金工>非常勤講師を12年間勤務
2006 東京浅草に工房・店舗『銀泉いづみけん』設営
諸コンクール
台東区長賞 東京都知事賞 経済産業局長賞 日宝連実行委員長賞 中小企業庁長官賞
東京通商産業局長賞 山梨県知事賞 労働大臣賞 伝統工芸日本金工展 入選
ワールドゴールドカウンシル賞 伝統的工芸品産業振興協会会長賞 等
現在
伝統工芸士(国・都)
日本彫金会会員
東京金銀器工業協同組合理事