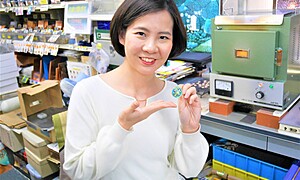大阪浪華錫器とは
大阪浪華錫器とは、大阪府大阪市周辺の地域で作られている金工品です。
錫という金属を原材料として、和・洋酒器や茶器、花器などのうつわものや、神具・仏具など、様々な製品が作られています。
昭和58年に経済産業大臣指定の伝統的工芸品に選ばれました。
大阪浪華錫器の歴史
日本に錫器が伝わったのは7世紀の初め頃(610年前後)、遣隋使の手によるものと言われています。
この頃の日本は飛鳥時代にあたり、天皇を中心とする中央集権国家が出来た時代でした。
当時、錫は金や銀に並ぶ貴重品であったため、宮中で用いられるうつわや、神社仏閣で使われる神仏具など、一部の限られた人々の間でのみ使用されていました。
奈良の正倉院には、錫の薬壺(薬を入れる壺)や、佐波理(錫と銅の合金、青銅の一種)の水瓶や皿などが、今も宝物として保存されています。
日本での錫器の生産は、日本で初めて錫鉱山が開かれた京都の丹波地方で始まりました。
1690年に出版された「人倫訓蒙図彙」(あらゆる身分・職業の簡単な解説と図解が描かれた辞典)には、江戸時代初期(1603〜1715年頃)の錫師(錫の加工を生業とする職人)の仕事場の様子が描かれています。
大阪では、江戸時代中期(1716〜1829頃)に、心斎橋や天神橋など流通が盛んな地域に産地が形成され、産業へと拡大していきました。
採掘技術が発達し、薩摩(現在の鹿児島県)などに新しい錫の鉱脈が発見されたこともあり、錫器の製造も増大していきます。
昭和初期頃(1926〜1950年頃)には最盛期を迎え、大阪全体で300人を超える職人が活躍しました。
この頃には、錫器は高級品ではあっても、一般の家庭でも広く使われるようになっていました。
その後の第2次大戦勃発時には、多くの職人が招集され材料の入手が困難になるなど、錫器の生産自体が厳しく、錫器の歴史とその技術を残す上で大きな打撃を受けることとなりました。
また、日本が高度成長期を迎えた1970年代以降、ステンレスやプラスチックの器に取って代わられ、錫器は一般家庭から姿を消してしまいました。
しかし、錫器の伝統と技術は職人たちの手によって脈々と受け継がれてきていました。
そして昭和58年(1983年)3月、その伝統性や技術などが評価され、当時の通産大臣(現在の経済産業大臣)により伝統的工芸品に指定されました。
錫の器の魅力
錫 の魅力
錆びにくく、安定した金属
錫は非常に錆びにくい金属として知られています。
全く錆びないというわけではありませんが、酸化する速度がとてもゆっくりだということです。
錆びは金属が空気中の酸素と結びつき変化することで起こりますが、錫はそれ自体が安定しているので酸素と結びつきづらいのです。
あえて錆びの発生を促すようなことをしない限り、日常生活で使う程度ではすぐ見た目に分かる変化は起きません。
よって変色が少ないので、美しい光沢を長く楽しむことができます。
しかし、使い込んでいくうちに表面の光沢が柔らかくなり、アンティークのような独特の風合いを帯びてきます。
しっとりと落ち着いた雰囲気となり、これはこれで大変味わい深いものとなります。
こちらの雰囲気を好む方もいらっしゃいますが、曇っているようで気になるという場合は、重曹をつけた布やメラミンスポンジなどでこすれば元の光沢を取り戻すことができます。
抗菌作用
昔から、「井戸の底に錫板を沈めると水がきれいに保たれる」「錫の花瓶は花が長持ちする」などと言われています。
これは錫のイオン効果によるもの。
錫イオンによって水の中の雑菌の繁殖が抑えられ、井戸の水が浄化されるため、切り花の切り口に雑菌がつかなくなるのです。
手で曲げられるほどのやわらかさ
錫の融点はおよそ230度と低く、分子構造が粗いので常温の状態でも軟らかなままです。
厚みがなければ人の手の力でぐにゃりと曲げられるほど軟らかく、「金属=硬い」という概念が覆されます。
大阪浪華錫器に使われている錫は、錫以外の金属をおよそ3%含む本錫と呼ばれる錫合金ですが、その軟らかさのため機械による加工が難しく、工程のほとんどが手作業となります。
そのため出来上がった製品の仕上がりに、それぞれ微妙な違いが生まれます。その違いが作り手の存在を感じさせ、金属でありながら人の手のぬくもりを感じることができる、温かみのある器を生み出すのです。
錫製の器はその特性ゆえに、落とすと凹んでしまうので取り扱いには注意が必要です。ただ凹んだとしても割れはしないので、内側から叩き出したり、当て金に当てて木槌で成形すれば直すことができます。
長く使用していると器によっては傷だらけになることもありますが、それもまた使用してきた人の歴史として刻まれ、侘び寂びに通じる美が感じられるものとなります。
あ らゆる飲み物を美味しくしてくれる器
抗菌作用のところでも少し触れましたが、錫にはイオン効果があり、水を浄化する作用があります。
錫の器に入れたお酒は雑味が抜け、口当たりがまろやかに。ジュースは酸味が和らぎ、美味しくなると言われています。
それに加え、錫は熱伝導率が高く、保温・保冷性に優れているので、飲み物をすばやく適温にし、その状態を長く保つことができます。
熱燗は短時間で温まるためお酒の旨みを損なわず、タンブラーに冷たいビールを注げば器も瞬時に冷え、最高の喉越しを味わうことができます。
またタンブラーの内側には手作業で細かな凹凸が施されており、きめ細かく持ちの良い泡が立つように作られています。
冷えたコップにアイスコーヒーを注げば、夏場のおもてなしにも最適です。
おわりに
金属の器というと、現代の日常生活においてはあまり馴染みがないかもしれません。
しかし錫器には先述したように様々な特徴があり、他素材の器では得られないメリットがあります。
白く上品な光沢を持つ錫器は見た目にも美しく、錫のお皿に料理を盛りつければ、普段の食卓に新鮮さが加わります。
まずは錫の器に汲んだ水で、その美味しさを体感してみてはいかがでしょうか。
大阪の地で300年以上もの歴史を紡いできた大阪浪華錫器紀。
職人の手仕事の成果を、ぜひご自分の手や目、舌で感じてみてください。

「天下の台所」として古くから商業の栄える大阪では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、20品目以上の伝統工芸品が存在します。今回は経済産業大臣によって大阪府の「伝統的工芸品」として指定されている、大阪欄間、大阪唐木指物、堺打刃物、大阪仏壇、大阪浪華錫器、大阪泉州桐簞笥、大阪金剛簾、浪華本染めをご紹介します。

大阪は、グルメ・ショッピング・お笑いがそろっている日本屈指の観光地です。この記事では、子連れで大阪を観光する方にオススメのスポット15か所をご紹介します!子供が楽しめる場所ばかりですので、楽しい思い出作りにぜひご活用ください♪

金工とは金属に細工をする工芸、あるいはその職人のことを指し、金属を加工して作られる工芸品のことを金工品と言います。
日本に金属とその加工技術がもたらされたのは、弥生時代初期、紀元前200年頃のこと。
中国大陸・朝鮮半島から伝わった金工技術によって剣や銅鐸、装身具などが作られ、材料として青銅や鉄が使われていました。

肥後象がんには、鉄の地に布目のような刻み目を入れて金属を密着させる「布目象嵌」や、象嵌する部分を地の部分より深く彫る「彫り込み象嵌」などいくつかの技法がありますが、現在作られている作品はほとんどが布目象嵌の技法によるものです。