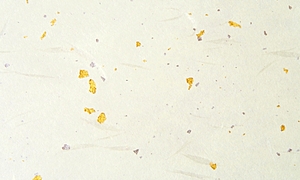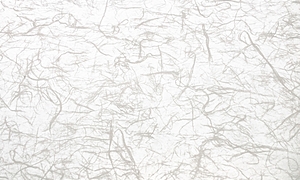日本で古くから作り続けられている和紙。
奈良県の正倉院に残されている経典や絵画に使用されている和紙は、奈良時代からその姿を保っているほど耐久性に優れ、海外からもその品質の高さを認められています。
そんな和紙の技法を用い、モダンスタイルに打ち直したアイテムはたくさんありますが、「日常的に使えるものが良い」、「カッコよくて、持ち歩いて使えるものが欲しい」、そんなものをお探しならば和紙を使った財布はいかがでしょうか?
山梨県にある和紙メーカー大直が、工業デザイナー・深澤直人氏と共同開発した「SIWA」の財布は、大直が生み出した破れない障子紙”ナオロン”を使用しており、和紙らしい本来の折れややつれの風情が見事に表現されています。
兵庫県姫路市にアトリエを構える「所作 Shosa」では、レザーと和紙を組み合わせた財布を制作しています。
兵庫県明石市の「帋屋」は、1300年の歴史を持つ杉原紙を使って、渋柿和紙の財布を作っています。
帋屋の和紙財布は、何度も柿渋を重ねることにより耐久性や防虫性が増した柿渋和紙を使用しており、柿特有の美しい飴色が特徴です。
今回は、手作りのあたたかみを伝えてくれる、和紙を使った財布7選をご紹介いたします。
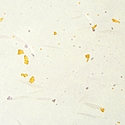
和紙は材料の選定、準備、そして工程に至るまで、一つひとつに職人の技術が込められています。
「紙和」SIWA 耐久性と撥水性に優れたわずか20gの和紙の長財布 !
最初にもご紹介した山梨県の和紙メーカー大直のSIWAが作る、ナオロンで作られたスタンダードな長財布です。
和紙独特の白い折り模様が、単色のシンプルなデザインに映えています。
わずか20gという軽さは、和紙でできているからこそ実現できるんですね。
小銭入れやカード類が入れられるポケット付きなので、この財布一つで気楽にポケットやバックサイドにしまって持ち出せます♪
カードの収納は3×2スペースでスッキリ6枚ほど入ります。
紙幣とならび、小銭収納も大口で出し入れがしやすいので、手が大きな男性でも使いやすいのが嬉しいポイント。
強度の高いこの特殊和紙は、機械ではなく職人が一点一点ミシンがけして作られています。
カラーバリエーションは全6色。
あなたのお好きなカラーをお選びください!
柿渋和紙の長財布「帋屋」のロングウォレットシリーズ♪
無骨さが大人の男らしさを醸し出す、柿渋和紙の長財布 。
帋屋の柿渋技法を駆使した和紙は、重厚でいてどこか懐かしさを感じます。
その秘密は、手に馴染むワッフルのような独特な凹凸の立体感のある和紙。
柿渋技法とは、まだ硬い青い柿を発酵させて、その煮汁とともに紙を漬け込み天日で干す作業を幾度か繰り返すことで独特の茶色に染める技法です。
天日にあてることで、趣ある柿渋茶を染め出します。
最初の数回だと淡い紅茶色なのですが、繰り返すことにより色艶とともに強度や撥水性が増していくのです。
地域の名産「杉原和紙」を加工した匠の逸品で、カラーは鉄 ・柿渋の2色を用意しています!
芦屋昭萬堂「散らし友禅の和柄財布」は千代紙の面白さ!
昔遊んだ千代紙を想うような、懐かしい江戸小紋風の柄が愛らしい友禅紙の長財布♡
内側にはお札入れの他に、もう一つポケットが付いているので、カード類も収納可能!
ちょっとした茶席での懐紙や菓子切りを忍ばせて持ち歩くのにも、ちょうど良さそうなカジュアル感です。
柄指定、色指定はおまかせということなので、何色が届くのかはお楽しみ♪
価格も群を抜いてリーズナブルな設定ですから、小さな子供たちへのちょとお洒落なお土産品にも良いかもしれません。
友禅紙の柄が美しいので、海外の方へのお土産にも良さそう!
ブランド「所作(Shosa)」の袱紗をモチーフとした和紙財布
侍を想わせる「所作」という銘の和財布は、美しい流動線を織り込んだ和紙と黒牛革の合わせ素材で縫製されたロングウォレットです。
小銭ポケット部分にもチャックやボタンは使用せず、日本独自の文化でもある「折形」の様式を模して作られています。
折形とは武家が用いる礼法の一つで、和紙を使って物を包む技法のことです。
そして、財布のデザインのコンセプトになったのは「袱紗」。
慶弔のお包みを手本に制作されたのは、このような時の所作振る舞いのさりげない美しさを写したかったから。
職人の気概が伺えますね。
外側の軽やかな和紙の手触りとしっとり落ち着いた牛革、そのどちらも過剰な素材加工は行わず小さな孔や傷は風合いとしてあえて残した仕上がりとなっています!
「紙和」SIWAの新素材であるナオロン和紙を用いた二つ折り財布!
山梨県の和紙メーカー「大直」が開発製作している破れない新素材ナオロンを使った、SIWAの逸品です。
こちらの財布はコンパクトな二つ折りの財布になっていますが、機能性は充分に備わっています。
カードスリットが6つも入っているので、カード派の方や海外へ行く方に便利そう。
Suicaや電子マネーの決済も、財布をかざすだけでOKなのも嬉しいですね!
サイズは約10cm四方、カラーは8色がラインナップされていますので気軽なポケット財布に手にしてみるのもオススメです♪
ナオロン和紙の小銭入はなんとたったの8g!「紙和」SIWAのコインケース
この小銭入のサイズは 11.0×8.3cm で、たったの8g!
手のひらサイズの機能性に富んだ小銭入れです♪
上で紹介した同シリーズの長財布には小銭入れが付いていないので、合わせて使うといいかも!
カードポケットと小銭ポケットが分かれており、こちら一つでも活躍しそうな仕様です。
こちらの小銭入れも財布をかざすだけでICチップは読み取れますので、クレジットカードやデビットカード、電子マネーなど一枚いれておけば便利に使えそう。
洋服のポケットにしまえるサイズなので近所の散歩のお供にも♪
もちろん撥水性もある新素材和紙なので濡れても平気です!
SAMIRO YUNOKI ×「紙和」SIWAの蓋のない軽快なデザイン長財布!
染色家・柚木沙弥郎氏がデザインした柄を、破れない和紙ナオロンに印刷した長財布♪
黒の大筆を無造作に走らせた豪快なデザインは、どこか北欧を思わせるおしゃれさ。
なんと、この長財布には蓋がついていないんです。
無駄が一切省かれたデザインの長財布なので、小さなバッグでの移動や、トートバッグの内収納に差して使うシーンで活躍しそう。
ちょっと人とは違う財布をお好みの方にオススメしたい逸品です♪
柄は5パターンから選ぶことができますので、あなたのファッションに合う一つを探してみてください。
おわりに
年々携わる職人が減りつつある手漉き和紙。
そんな中で、個性的な商品が新たな市場を得るかもしれません。
昔ながらの手仕事によりできあがった商品は、機械で大量生産されている商品に比べて、今後どんどん貴重になっていきます。
海外でも認められている伝統工芸品である和紙。
モダンなデザインや形に姿に変えて、これからも私たちの生活の中で進化を続けていくでしょう。
ぜひ、新しい形に進化した和紙の財布を毎日の暮らしに取り入れてみてください♪

和紙は古来から日本で作られてきました。和紙の作成技術の起源には諸説ありますが、有力な説は、日本書紀に書かれている西暦610年に朝鮮から仏教の僧によってもたらされたというものです。当時は聖徳太子が活躍していた時代でした。

ワゴコロ編集部による、日本橋の和紙専門店「小津和紙」さんでの“手漉き和紙体験”レポートです。

福井県越前地方の岡太川流域で1500年程前から作られている、越前和紙。「紙の王様」と呼ばれる越前和紙は、美しい生成り色で表面は滑らか、丈夫さと美しさを併せ持つ極上の和紙です。日本伝統の文化が息づくこの越前和紙について、今回は詳しく見ていきたいと思います。

日本の伝統などと言うと古いイメージがあるかもしれませんが、職人の確かな技術に基づいて作られた近年の和紙の照明器具は、オシャレで可愛いものから、モダンでハイセンスなものまで魅力的なデザインが多くなっています。
今回はそんな和紙照明の中から、実用的で部屋にいるのが楽しくなるような美しい和紙の照明器具10選をご紹介します。

長い繊維が絡み合うことで強い耐久性を持ち、そして、柔らかく趣のある風合いが魅力の和紙。
この記事では、比較的お手頃で部屋に飾りやすいサイズ感のオススメの和紙人形をピックアップしてみました。
また、オススメの和紙人形と合わせて、有名な作家さんや魅力についてもご紹介していきたいと思います♪

岐阜県美濃市で、1300年以上前から伝統の技法で漉かれ続けてきた美濃和紙。厳選した素材で手漉きされる「本美濃紙」の技術は、ユネスコ無形文化遺産に登録され、国宝級の古文書や絵画の修復にも使用されるほどです。この記事では、美濃和紙とはなにか、その歴史や魅力についてご紹介します。

日本三大和紙の一つに数えられる、高知県の「土佐和紙」。 古くから土佐では、薄く丈夫で多彩な紙が作られ、幅広い用途で使われてきました。 この記事では、土佐和紙の特徴と魅力をはじめとして歴史や種類、作り方、土佐和紙の紙漉き体験ができる施設などをご紹介します。

父の日は、いつも頑張ってくれているお父さんに感謝の気持ちを伝える大切な日です。しかし毎年日付が変わるため「今年の父の日はいつだっけ?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか?この記事では、父の日の歴史やシンボルとなる花の由来、オススメのプレゼントをご紹介します♪