長い繊維が絡み合うことで強い耐久性を持ち、そして、柔らかく趣のある風合いが魅力の和紙。
日本古来の伝統的な和紙は、樹木の皮である楮、三椏、雁皮などを原料とし、横と縦の交互に繊維を流して漉いていく「流し漉き技法」で作られています。
ユネスコ無形文化遺産に登録されている和紙や、国の伝統的工芸品に指定されている和紙も多く、それ以外にも昔ながらの流し漉き技法を受け継ぎ、丁寧な和紙作りを行う工房が全国各地に存在しています。
この記事では、比較的お手頃で部屋に飾りやすいサイズ感のオススメの和紙人形をピックアップしてみました。
また、オススメの和紙人形と合わせて、有名な作家さんや魅力についてもご紹介していきたいと思います♪
ぜひ、和紙人形が織りなす情緒豊かな世界に触れてみてください!
越前和紙のころんとかわいいうさぎのおひなさまのお人形♪
優しい笑顔がキュートなうさぎのおひなさま♡
たまご型の体はだるまのように、起き上がりこぼしになっています。
輪郭はどの角度から見ても滑らかで美しく、和紙の柔らかな風合いが最大限に活かされた人形ですね。
おひなさまが着ている色鮮やかな可愛らしい着物は、空間を華やかな雰囲気に演出します♪
使われている和紙は、約1500年の歴史をもつといわれている「越前和紙」。
福井県越前地方で作られている、優雅で美しい色合いと高い品質が特徴の和紙です。
本アイテムは、福井県大野市のふるさと納税返礼品。
10,000円の寄附に対して、おひなさま一式と、越前焼で作られたオリジナル湯のみがセットで受け取れます。
この機会に、ぜひかわいらしい和紙のお雛様をお迎えしてみては?
赤いほっぺに癒される、ペアで飾る和紙人形♡
和紙特有の優しい風合いと、丸いフォルムが調和したかわいらしい起き上がりこぼし人形です。
良質な国産の和紙を使い、細部まで丁寧に仕上げられているのが魅力的♪
使用されている和紙には、薄さと柔らかさ、繊細で美しい色合いが特徴の美濃和紙が使われています。
ペアになった人形は、「祖父母」「和装新婚」「わらべ」の3種類。
体や顔の作りはどれも共通していますが、着物や小物、髪型、肌の色など、それぞれの個性を柔らかな和紙で見事に表現しています。
小さな人形の背の高さは約5cm。
どこにでも飾りやすいので、結婚祝いや外国の方へのプレゼントにもオススメです!
お値段もお手頃なので、思わず揃えたくなってしまうのでは?♡
和紙の雛人形♪金色の屏風付きで和紙でありながら華やか!
和紙人形の座り雛人形です♪
雛人形としては非常にコンパクトなサイズに収まっているところもかわいいですよね!
細部までこだわって作られており、金色の屏風や、お雛様とお殿様が着ている着物も華やかで美しいです♡
簡単にしまうこともできるので、毎年の雛祭りに重宝しそうです!
素朴なものから豪華な物まで!和紙人形の魅力♡
一度知るとどっぷりとハマってしまうという和紙人形。
今回ご紹介している和紙人形は、簡略化されたデザインのものが多いですが、人型の和紙人形は、繊細でありながらダイナミックな動きを感じることができ、和紙でしか表現することができない素材の質感もそのまま現れています。
また、和紙は弱そうなイメージがあるかもしれませんが、1000年も持つといわれているように、加工しやすく強靭であることから、人形にするのには適した素材であるといえるかもしれませんね。
作り手によって衣装の色使いも全く異なる点も魅力の一つです!
そんな魅力あふれる和紙人形を制作している有名な作家さんもご紹介します。
和 紙人形作家 山中セツ子氏~大阪府泉佐野市の人間市宝!~
世界でも活躍している和紙人形作家、大阪府泉佐野市の人間市宝に選ばれた山中セツ子氏。
海外で開かれる世界的な人形のコンクール「世界人形会議」で、2度の金賞を受賞されている実力者です♪
自宅にはご自身で制作した和紙人形の美術館を開設しており、作品を近くで見ることができます♡
和紙人形を作る際は、丸みを出したり厚みを出す作業がとても大変なのだそう。
和紙人形に着物を着せる場合には、着物がどういう作りになっているのかなど、着物の構造の知識も必要となります。
和紙には独特のシワがありますが、このシワをどういう風に活かすのかも重要になってきます。
作りながら合わせていくのではなく、建築のように人形にしていく前にきちんとした設計図が必要な点も和紙人形を作るのが難しい点の一つです。
そんな和紙人形を作り続けているだけで、山中セツ子氏の凄さを感じますよね♪
かわいいダルマで祝う端午の節句♪ちぎり和紙でできたぽっちゃりダルマ武者人形
キリリとした眉とつぶらな瞳、にっこりとほほ笑む口元がなんともかわいらしいダルマの武者人形♪
大きさは横幅約14cm、高さ約13cmと、小さなお子さんが持つにはちょうどいいサイズ感!
限られたスペースにも飾りやすく、マンションサイズの五月人形としてオススメです。
化粧箱入りで台座もセットになっており、端午の節句の贈り物にも最適。
ちぎり和紙で丁寧に作られただるまは、和紙の柔らかさが強調された優しい風合いです。
また、全体的に落ち着いた色合いですが、兜とダルマの体にあしらわれたゴールドがアクセントとなり、華やかな雰囲気も感じられますね。
お子さんの名入れ立て札も作ってくれますので、プレゼントであげたら喜んでもらえそう!
大きなリボンがポイント!ノスタルジックな壁飾りの和紙人形 赤袴
袴姿でにっこりとほほ笑むかわいらしい女の子の和紙人形。
豊かな黒髪に大きなリボン、色鮮やかな袴が、ノスタルジックな雰囲気を引き立てています♡
横幅約14cm、高さ約26.5cmですので、壁に飾りやすい適度なサイズ感が嬉しいですね♪
一つひとつ手作りで丁寧に仕上げられており、空間を華やかに演出してくれます。
また、平面的な壁掛け人形ですが、和紙の質感と細かな作りで、奥行きが感じられるのも魅力です。
赤袴タイプのほか、青袴もラインナップされており、セットで揃えるのもオススメ!
和風の魅力が凝縮された一品です。
傘を持った小さくてかわいい和紙人形!着物の柄も綺麗♡
和柄の着物を纏った、小さくてかわいい和紙人形です♪
背の高さは13㎝と小ぶりの和紙人形ですが、インテリアとしてさりげなく置いておくだけでインパクトがあります!
もちろん一つひとつ手づくりで作られているので、手作りならではの温かみや素朴さも感じることができる商品です!
日本好きな外国の方へプレゼントしても喜んでもらえるのではないでしょうか?♡
千客万来!なが~い手で幸せを招く♡ちぎり和紙の招き猫人形
愛嬌のある表情と、長く高く伸びた大きな左手が目を引く招き猫。
右手を挙げている招き猫はお金や金運を招くとされているのに対し、左手を挙げている招き猫は人を招き寄せるといわれています♪
さらに、長い手の猫は「手長招き猫」と呼ばれ、手の高さが高いほど遠くの人や金運などを招いてくれるとされているんですよ!
長い左手を挙げたこちらの招き猫は、商売繁盛を願うのにぴったりですね♡
ちぎり和紙ならではのふっくらとした風合いで、穏やかで優しい雰囲気も魅力。
高さ約29cmで、お店はもちろん自宅の玄関やリビングなどのスペースにも飾るのもオススメです。
おわりに
紙には洋紙と和紙がありますが、日常生活で使われるほとんどの紙が洋紙です。
洋紙は、一般的なノートやコピー用紙など、表面が滑らかでインクが乗りやすい印刷に最適な紙。
一方、和紙は長い繊維を絡めて作られた紙で、通気性のよさが特徴です。
また、墨で文字を書いたときの吸い付きのよさと美しい滲みは、微細な穴がある和紙ならではです。
繊維がよく絡み、薄くて強度の高い和紙は、古くは「流し漉き」という伝統的な技法で作られていました。
しかし、現在流通している和紙の多くは、量産が可能な「機械抄き」です。
製法は多様化しましたが、味わい深い和紙の風合いは、障子や半紙、扇子やインテリアなどに活かされています。
和紙人形は、気軽に飾れるリーズナブルな人形から芸術的な作品までさまざまなタイプがあり、豊富な選択肢が魅力です。
ぜひ、1000年以上の歴史をもつ和紙の魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。

和紙は古来から日本で作られてきました。和紙の作成技術の起源には諸説ありますが、有力な説は、日本書紀に書かれている西暦610年に朝鮮から仏教の僧によってもたらされたというものです。当時は聖徳太子が活躍していた時代でした。
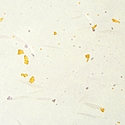
和紙は材料の選定、準備、そして工程に至るまで、一つひとつに職人の技術が込められています。

ワゴコロ編集部による、日本橋の和紙専門店「小津和紙」さんでの“手漉き和紙体験”レポートです。

福井県越前地方の岡太川流域で1500年程前から作られている、越前和紙。「紙の王様」と呼ばれる越前和紙は、美しい生成り色で表面は滑らか、丈夫さと美しさを併せ持つ極上の和紙です。日本伝統の文化が息づくこの越前和紙について、今回は詳しく見ていきたいと思います。

日本の伝統などと言うと古いイメージがあるかもしれませんが、職人の確かな技術に基づいて作られた近年の和紙の照明器具は、オシャレで可愛いものから、モダンでハイセンスなものまで魅力的なデザインが多くなっています。
今回はそんな和紙照明の中から、実用的で部屋にいるのが楽しくなるような美しい和紙の照明器具10選をご紹介します。

日本で古くから作り続けられている和紙。
奈良県の正倉院に残されている経典や絵画に使用されている和紙は、奈良時代からその姿を保っているほど耐久性に優れ、海外からもその品質の高さを認められています。

岐阜県美濃市で、1300年以上前から伝統の技法で漉かれ続けてきた美濃和紙。厳選した素材で手漉きされる「本美濃紙」の技術は、ユネスコ無形文化遺産に登録され、国宝級の古文書や絵画の修復にも使用されるほどです。この記事では、美濃和紙とはなにか、その歴史や魅力についてご紹介します。

日本三大和紙の一つに数えられる、高知県の「土佐和紙」。 古くから土佐では、薄く丈夫で多彩な紙が作られ、幅広い用途で使われてきました。 この記事では、土佐和紙の特徴と魅力をはじめとして歴史や種類、作り方、土佐和紙の紙漉き体験ができる施設などをご紹介します。
















































