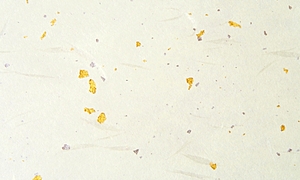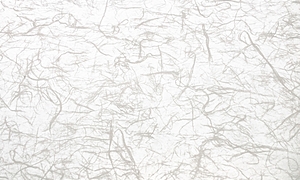日本三大和紙の一つに数えられる、高知県の「土佐和紙」。
古くから土佐では、薄く丈夫で多彩な紙が作られ、幅広い用途で使われてきました。
この記事では、土佐和紙の特徴と魅力をはじめとして歴史や種類、作り方、土佐和紙の紙漉き体験ができる施設などをご紹介します。
土佐和紙とは

土佐和紙とは、高知県の中でも特に土佐市や、いの町周辺で作られている和紙のことを指します。
その歴史は長く、千年ほど前からこの地で漉かれてきたといわれています。
土佐和紙の種類は約300種類あるといわれており、中でも「土佐典具帖紙」と呼ばれる手漉き和紙は、非常に薄い手漉き和紙として“カゲロウの羽”とも呼ばれています。
そんな土佐和紙は、昭和51年(1976年)に経済産業大臣により、国の伝統的工芸品として認定されました。
また、中でも土佐典具帖紙と土佐清張紙は、国が指定する重要無形文化財にも認定されています。
和 紙生産に適した産地「土佐」
土佐和紙の「土佐」とは、高知県の旧国名のこと。
この地域は“仁淀ブルー”と呼ばれる透明度の高い独特の青色をした清流の仁淀川が流れ、原料となる良質な楮が生産されており、和紙作りに必要な水と原料に恵まれた場所でした。
特に温暖で降水量の多い土佐で育った楮は、他の地域の楮と比べて繊維が太く長いため、繊維同士がしっかりと絡みあい、薄くても丈夫な紙を作りやすいのです。
さらに土佐和紙は土佐藩に保護され、代々、紙漉きの伝統が継承されるとともに、製紙用具専門の職人が生まれ、製紙用具作りも発展しました。
中でも、竹ひごや編糸などの製紙道具の基本素材は、高知から全国へ送られてきた歴史があります。
このように、土佐和紙は豊かな清流・仁淀川のもと、この地域ならではの原料、用具、技術があり生み出されてきた、優れた伝統的工芸品なのです。
土 佐和紙の魅力
上述した「土佐典具帖紙」は手漉き和紙の中でも薄く、その厚さはなんと0.03mm!
通常のコピー用紙の厚さが0.08mm程度であることを考えれば、土佐典具帖紙がいかに薄いかがわかります。
また、土佐和紙は現在、手工芸用紙、書道用紙、美術修復用紙など幅広い用途の紙が作られています。
最盛期には300種類もの土佐和紙が作られており、土佐典具帖紙をはじめ、図引き紙、インク止紙など新たな紙も歴史の中で次々と発明されてきたのです。
薄くて丈夫な土佐和紙は、古くから財布や灯篭、ふすまなど幅広く使われてきました。
今でも壁紙やインテリア、文具、ちぎり絵、マスク、さらには国内外の美術工芸品の修復など、いたるところで使われています。
土佐和紙の歴史
土佐和紙が誕生した正確な時期は不明ですが、平安時代中期に出された法令集である『延喜式』の中には、すでに「土佐和紙」の名前が献上品として登場しており、少なくとも千年以上前から製造されていたことがわかっています。
しかも、このときには4人の技術者で年間2万枚の紙を作っていた、という記録が残されているんだとか!
また、平安時代の『土佐日記』の作者・紀貫之が土佐国司として赴任した際、土佐和紙の生産を奨励したという伝説も。
七 色紙で有名に
そんな歴史ある土佐和紙ですが、その名が全国に広がったのは江戸時代。
きっかけは、安土桃山時代の1590年以降に開発された「土佐七色紙」という色紙でした。
土佐七色紙とは、いの町の草木染の技術を生かして作られた7色の美しい色紙のことで、土佐の特産品として江戸時代に徳川幕府への献上品となりました。
土佐藩は土佐和紙を作成する技術を保護するとともに、紙の原料である楮の生産を奨励し、それ以降、土佐ではさらに和紙作りが発展していきました。
明 治時代、吉井源太が製紙王国へ
江戸末期から明治期にかけて、土佐和紙はいの町出身の吉井源太により、さらなる飛躍を遂げます。
吉井源太は大型の簀桁※を開発し、土佐和紙の量産化を図りました。
さらに、土佐典具帖紙をはじめとする新製品を30種類近くも発明し、土佐和紙を発展させたのです。
こうして、明治時代半ば、土佐は全国一の和紙生産量を誇る製紙王国になりました。
土佐和紙の品質と技術は高く評価され、昭和51年(1976年)には土佐和紙が国の伝統的工芸品の指定を受けます。
さらに、土佐和紙の中でも代表的な土佐典具帖紙と土佐清張紙は、国の無形文化財ともなりました。
和紙を作る職人も、選定保存技術に指定され保護されています。
また、透かし紋様入りの土佐典具帖紙などを発明した紙漉き職人の浜田幸雄は、人間国宝に認定されました。
※簀桁:紙を漉く道具
土佐和紙の種類
土 佐典具帖紙
土佐典具帖紙(超々極薄!)
— 山本 志帆 (@Shiho__YAMAMOTO) October 19, 2018
重ねると綿菓子みたい
美しい紙#和紙 pic.twitter.com/K2oTSFlPd8
土佐典具帖紙は、0.03mmという薄さを誇る和紙。
その薄さは「カゲロウの羽」とも形容され、透けるような薄さでありながら、しなやかさと丈夫さも兼ね備えているところが魅力の土佐和紙です。
元は美濃で漉かれていた和紙を明治時代に吉井源太が改良し、0.03mmの薄さの紙を作り出しました。
土佐典具帖紙はインクのりがよく、叩いても破れない丈夫さから、開発された当時はタイプライター用紙として欧米に輸出され人気を博しました。
土佐典具帖紙の制作の際には、塵一つ入らないよう入念な下準備が行われ、紙漉きは簀桁を力強く大きく揺り動かして液を激しく回転させます。
この方法によって繊維を薄く均一に絡み合わせることができ、薄い土佐典具帖紙を作り上げることができるのです。
さらに、その技術を受け継ぎ人間国宝に認定された浜田幸雄(1931年~2016年)が、土佐典具帖紙の透かし文様入りや染紙を発明しました。
このように進化を続けてきた土佐典具帖紙は、今では海外も含めた文化財修復に使われるほか、ちぎり絵、貼り絵用などにも使われています。
この技術は、浜田幸雄亡き後も、孫の浜田洋直・治によって受け継がれています。
土 佐清張紙
かつて、清張紙は高級な帳簿や事務用紙として使われてきました。
とくに土佐清張紙は「千年長持ちする紙」と言われるほど、丈夫で耐久性に優れた和紙です。
白くふっくらとした上品な紙質であり、墨付きも良いため、今では高級な書道用紙として人気を博しています。
現在は尾崎製紙所が地元・土佐で採れる楮を使い、天日干しや石灰煮熟方法などの伝統的な技法を守りながら土佐清張紙を作っています。
土 佐美術工芸紙
土佐美術工芸紙とは、染色や装飾で加工した土佐和紙のことです。
その用途は幅広く、美術工芸や表具などさまざま。
土佐には土佐七色紙の伝統があり、そこから青色の青土佐や、薬を入れる袋として使われた薬袋紙などが生まれました。
さらに、土佐の薬袋紙は薬を入れる用途だけではなく、江戸時代には大名屋敷の襖としても使われていたといわれています。
土佐和紙の作り方
和紙のおもな材料は楮、雁皮、三椏などの樹皮です。
土佐和紙の作り方は、それら植物の皮を石灰などで煮出して繊維を取り出し、水洗い、さらに日干しまたはさらし液で漂白するところから始まります。
その後、漂白した原料から残っている塵や埃をとる「ちり取り」を手作業で行なった後、原料をほぐれやすくするため木の棒で叩きます。
この叩く作業は、手で行うこともありますが、現在は機械で行われることが多いそうです。
叩いたことにより繊維がほぐれたら、その原料を「こぶり籠」へ入れてよくかき混ぜ、繊維を分散させます。
土佐和紙では、このこぶりの工程が紙質を大きく左右するため、ここは特に重要な作業です。
そして、こぶりが終わったらようやく漉きの工程に入ります。
漉き舟に原料とトロロアオイの根から取り出した粘りのある液を加え簀桁を使って紙を漉いていきます。
紙の漉き方には「溜め漉き」と「流し漉き」の2つがあります。
溜め漉きは厚い紙用の漉き方で、一度だけ紙料をすくいあげて漉き、一方の流し漉きは薄い紙用の漉き方で数回紙料をすくいあげて簀桁を前後に揺らして和紙を漉いていきます。
漉いた後は、できあがった和紙を脱水、乾燥して完成です。
ちなみに、手漉き和紙の重要な道具の一つである簀桁は、小さい竹ひごや、かやを何本も編んだ「簀」を桁にのせて使う道具です。
簀桁を作るのも簡単ではありません。
簀は、竹ひごを均一にしなければなりませんし、桁は軽くて丈夫で、簀との間に隙間がないように作る必要があり、緻密な作業と高度な技術が必要です。
土佐和紙の紙すき体験ができる主な工房
土佐和紙の産地である高知県には、紙すき体験ができる工房がいくつかあります。
今回は、いの町にある紙すき体験のできる2つの工房を紹介します。
い の町紙の博物館
「いの町紙の博物館」では色紙やハガキを作る紙すき体験ができます。
通常は「溜め漉き」の体験ですが、月に1回「流し漉き」体験もできます。
さらに、いの町紙の博物館では和紙の歴史や道具、土佐和紙ができるまでの工程や紙を使った製品などが展示されており、和紙についてさまざまな知識を学ぶことができます。
また、各種紙製品も売られており、お土産にもオススメです!
住所:〒781-2103
高知県吾川郡いの町幸町110-1
アクセス:土讃線伊野駅下車、徒歩約10分
土 佐和紙工芸村「くらうど」
いの町の道の駅「土佐和紙工芸村くらうど」では、土佐和紙の手すき体験ができます。
紙を漉いて押し花などを施したオリジナルハガキや色紙は40~60分で完成です。
さらにこの道の駅は土佐和紙の体験ができるだけでなく、宿泊施設や温泉、レストランなども併設しており、カヌー体験もできます。
住所:〒781-2136
高知県吾川郡いの町鹿敷1226
アクセス:JR伊野駅より高知県交通バスで15分、岩村下車すぐ
おわりに
今回は土佐和紙の魅力や特徴、歴史、作り方などをご紹介しました。
千年以上も伝統を受け継ぎながらも革新を続けてきた土佐和紙は、今ではイタリアのバチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂の美術修復用や、腕時計の文字盤に使わるなど意外なところでも活躍しています。
和紙には独特の優しさと風合いがあります。
興味のある方は、道の駅の土佐和紙工芸村「くらうど」や、いの町紙の博物館に足を運んで土佐和紙の魅力に触れてみてください。

和紙は古来から日本で作られてきました。和紙の作成技術の起源には諸説ありますが、有力な説は、日本書紀に書かれている西暦610年に朝鮮から仏教の僧によってもたらされたというものです。当時は聖徳太子が活躍していた時代でした。

岐阜県美濃市で、1300年以上前から伝統の技法で漉かれ続けてきた美濃和紙。厳選した素材で手漉きされる「本美濃紙」の技術は、ユネスコ無形文化遺産に登録され、国宝級の古文書や絵画の修復にも使用されるほどです。この記事では、美濃和紙とはなにか、その歴史や魅力についてご紹介します。

福井県越前地方の岡太川流域で1500年程前から作られている、越前和紙。「紙の王様」と呼ばれる越前和紙は、美しい生成り色で表面は滑らか、丈夫さと美しさを併せ持つ極上の和紙です。日本伝統の文化が息づくこの越前和紙について、今回は詳しく見ていきたいと思います。
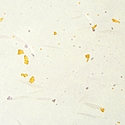
和紙は材料の選定、準備、そして工程に至るまで、一つひとつに職人の技術が込められています。

日本の伝統などと言うと古いイメージがあるかもしれませんが、職人の確かな技術に基づいて作られた近年の和紙の照明器具は、オシャレで可愛いものから、モダンでハイセンスなものまで魅力的なデザインが多くなっています。
今回はそんな和紙照明の中から、実用的で部屋にいるのが楽しくなるような美しい和紙の照明器具10選をご紹介します。

長い繊維が絡み合うことで強い耐久性を持ち、そして、柔らかく趣のある風合いが魅力の和紙。
この記事では、比較的お手頃で部屋に飾りやすいサイズ感のオススメの和紙人形をピックアップしてみました。
また、オススメの和紙人形と合わせて、有名な作家さんや魅力についてもご紹介していきたいと思います♪

四国の南部、太平洋側に位置し、豊かな森林と四万十川の美しい清流に恵まれ、自然の雄大さを間近に味わえる景勝地が多く存在する高知県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、10品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている2品目をご紹介します。

日本各地には、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いて作られる工芸品や美術品がたくさん存在します。日本に数多くある伝統的工芸品のうち、ここでは四国地方に伝わる9品目をご紹介します。