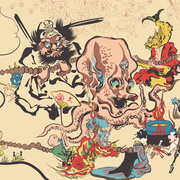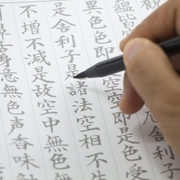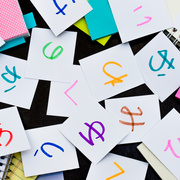盆栽を始めようと思った時に、まず気になるのが管理方法。
何をすればいいのかネットで調べてみると、水やり、肥料、剪定、針金掛け…など、少し専門的な用語がずらり。
こんなこと、自分にできるのかな?
と不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。
大丈夫、あきらめないで!
ここでは、最初に知っておくとより盆栽を楽しむことができる、盆栽の基本の管理方法について分かりやすくご紹介します。
心から盆栽を楽しむ!
自 分の価値観で楽しむ
盆栽は鉢の中に自分の好きなように樹や草花を植え、大自然の光景を創ることができます。
そのため、盆栽の楽しみ方に理屈は不要。自分の価値観で楽しめばよいのです。
盆栽を楽しむために、まずは1本の樹を盆栽鉢に植えることから始めてみましょう。
庭先で見つけた小さなもみじの木や旅先の盆栽市で見つけた苗木など、とにかく春夏秋冬を通して自分で見つけた1本の樹木を植えて、ゆっくりあせらず一年間育てることから始めてみましょう。
「盆栽も園芸も初めて!」という方は、最初はお手頃価格の盆栽や、身近にある草物を使った草物盆栽の「寄せ植え」から始めるのがオススメです。
盆 栽を楽しむためのポイント

盆栽を楽しむためには、盆栽の「見所」を知っておくことが大切です。
盆栽の見所とは、盆栽の土の上に出ている「根張り」から上に向かって「樹の立ち上がり」、一番下の枝から「一の枝」、「二の枝」、「三の枝」、そして一番上の枝棚全体を「樹冠」と呼び、樹の先端部分で幹の頂点が樹芯です。
盆栽の水やり(灌水)
水 やり(灌水)のポイント
水やり(灌水)は、樹種、樹の大きさ、鉢の大きさ(大小・浅い・深い)、用土の乾燥具合、置き場所の状況、季節、天候などによって日々、調整しながら行います。
モミジなどの雑木類盆栽は、夏の時期に水分が不足すると、葉焼け※ 1の原因になりますので、特に注意してください。
※1夏の暑い時期に強い日光を浴びすぎて水分が不足し、葉が枯れてしまうこと
水 やりのコツ

水は鉢中の用土の中に蓄えられた分量しかないので、完全に水切れしてしまうと枯れ始めてしまいます。
なので、日頃から鉢土の表面の乾き具合を良く観察し、土面が乾ききる前に鉢の底から水が流れ出るまでしっかりと与えてください。
水やりの目安は1日1回、夏は朝夕2回位、冬は2~3日に1回位です。
冬は寒さでかけた水が凍りやすいので、水やりは午前中にしましょう。
広葉樹の盆栽は葉から水が蒸発するので、夏場は葉水※2を与えると効果的です。
雨の日は、雨が降っても土面だけしか濡れない場合があるので、土の状態に注意して水やりをしてください。
※2霧吹きスプレーなどを使い、葉に直接水を吹きかけること
盆栽の置き場所

盆栽の育て方の中で、水やり(灌水)と同じくらい大事なのが「置き場所」です。
盆栽に適した置き場所は、陽当たりや風通しが良く、夜露が当たる場所です。
置き場所を移動する際、盆栽鉢を地面に直接置いたり、室内に長期間置くことは避けましょう。
酷暑時期は西日を避け、厳冬時期は盆栽が凍らない場所に盆栽鉢を移動してください。
盆栽の病虫害対策(予防)
盆栽の病虫害対策は、早期発見と予防が大切です。
盆栽が害虫被害を受けやすい時期は、春先から夏にかけてです。
病害は高温で長雨が続いている時期に発生しやすいです。
盆栽の病虫害対策には薬品を使用しますが、必ず説明書をよく読み、希釈率を守ってください。
使用する際は、殺虫剤と雑菌剤の用途の違いを理解しておきましょう。
また、殺虫剤と雑菌剤を合わせて使用する場合、薬品同士の相性もに気を付けることがポイント です。
盆栽の肥料(施肥)
肥 料の与え方
盆栽は庭木とは異なり盆栽鉢の中で小さく育てるので、肥料の量や成分には注意が必要です。
また、肥料は少量を数回に分けて与えることが基本です。
盆栽の肥料には置き肥と液肥があり、春と秋に与えます。
春は4月から6月、秋は彼岸頃に肥料を与えます。
施 肥を避ける時期
植えかけをする際、従来伸びていた根を短く切ったり、枝を詰めたりしているので、樹に負担がかかっています。
なので、植えかえをしてから2~3週間位は施肥(肥料を与えること)を避けてください。
植えかえをしてから2~3週間位すると根が伸び出し、切り詰めた枝などの樹の負担も軽減されてくるので、それから肥料を与えてください。
また、樹勢が弱っている時は根の活力も弱っているので施肥はしないでください。
梅雨時期などの長雨が続いた後の数日間も避けましょう。
盆栽の剪定・整姿
剪 定と整姿
盆栽は樹形を作ったり、整えたりするために「剪定」と「整姿」の作業を行います。
「剪定」は、樹の枝を切り詰めたりして、陽当たりや風通しを良くすることです。
一方、「整姿」は、樹形を整えることです。
整姿をしないでいると樹形が整っていた盆栽でも樹形が崩れてしまいます。
盆栽の剪定や整姿は庭木と同じように枝葉を切り詰める作業を行いますが、これらの2つの作業は樹を“創る”ことなので、初心者の方は失敗を恐れず気楽な気持ちで剪定や整姿を始めてみましょう。
剪 定の仕方

剪定の仕方は、樹形全体を見ながら
・樹の正面
・樹高
・枝順
・枝の間隔
・枝の方向
・枝の長さと太さ
を考慮しながら行います。
剪定作業をしながら多すぎる枝を整理したり徒長枝 ※3や不必要な枝、混みあっている枝など取り除いたりして、枝の分かれ目をはっきりさせます。
また、葉の日当たりや風通しがよくなるように剪定していきます。
盆栽の剪定は一度で終わりではなく、樹の生長※4に合わせて年に数回剪定をしながら理想の樹姿に仕立てます。
※3徒長枝は、強くて勢いよく伸びたままの枝です。この徒長枝を放置しておくと樹の養分がこの枝に行ってしまうので、他の枝の生長が遅くれてしまいます。そのため、剪定の際に根元から切り詰めます。
※4植物が伸び育つこと
整 姿の仕方
整姿の仕方は、樹形が完成した時の樹高や幹の太さなどの樹形全体を考えながら、幹と枝、枝と枝、枝と葉などのバランスを整えるようにして、樹形全体を整えます。
整姿の作業は、樹姿を良くするだけでなく剪定と同じように枝や葉に日当り、風通しが良くなるように行います。
整姿の作業には、樹形を整えるだけでなく、芽摘み、針金かけ、葉刈りなど、いろいろな作業が含まれています。
盆栽の針金かけ
針金かけは、角度や方向が悪い幹や枝に針金をかけて、理想の樹形に整える整姿法の一つです。
針 金のかけ方
最初に樹の正面を決めてから針金の太さを決め、太い針金から細い針金の順に針金をかけていきます。
針金の巻き方は、右に枝や幹を曲げる時は右巻き、左に曲げる時は左巻きにします
針金をはずす時期は、かけてから約1年後です。
外し方は、かけた時の逆の順に行うので頭部の樹芯から外し始め、細い枝から太い枝の順に外していきます。
針金かけの技術を短期間で習得することは不可能なので、適切な時期に少しずつ経験を積んでいくことが技術習得の近道です。
針 金かけの注意点
針金かけで最も注意すべき点は、樹を傷めないことです。
針金かけは樹に負担がかかるので、衰弱している樹は避けましょう。
また、針金をかけた盆栽は樹が疲れているので、一週間位葉水を与えて風が当たらないところで管理をします。
針金かけを行う時期は樹の負担が比較的少ない春と秋ですが松柏類などは、樹液の流動が少ない秋の彼岸頃から翌春の彼岸頃までに行います。
盆栽を始めたばかりの方は、最初から樹形を大きく変えようとせず、小さな枝の向きや角度を少し変えながら樹形を整えましょう。
盆栽の植かえ

植 かえの目的
植えかえの目的は、古い土を新しい土にかえて水はけを良くし、枝や根を切って樹の新陳代謝を良くすることです。
そのため、樹種や大きさによって植えかえを行う間隔は異なりますが、落葉樹類は1~3年、松柏類は3~5年位の間隔で行います。
植 えかえの注意点
植えかえは、根を乾燥させないように、直射日光や風が当たらない場所で作業を行います。
植かえをする盆栽は、事前に水切りをしてから行います。
土や根が湿っていると根が傷みやすいので、事前の水やりは避けてください。
土が乾燥していると、根がほぐれやすくなり、傷みにくくなります。
また、植えかえをする度に樹姿や根張りの状態をよく観察して、樹の向きや流れを変えて樹の魅力を引き出します。
植えかえでは、鉢の中にびっしりと回った古根を整理して切り詰めます。
太くて強い根ばかり伸びてしまうと根元の小さな根が育ちにくくなるので、できるだけ小さな根が多い樹になるように育てます。
植えかえ後は根元がぐらつきやすいので、針金で固定したりして、風が当たらない場所で管理をしましょう。
おわりに
盆栽の基本的な管理方法は、時間をかけてあわてず、ゆっくりと覚えましょう。
最初のうちは、盆栽の管理方法を間違えて失敗することもあろうかと思いますが、どんな失敗でも貴重な経験として必ず将来の盆栽づくりに役立つので、失敗を恐れず盆栽を育ててみましょう。
老後の趣味として人気がある「盆栽づくり」。
昨今では介護施設でも盆栽づくりの体験が取り入れられています。
施設に入っても趣味を続けたいなど、楽しみのある施設をお探しの方にオススメなサイトがあります!
全 国で4万件以上の介護施設と提携している「ケアスル介護」
「ケアスル介護」は、令和2年(2020年)12月にリリースされた理想の介護施設が見つかる有料老人ホームの検索サイト。
幅広い選択肢の中から本人に合った施設を選ぶことが出来るので、入居後のギャップを出来るだけ少なく施設探しをすることができます。
コラムでは介護や老後の生活に関するお役立ち情報を幅広く発信しているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

盆栽は、長きにわたり日本人に愛され、大切に継承されてきた日本の伝統文化です。
近年、盆栽は、海外でも芸術性が高く評価されているので、愛好家や富裕層のコレクターも増加していますが、盆栽の基礎知識については、意外と知られていないです。

盆栽は日本の伝統文化の1つなので、“いつか”自分で育てて楽しんでみたいと思っている人は、多いはずです。
しかし、実際に盆栽を育てた経験や知識がない初心者は、盆栽をどのように楽しんだら良いのでしょうか。
初心者が盆栽を楽しむ場合、余計な理屈は不要です。
盆栽は、自由に “自分流”で気軽に楽しむことが、1番です。

盆栽の植替えとは、樹の古い根や枝を切って新陳代謝を図るために行う作業です。植替えは、樹種の適期に手順良く行うと初心者でも失敗しないで出来る作業です。