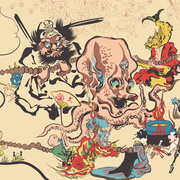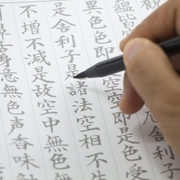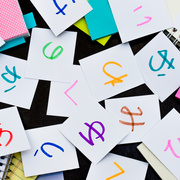日本の伝統文化の一つでもある盆栽。
興味があっても、剪定や管理が難しく費用もかかると思って、始めるのを諦めていませんか?
そんな方にぜひオススメしたいのが「苔盆栽」です。
苔盆栽は道端の苔を使い手軽に、立派に作ることができる上、育てるのも簡単!
この記事では、道端の苔を使って簡単にできる苔盆栽の作り方や、楽しみ方についてご紹介します。
苔盆栽とは
苔盆栽とは、盆栽鉢や自分の好きな陶磁器(小鉢、お皿、カップなど)に苔を“こんもり”と盛り上げるように植え付けた盆栽のことです。
直射日光を避けた半日陰や、木漏れ日がさす風通しの良い場所に置いておけば、長く楽しむことができます。
樹を植え付けて育てる一般の盆栽は、それぞれの樹種に合わせた剪定・整枝、針金かけや管理などが一年を通して必要です。
しかし、苔盆栽は樹の盆栽に比べて管理作業も簡単なので、盆栽経験がない方でも気軽に始めることができるでしょう。
苔盆栽は一般的な盆栽鉢を使えば、樹の盆栽と同じように日本の伝統文化の素晴らしさを感じることができます。
一方、洋風な器を鉢にして苔盆栽を作れば、あっという間にモダンな苔盆栽となり、お部屋のインテリアとしてもおしゃれな盆栽に仕上がります。
盆 栽に使っても良い苔
苔盆栽に使っても良い主な苔は、一般的な盆栽に使われる以下のような種類があります。
これらの多くは、普段通るような道端や駐車場のブロック塀との境目、神社や日陰に群生しています。
また、これらの苔は比較的寒さや乾燥にも強いので、取り扱い・育てやすさは抜群です。
使 ってはいけない苔
苔の種類によっては、苔盆栽や一般の盆栽に使ってはいけない苔もあります。
これらの苔は、増えて土の表面を覆い盆栽の生育を妨げてしまうのです。
盆栽に使っても良い美しい苔は、水はけが悪いと枯れてしまいます。
逆に、使ってはいけない苔は、水はけが悪いと増えてしまいます。
そのため、見つけたらすぐに取り除きましょう。
苔盆栽づくりの楽しみ方

苔盆栽づくりは、最初の鉢選びの段階から楽しさを感じることができます。
苔盆栽は鉢によって印象を変えます。
お子様向けとして、アニメのキャラクターがついている器を使うと、かわいらしく仕上がるでしょう。
また、お気に入りの鉢や器に一種類だけの苔を植えても楽しいですが、複数の苔を一緒に植えたり、山野草と一緒に植えたりしても趣ある苔盆栽に仕上がり、自分だけの小さな空間を楽しめます。
他にも、樹の盆栽と同じように石付けの苔盆栽に仕立てても、趣や風情があるものとなるでしょう。
このように苔盆栽は、「作る楽しみ」と「観賞する楽しみ」の二つの楽しみがあります。
まずは身近な場所に自生している“使っても良い苔”を見つけて、実際に作ってみましょう。
苔盆栽を実際に作ってみましょう!
用 意するもの
➀苔盆栽に使っても良い苔
前述したギンゴケ、タマゴケ、ニワスギゴケなど
② ケト土、赤玉土
ケト土と同量の赤玉土を一緒に使います。
ケト土だけを使用すると、乾燥した時に土が縮み苔の活着が悪く、固まった状態になり、水の吸水性が悪くなってしまいます。
活着とは、移植した植物が根づいて生長し始めることを意味します。
③鉢
盆栽鉢、自分の好みの器など(お気に入りのアニメキャラクターのカップ、湯のみなど)
④軍手
ビニール手袋でも可
⑤ピンセット
⑥霧吹きやジョーロ
⑦保存用タッパー(キッチン用)
⑧活性炭
鉢の中に溜まった水を濾過するために少々使います。
苔 盆栽の作り方の手順
①苔を採取しましょう
道端や駐車場のブロック塀との境目や、境内などに生えている苔で苔盆栽に使って良い苔を丁寧にピンセットで採取します。
②水に浸しましょう
採取した苔は、仮根についている土や汚れをきれいする必要があります。
仮根は、字のごとく仮りの根、根の先についている毛のようなもので、苔やシダ類に見られます。
苔より一回り小さめなタッパーに入れて、仮根を完全に水で浸しましょう。
その際、上下の向きが逆さにならないように苔を容器に入れて水に浸すことがポイントです。
しばらくすると苔の汚れや泥が水の中に浮いてくるので、水が綺麗になるまで水を取り替えながら浸します。
水に一晩位浸しておくと、苔が土に活着しやすくなります。
③土を作りましょう
ダマになっているケト土の塊に、水を少しずつ足しながらほぐして、活性炭や赤玉と一緒に混ぜて粘土状にします。
水の量は、土を握った時に水が滲んでくる位が目安です。
赤玉が混ぜやすいよう、細かく砕いたケト土を使うと簡単に作業ができます。
粘土状になった土は、ご飯をお茶碗にもるように鉢に盛り付けます。
④苔を貼りましょう
先程作った土に苔を貼り付けます。
ポイントは、苔と土の間がぴったりと隙間ができないように貼り付けることです。
隙間が出来ていると、苔が活着せずに枯れてしまいます。
ピッタリと隙間がないように貼り付けるコツは、苔の上から手のひらでやさしく押さえることです。
猫や犬の頭をやさしくなでるようにイメージして押さえると、苔と土を密着させやすくなります。
⑤活着するまで押さえましょう
苔に限らず、他の植物と同じように根が活着すると鉢土と密着し、動かなくなり、安定感が出てきます。
そのため、活着したかどうかの見極めは、苔が鉢土からずれないか、剥がれにくくなったかどうかです。
時間的には苔の種類、大きさ、土の状態、植付けの仕方など、色々な要素によって異なりますが、一般的には数週間位で活着します。
人ぞれぞれ、植え方の得手不得手がありますので、一概に活着するまで期間を特定することはできません。
しかし、活着するまでは、苔を押さないと苔の根の活着が遅れてしまいます。
植え付けが上手な人でも一週間から十日程度は抑えた方が無難でしょう。
苔は何かに吸着していないと枯れてしまう植物なので、苔が土に活着するまでしばらくの間、手のひらで上から何度も押さえます。
⑥活着したら完成です
苔が土に活着したら完成です。
苔盆栽を長く楽しむためには
苔盆栽の管理はとても簡単です。
正しく管理をして、苔盆栽を長く楽しみましょう。
置 き場所は半日陰や木漏れ日のある場所
苔盆栽は日陰に置いたままにしておくと色が悪くなってしまうので、ある程度風通しが良い、半日陰や木漏れ日のある場所で管理をしましょう。
また、風当たりが強すぎるとギンゴケは白っぽく、スナゴケは茶色に変色してしまいます。
水 やりは霧吹きで
苔盆栽は常に湿っている状態が理想です。
そのため、水やりをする際は霧吹きを使い、鉢の上から水が溢れるくらいたっぷりと与えましょう。
水やりは乾燥状態をチェックしながら朝晩してください。
霧吹きで水やりをする際は、苔が動かないように注意しながら行いましょう。
植えたばかりで苔が土に活着しないうちは、上からキッチンペーパーなどで苔を覆って、苔が動かないようにしてから水やりをすると良いです。
苔盆栽が乾燥しているかどうか判断ができない時は、鉢を持ってみましょう。
苔盆栽の鉢が少し軽くなっていたら、乾燥しているというサインです。
また、苔は一度乾燥してしまうと再度水を吸収しないので、乾燥しないように日頃の水やりに注意してください。
肥 料は不要
苔盆栽の肥料は、基本的に不要です。
他の樹や山野草などと一緒に組み合わせて植え付けてある苔盆栽は、それぞれの植物に応じた肥料が必要となりますが、置き肥を与えると肥料焼けを起こすことがあります。
もし、肥料を与える場合は、薄めた液肥を与えましょう。
木 酢液で害虫対策をしましょう
苔盆栽はきちんと管理をしていても、置き場所や気候によって小さな害虫が発生することがあります。
その場合は、木酢液を指定の量で薄めたものを、霧吹きで散布すると害虫対策に効果的です。
木酢液とは、木炭や竹炭を焼くときに出る水蒸気や煙を冷やし、液体にしたものです。
光 合成をする機会を与えましょう
苔も植物なので光合成が必要です。
一週間に二回位は、屋外の直射日光が当たらない場所に置き、苔が光合成する機会を与えてあげましょう。
屋外での光合成は、苔のカビ発生防止や美しい緑色の維持にも効果的です。
また、レースカーテン越しの窓際に置いている場合でも、二日に一回位は外気の風に当ててあげると生育が良くなります。
おわりに

苔盆栽は樹を植えた盆栽とは異なり、手間がかからないので気軽に楽しむことができる、とてもおしゃれな盆栽です。
最近では、苔盆栽の室内向けキットがネット通販等でも販売されており、簡単に苔盆栽づくりを楽しむことができます。
苔盆栽は樹の盆栽よりハードルが低いので、盆栽に興味のある方はぜひ、苔盆栽から始めてみてはいかがでしょうか。

盆栽は、長きにわたり日本人に愛され、大切に継承されてきた日本の伝統文化です。
近年、盆栽は、海外でも芸術性が高く評価されているので、愛好家や富裕層のコレクターも増加していますが、盆栽の基礎知識については、意外と知られていないです。

何か趣味が欲しいな…と、お考えのあなた!
ぜひ、盆栽を始めてみませんか?
「盆栽はおじいちゃんがやるのもの」だなんて、大間違い!
海外では「BONSAI」ブームが巻き起こっているほどなのです。
楽しみながら自分にあった方法を見つけて、ぜひ盆栽を始めてみましょう。

紅葉は日本各地に自生しており、日本人にとって最も馴染み深い樹種の一つではないでしょうか。また、もみじは約160種にも及ぶ樹種が世界各地に自生していると言われ、その中の約30種が日本に自生しています。