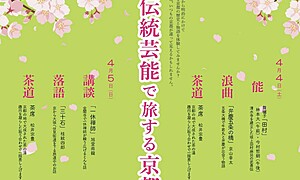全国屈指の温泉スポットとして名高い別府市の温泉は、源泉数・総湧出量ともに日本一を誇っています。
全国から人々が訪れる大人気の観光地・別府ですが、実はその魅力は温泉だけじゃないんです!
今回は、別府市を拠点に活動するアートNPO「BEPPU PROJECT」さんにご招待頂き、大分県文化観光拠点ツアーに参加させていただきました♪
本記事では、ツアーで訪れたスポットとその魅力をご紹介します。
ぜひ、観光の参考にしてみてくださいね!
別府温泉と竹の関係

今回参加させていただいたツアーでは、大分県の伝統的工芸品・別府竹細工をメインに、別府の街を巡りました!
大分県は、日本一のマダケの産地です。
別府竹細工をはじめ、古くから別府の人々の生活には竹製品が使われてきました。
別府では、今も温泉へ行く時に竹バッグを使用する人がいるほど身近な存在です。
そのほかにも、温泉の蒸気を利用して食材を蒸す「地獄蒸し料理」で竹籠が使われたり、高温の温泉を入浴可能な温度に冷ますための冷却装置にも竹が使われていたりと、まさに竹は別府温泉と切っても切れない関係にあるのです!

【1日目】別府竹細工の旅スタート!
別 府竹細工販売店「cotake」
竹細工の魅力を知るためにまず向かったのは、別府竹細工を販売・展示している竹細工専門店「cotake」。
店名は漢字で“子竹”と記します。
これは、“子”という漢字に含まれる「一から了(最後)までの一生」という意味にちなんで、「竹を、一から了の中に少しでも取り入れてほしい」という願いからつけられたそうです。
迎えてくれたのは、オーナーであり工芸家の佐藤美樹子さん。
約6年前、はじめて訪れた別府市竹細工伝統産業会館で現在の竹細工の姿に感銘を受け、職人になることを決意し、お店を開いたそうです。
現在は、アクセサリーやバッグなどのファッション小物を中心に、竹細工を製作しています。
そんなcotakeでは、佐藤さんの作品はもちろん、竹細工作家さんのさまざまな作品を展示・販売しています。
店内には工房が併設されており、職人の製作の様子を間近に見ながら竹細工を楽しむことができました♪

またcotakeでは体験も行っているそうで、職人さんの工房で実際に竹細工の体験ができるのはかなりレアなのだとか!

日常生活で使いやすいおしゃれな竹細工から、伝統的で重厚感のある竹細工まで、さまざまな作品が展示されており、とても魅力的でした♡
※情報は変更となる場合がございます。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
古 民家コミュニティスペース「Space Beppu」

次に向かったのは、古民家を利用して作られたコミュニティスペース「Space Beppu」です。
令和5年(2023年)にオープンしたばかりのこちらの施設は、築105年の古民家をリフォームして作られているそうです。

1階では、大分県の老舗竹加工メーカー・永井製竹株式会社の製品や、木のおもちゃ、木琴など、さまざまな木や竹の製品を販売。
2階には、別府の歴史を学べる写真展示とブックカフェがありました♪
写真展示スペースでは、こんな写真も発見!

なんと昔、別府には、奈良の大仏の1.6倍もの大きさがある別府大仏がいたのだそう!
コンクリートで作られていましたが、亡くなった方の供養のため、中に遺骨や遺灰を混ぜて作ったことで、脆くなり老朽化が進んでしまったとのこと。
それにしても、奈良の大仏の1.6倍とは、すさまじい大きさですね…!
※情報は変更となる場合がございます。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
別 府竹細工を支える大黒柱「永井製竹株式会社」

続いて、Space Beppuにも作品を置いていた、明治41年(1908年)創業の竹加工会社「永井製竹株式会社」へ向かいました。
竹細工作家は、主に竹ひごを使用して竹製品を製作しますが、自分で竹を採ってくるわけではありません。
“切子“と呼ばれる業者が竹林から竹を伐採し、加工会社で竹ひごの状態にしてから、やっと作家の元へ届けられるのです。
永井製竹株式会社は、そんな竹加工の作業を担う数少ない会社です。
ここでは、竹の加工がどのように行われるのか、実際の作業場を見ながら説明をしていただきました。
伐採してきたばかりの竹は、油を含んでいます。
油を落とさない竹を青竹、油を落とした竹を白竹と呼び、別府竹細工には表面の美しさがより長く保たれる白竹を使用するが一般的だそうです。
油を落とす作業は、以下の手順で行われます。

油を落とす前の竹が写真真ん中、油を落とし拭き取った竹が写真右、油を落として乾燥させた竹が写真左です。
白竹の名の通り、油を落とすとクリーム色に変化するのですね!

天日干しの様子はこんな感じ!
長い竹を扱うのは、相当な力仕事です。
あの美しい竹細工は、この大変な作業を担う職人たちの力があってこそのものなのだと、改めて実感することができました。
※情報は変更となる場合がございます。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
竹の魅力に出会う「OPAM 大分県立美術館」

続いては、“五感のミュージアム”がコンセプトの「OPAM」へ。
建築家の坂茂さんによって設計されたOPAMは、全面ガラス張りの建物や竹細工を彷彿とさせるデザインが美しい美術館です。
この日は、令和5年(2023年)10月17日(火)~11月4日(土)まで行われていた竹イベント“竹会”にお邪魔しました!

竹藝家のこじまちからさんがディレクションを行った1階のイベントブースでは、別府竹細工で飾られた空間を楽しむと共に、別府竹細工の製作工程を学ぶことができます。
奥のエリアでは、こじまさんが実際に竹細工の材料である竹ひごを取る作業を実演。

1本ずつ異なる竹の節を意識しながら、専用の刀を使って竹を一気に半分に割り、これを繰り返していきます。
色とツヤが綺麗で扱いやすい、表面の皮の部分だけを使うため、竹1本のうち3分の1は使われないそうです。
竹細工は材料採取が命の工芸品で、その難しさは「ひご取り3年」と言われるほど。
一見簡単そうに見えるのは、まさに職人の技術の賜物なのですね!
2階の展示コーナーでは、作家さんたちの竹工芸品をコレクションしたイベント“此君礼賛”が行われていました。

竹細工には、設計図がなく、8種類ある基本の編み方を組み合わせることによって、200種類以上の編み方が可能となります。
まさに数学の世界といっても過言ではなく、別府市にある日本唯一の竹工芸の学校では、入学試験として数学のテストもあるそうです!
夜には音楽ライブも行われました。
竹製のおちょこに地元の日本酒を入れて頂き、おつまみのメンマを受け取ったら、準備万端!

竹で作られたパンフルートやオリジナルのパーカッション、さらにこじまさんが自ら作った竹製のギターなどの楽器を使用した三重奏がはじまりました。
パンフルートの奏でる美しい音色に、思わずうっとり♡
時間を忘れて楽しんでしまいました。
これで、1日目は終了です。
繊細で美しい竹細工の数々に圧倒され、さまざまな形の竹に可能性を感じた、まさに竹尽くしの1日でした♪
※情報は変更となる場合がございます。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
【2日目】別府竹細工の旅、最終日
竹 のルーツを学ぶ「別府市竹細工伝統産業会館」

2日目は、昨日訪れたcotakeのオーナー・佐藤さんが竹細工に目覚めた場所「別府市竹細工伝統産業会館」からスタート!
竹細工の歴史はもちろん、素材や技法を知ることができる施設です。
展示室の中には、なぜかエジソンの写真と彼が発明した白熱電球が展示されていました(!?)。
聞くと、エジソンは白熱電球開発の際、6000種類もの材料を試した結果、京都八幡産の真竹が一番持続力が良いという結論に至ったそうです。
こちらに展示されている電球は、平成6年(1994年)の開館以降、一度も切れていないというから驚きですね!

他にも、竹工芸ではじめて人間国宝に認定された、別府市出身の作家・生野祥雲斎の作品や、竹製のフェイスシールド、花瓶、コーヒードリッパーなど、近年の生活様式にあった竹細工作品が展示されていました。
この日は見ることができませんでしたが、2階にある研修室では、体験学習やワークショップ、後継者育成教室などが行われているそうです。
※情報は変更となる場合がございます。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
竹のアクセサリー作りに挑戦!「竹楓舎」

ここまで、さまざまなコンテンツを通して別府竹細工の魅力を学んできました。
続いて向かったのは、別府竹細工伝統工芸士・大谷健一さんの工房「竹楓舎」。
大谷さんのご指導のもと、いよいよ、竹細工の製作体験をさせて頂きます♪
今回挑戦するのは、竹のペンダント製作です。

途中まで組まれた丸い竹のパーツを使って、ペンダントパーツを作っていきます♪
今回使う編み方は、“やたら編み”という技法です。
“やたらめったら”編むことからきている名称で、法則性がないため、編む人のセンスが問われる編み方なのだそう。
編む人のセンス…なんだか緊張してきました!
まず、ひごを曲げた時に竹が割れてしまうのを防ぐため、水の入ったスプレーでパーツ全体を濡らします。

次に、各方向に飛び出ている竹ひごの長いものから順番に、空いている穴に差し込み、他の空いている穴から先を出していきます。
あとは、ただひたすらにこれを繰り返すだけ!
一見簡単に聞こえるかもしれませんが、これがなかなか難しい……。
全体が綺麗に見えるように考えながら、できるだけ竹が交差するように入れていかなくてはならないのですが、作り進めると穴はどんどん少なくなり、入れられる場所も限られてきます。
入れられる場所がなくなったら、先のとがった棒を差し込んで穴を作り、そこに入れていきます。
ですが、無理にやりすぎると竹が割れてしまいます。

苦労しながら慎重に差し込み続けていき、なんとかパーツが完成!
間に金具を差し込み、紐を通したら、ペンダントの出来上がりです♪

はじめに作り方を聞いた時は、「ふむふむ…、意外と簡単なのでは!」と思っていたのですが、完成形を見通しながら作り進める必要があり、かなり頭を使う工芸品なのだな…と改めてその奥深さを実感しました。
竹楓舎では、日本人だけでなく海外の方も体験に参加できるそうなので、気になった方はぜひチェックしてみてください♡

※情報は変更となる場合がございます。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
名 物地獄蒸し体験「湯治の宿 大黒屋」

さて、お昼の時間になりました!
お昼は、温泉の蒸気で食材を蒸して作る別府の名物・地獄蒸しを体験しました♪
「湯治の宿 大黒屋」は、地獄蒸しが体験できるお宿です。
事前にオススメの食材を用意していただき、宿の前にある“地獄釜”で食材を蒸していきます。

今回は特別に、地元の野菜を販売する「かんなわ六角ストア」で気になる食材を調達できるとのことで、私は蓮根をチョイスしました♡
竹籠に並べた食材を100℃の釜に入れ、蓋をして蒸せば…あっという間に完成です!

蒸しあがった食材はさらに彩りが良くなり、とっても美味しそう♡
塩コショウやポン酢、大黒屋さん特性の辛いタレを付けていただきます。
うーん…美味しい!!
素材の美味しさが、ダイレクトに伝わってきます!
なにより先ほど選んだ蓮根が、今まで食べた蓮根の中で一番美味しいと言っても過言ではないほど、甘くてみずみずしい♪
野菜の甘さが引き立つ理由は、100℃の高温で野菜の甘味がぎゅっと濃縮されるからだそうです。
大黒屋に宿泊した方はいつでも地獄釜を利用できるそうなので、別府旅行の際はぜひこちらに泊まってみてはいかがでしょうか?

※情報は変更となる場合がございます。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
竹 林で癒される「ハーモニーランド 竹林公園」

さて、地獄蒸しでお腹を満たしたら、いよいよこの旅最後のスポット、日出市にある「ハーモニーランド 竹林公園」へ向かいます。
実はこのハーモニーランド、あの世界的人気キャラクター・ハローキティが属する、サンリオの屋外型テーマパークなんです!!!
サンリオなのに竹林!?とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんね。
なんとハーモニーランドは、園内面積の4分の1が竹林です。
園内を進み竹林エリアまで歩いていくと、見渡す限りの竹が天高く伸び、あたり一面を彩っています。

さわさわと竹が揺れる音が心地よく、風情があります♡

看板が竹モチーフになっていてかわいいですね。
こんなに美しい竹ですが、「竹害」という言葉があることをご存知でしょうか。
竹は倒れにくく、とても生命力が強いため、放っておくと雑草のごとく増殖してしまうのです。
竹はぐんぐん伸びて、太陽光を遮り、他の植物を枯らしてしまったり、地下に這った根が地滑りの原因になったりします。
この竹害を解決すべく、放置竹林から伐採した竹でメンマを製造し、お土産として販売したり、大分県下では毎年竹を使ったお祭りが行われたりしているそうです!
竹細工を製作することは、こういった竹害を防ぐことにも繋がっているのですね。
※情報は変更となる場合がございます。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
旅を終えて
今回の旅で、はじめて別府に訪れた私。
旅に行く前は、「別府といえば温泉!」というイメージを持っており、竹細工のことはあまり知りませんでした。
しかし、今回の旅で、別府という地域と竹製品の深い繋がりを学ぶことができ、別府に来るなら、温泉と一緒に竹細工のことも知ったら、もっと楽しいのに!と、周りの人に伝えたくなるような情報をたくさん知ることができました♪
別府竹細工は、観賞としてだけでなく、実際に日用品として「使える」工芸品であることが魅力です。
使ううちに色が飴色に変わっていくため、経年劣化を楽しむことができる「育てる」工芸品でもあります。
別府に来る際は、本日ご紹介したスポットにぜひ足を運んで、竹細工を手に取ってみてくださいね!
別府の旅を、さらに有意義なものにすることができるはずですよ♡

100℃近くある7つの源泉をめぐる“別府地獄めぐり”など、温泉好きにはたまらない大分県。そんな大分県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、10品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって大分県の「伝統的工芸品」として指定されている別府竹細工をご紹介します。