長い歴史と伝統が息づく古都・京都には、世界的にも名の知れた有名なお祭りから地元の人達によって大切に受け継がれている年中行事まで、さまざまなイベントが1年を通して行われています。
そこで今回は、京都で一度は見に行きたいお祭り・行事・イベントを一覧でご紹介します♪
1月の京都のお祭り・行事・イベント
初 天神(北野天満宮)
初天神は北野天満宮にて年明け最初に行われる天神様を祭る縁日です。
境内には1000軒もの露店が並び、宝物殿の神宝の特別公開や奉納書初めの作品展なども行われます。
受験シーズンにむけ、合格祈願で参拝する受験生の姿なども多く見られます。
開催日:1月25日

志望校へ合格するためには毎日の勉強が大切なのは間違いないのですが、最後の一押しとして神社で手を合わせて、学問の神様に合格を祈願したいところですね。今回はそんな受験生のために、合格祈願にオススメの神社を紹介します。
2月の京都のお祭り・行事・イベント
節 分祭
冬と春の節目の節分には、京都各地の寺院や神社にてさまざまな節分祭が行われます。
なかでも、京都御所4方の鬼門を護る神社(吉田神社、壬生寺、北野天満宮、八坂神社)をお参りする「四方参り」は、邪気を払って福を招くとして千年も前から節分に行われてきた京都の風習として有名です。
開催日:2月3日
吉田神社
節分の当日を中心とした前後3日間にわたり行われる「吉田神社」の節分祭。
疫神祭・追儺式(鬼やらい)・火炉祭といった祭事が行われます。
壬生寺
幕末の志士・新選組とゆかりがあることでも有名な「壬生寺」の節分会。
厄除けなどの祈祷のほか、重要無形民俗文化財の壬生狂言の中から厄除け鬼払い壬生狂言『節分』が上演されたり、近所の保育園児のお稚児行列が見られます。
北野天満宮
「北野天満宮」の節分祭では、狂言大蔵流の名門・茂山千五郎社中による狂言、上七軒の舞妓さん・芸妓さんによる日本舞踊が奉納された後、豆まきが行われます。
八坂神社
2月2日、3日に行なわれる、京都・祇園「八坂神社」の節分祭では、四花街の芸妓さん・舞妓さんたちによる豆まきのほか、舞踊奉納がなされます。
空くじなしの景品福引付き福豆といった授与品もあり、多くの方が楽しまれる節分祭です。

皆さんは「節分」と聞くと何を思い浮かべますか?保育園や幼稚園、小学校で豆まきをして鬼退治をした!なんて思い出がある人も多いのではないでしょうか。今回の記事では、節分とは本当はいつ行うものなのか、由来や歴史、豆をまく理由、行事食などをご紹介します。
3月の京都のお祭り・行事・イベント
流 し雛(下鴨神社)
3月3日の桃の節句に下鴨神社にて行われる神事です。
境内を流れる御手洗川に、和紙で作った着物に土を丸めて胡粉を塗った顔をつけた雛人形を編んだ藁にのせて流し、災厄を払い女児の健やかな健康と成長を祈ります。
開催日:3月3日
※令和2年(2020年)は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
京 都・東山花灯路
平成15年(2003年)3月には京都・東山地域、平成17年(2005年)12月からは嵯峨、嵐山地域でもスタートした「灯り」をテーマにした京都の春の風物詩として定着している季節イベントです。
古都・京都の町に行灯の灯りが広がり、普段とは異なる夜の風景が楽しめますよ。
開催日:3月6日~3月15日
※令和2年(2020年)は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
北 野をどり(上七軒歌舞会)
北野天満宮にて行われる、春のはじめの舞踊公演です。
フィナーレの「上七軒夜曲」では、黒裾引摺姿に揃えた芸妓さんと色とりどりの鮮やかな衣装を身に着けた舞妓さんが総出演で華やかな演目が披露されます。
開催日:3月20日~4月2日
※令和4年(2022年)は10月8日(土)~10月22日(土)開催予定
※令和2年(2020年)は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
桜 ライトアップ
数多くの桜の名所が点在する京都では、ライトアップとともに夜間特別拝観などが各所で行われます。
なかでも二条城や、丸山公園・平野神社・祇園白川・京都府立植物園で行われるライトアップが有名です。
開催日:3月下旬~4月上旬
4月の京都のお祭り・行事・イベント
京 おどり(宮川町歌舞練場)
京都花街の一つ「宮川町」で行われる春恒例の催しです。
宮川町の芸舞妓さんが総出演し、毎年新しく書き下ろされた内容で舞を披露する華やかな舞台芸術を楽しむことができます。
開催日:4月1日~4月16日
※令和2年(2020年)は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
都 をどり(祇園甲部歌舞練場)
明治5年(1872年)にはじまった京都最大の花街・祇園甲部の芸舞妓さんによる華やかな舞踊公演で、1ヶ月に渡って行われます。
「ヨーイヤサー」の掛け声とともに幕を開ける華やかな舞台は、京都・祇園を代表する春の催し物として親しまれています。
開催日:4月1日~4月30日
※令和2年(2020年)は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
神 幸祭 おいで(松尾大社)
松尾大社の神幸祭は、平安時代にはじまった千年の歴史がある行事です。
松尾七社の神輿が境内を出発し、桂離宮の東北側から桂川を船で渡る光景は迫力満点です。
開催日:毎年4月20日以後の第一日曜日に開催
曲 水の宴(城南宮)
城南宮神苑内の平安の庭で行われる雅な宴の行事です。
平安貴族の装束を身につけた歌人が小川の辺に座り、川上から流れてくる朱塗りの盃が自分の前を流れ過ぎる前に歌を作り、盃を取り上げて酒を頂きます。
開催日:4月29日(昭和の日)
壬 生狂言 春の大念佛会
国の重要無形民俗文化財に指定される壬生狂言は、700年あまりの歴史ある仏教無言劇で「カンデンデン」と響く鐘に合わせて、無言劇が繰り広げられます。
奉納された素焼きの器を狂言舞台から叩き落す「炮烙割り」は迫力があります。
開催日:4月29日~5月5日
5月の京都のお祭り・行事・イベント
鴨 川をどり(先斗町歌舞練場)
明治5年(1872年)に創演された先斗町歌舞会の華やかな芸舞妓さんによる舞踊公演です。
豪華絢爛な舞台は伝統を継承しつつ、時代を反映した内容構成で人々を魅了してきました。
会期中はお茶席が設けられているため、開演前に芸妓さんのお点前を堪能することもできます。
開催日:5月1日~5月24日
納 涼床・川床
京都の夏の風物詩「納涼床・川床」は、水辺の涼しい風を感じながら各店自慢の料理を味わうことができる、京都ならではの風情ある夏の食事の楽しみ方です。
鴨川納涼床
納涼床・川床には「鴨川納涼床」、「貴船の川床」、「高尾の川床」、「しょうざん渓涼床」がありますが、なかでも鴨川納涼床は安土桃山時代まで遡る古い歴史があります。
鴨川西岸沿いに100店余りもの料亭や旅館が床を張り出し、風情ある納涼を堪能しようと多くの人で賑わいます。
開催日:5月1日~9月30日
神 幸祭 氏子祭(八大神社)
京都市東北部、一乗寺一帯の各地域から神輿や重要文化財の剣鉾などが巡行し、八大神社に集まるお祭りです。
夜には神社から下がり松にかけてかがり火が炊かれ、町の人々の奉仕により盛大に執り行われます。
開催日:5月5日
葵 祭(下鴨神社・神賀茂神社)
約1500年も前から受け継がれる京都最古の祭りであり、京都三大祭の一つです。
平安王朝の風俗を厳密に再現した装束の行列と、牛車すべてにフタバアオイの葉と桂の枝をさし、京都御所から下鴨神社・上賀茂神社への都大路を優雅にねり歩きます。
開催日:5月15日

葵祭とは、祇園祭と時代祭に並ぶ京都三大祭りの一つです。他の2つの祭りに先駆け、毎年5月15日に行われる賀茂社(上賀茂かみがも神社と下鴨しもがも神社)の例祭です。この記事では、そんな葵祭の由来をはじめ、どのようなお祭りなのか、葵祭の見どころをご紹介します!
6月の京都のお祭り・行事・イベント
貴 船祭
貴船神社で最も重要な祭りで、本宮での祭典にはじまり舞楽などが奉納された後、神輿が貴船町内を巡行して奥宮へと向かいます。
奥宮では島根県の貴船神社・出雲神楽団による出雲神楽が奉納されます。
開催日:6月1日

京都屈指のパワースポットとして有名な『貴船神社』。京都市内から離れた山奥にあるにもかかわらず、多くの参拝客が訪れる人気スポットです。当記事では貴船神社に古くから伝わる逸話や伝説をはじめ、行事や見どころ、周辺のオススメ観光スポットをご紹介します!
京 都薪能(平安神宮)
京都市と京都能楽会の共催ではじめられた京都薪能は、能や狂言の普及と発展を目指して初夏の夜に平安神宮にて開催される幻想的なイベントです。
闇夜の能舞台の周りにはかがり火が焚かれ、観世・金剛・大蔵の各流派による能や狂言が楽しめます。
開催日:6月1日~6月2日

薪能とは、神社仏閣などの野外に設置された能舞台や特設舞台の周囲に、かがり火を照明として上演される「野外能」です。寺社巡りやお城巡りが好きな方は、目にしたこともあるのではないでしょうか?今回は能・狂言に興味をお持ちの方、これから観てみようという方にオススメしたい薪能の基礎知識や魅力、鑑賞のポイントなどをご紹介します。
7月の京都のお祭り・行事・イベント
祇 園祭(八坂神社)
京都三大祭の一つで、7月の1ヶ月を通してほぼ毎日、さまざまな祭事が行われる京都の夏を代表する盛大なお祭りです。
宵山には数多くの屋台で立ち並ぶ他、山鉾巡行の際には沿道が多くの見物客で賑わいます。
開催日:7月1日~7月31日

京都の祇園祭りといえば、「コンチキチン」の甲高いお囃子に、豪華絢爛な山鉾(やまほこ)巡行。観光客の多い京都の街が、いっそう人であふれる夏のお祭りです。特に、山鉾行事はユネスコの無形文化遺産にも登録され、毎年数十万人が見物に訪れるそうです。
鵜 飼(嵐山・宇治川)
鵜匠が昔ながらの装いで、船上にて飼いならした海鵜を操り、川魚をとる伝統的な漁法で、京都の夏の風物詩。
古い歴史をもつ「嵐山の鵜飼」は、嵐山の夜景とかがり火が炊かれるなか、幻想的な光景を楽しむことができますよ。
また「宇治川の鵜飼」は、全国でも数少ない女性の鵜匠が巧みに鵜を操るさまを間近に見ることができます。
開催日:嵐山の鵜飼 7月1日~8月31日
宇治川の鵜飼 7月1日~9月30日

この記事では鵜飼(うかい)の歴史や、鵜舟を先導する鵜匠・鵜のこと、全国の鵜飼地についてご紹介します。
本 宮祭 宵宮祭(伏見稲荷大社)
伏見稲荷大社で行われる神事で、全国の稲荷大神を祭る崇敬者が総本宮である伏見稲荷大社に参拝し、日々の神様の恵みに感謝をするものです。
本宮祭前日の宵宮祭では、境内の石灯篭や数千にも及ぶ献納提灯などに灯をともす万灯神事が行われ、幻想的な風景が広がります。
開催日:本宮祭 7月土用入後初の日曜又は祝日
宵宮祭り 本宮祭の前日

お稲荷さんの愛称で親しまれている“稲荷神社”は全国各地にあり、私たちにとっても大変身近なお参りスポットです。今回ご紹介する京都の『伏見稲荷大社』は、その総本宮というだけあって、1300年以上の歴史を持つ見どころ満載の神社です!この記事では、有名な千本鳥居から穴場まで、伏見稲荷大社の魅力を存分にお伝えします。
8月の京都のお祭り・行事・イベント
御 手洗祭(北野天満宮)
北野天満宮で行われる伝統の七夕神事を「御手洗祭」と呼びます。
無病息災を祈願して境内の御手洗川に素足をつけて邪気祓いを行う「御手洗川足つけ燈明神事」を行い、五色の中から選んだろうそくに火をつけて奉納を行います。
開催日:7月下旬~8月上旬
八 朔(八月朔日)
八朔は8月1日のことで、古来より京都ではこの日に恩義のある人に贈り物をする風習がありました。
現代では、京都の八朔といえば花街の芸舞妓さんが黒紋付に髪を結った正装で、日頃恩義のある家元の師匠やお茶屋などに挨拶回りをする伝統行事として知られています。
開催日:8月1日

皆さんは、8月1日が「八月朔日」や「八朔」と別の呼び方をされることをご存知でしょうか?京都・祇園では「八朔」は特別な日であり、夏の風物詩としても知られています。この記事では、八朔とは何か、どのような歴史があるのか、そして舞妓さんとの関係やどのようなことが行われるのか、八朔についてご紹介します!
京 の七夕
京都の現代版・七夕まつりとして平成22年(2010年)から開催されているイベントです。
堀川エリアの二条城ライトアップをはじめ、鴨川、梅小路、北野天満宮周辺、また令和元年(2019年)から京都北部の宮津市も加わり、京都全体で七夕を盛り上げています。
開催日:8月1日~8月31日
※エリアにより開催期間が異なります
五 山送り火

かがり火を5つの山で焚き、お盆にお迎えしたご先祖様の霊をあの世へと送る盂蘭盆会の行事で、京都市の無形民俗文化財です。
東山に「大文字」が浮かび上がった後、西に向けて順に「妙法」→「船」→「左大文字」→「鳥居」と点火されていきます。
京都の夏の夜空に静かに燃え上がる光景は幻想的です。
開催日:8月16日

五山送り火とは、京都市で8月16日に行われる伝統行事です。京都の街を取り囲む山々で、5つの大規模な「送り火」が焚かれ、燃え上がる火で「大」「妙」「法」の文字と「船」「鳥居」の形が描かれます。この記事ではベストスポットや関連行事などをご紹介します。
六 道まいり(六道珍皇寺)
六道まいりは、お盆を前にご先祖の霊を迎えるため、六道珍皇寺を参拝する風習で「お精霊さん迎え」とも呼ばれています。
期間中は重要文化財の薬師如来や寺宝なども公開され、多くの参詣者が訪れます。
六道珍皇寺

六道まいりで知られる六道珍皇寺は、平安時代以前に建立された古い歴史を持つ寺院です。
この世とあの世の分岐点で冥界への入り口となる場所が境内の門前あたりにあると古来より信じられていたことから、お盆にはご先祖の霊を迎える鐘をつくために参詣します。
開催日:8月7日~8月10日

京都では毎年、お盆の少し前に「六道まいり」と呼ばれる、ご先祖様の霊を迎えるためにお寺へ参詣する行事が行われます。京都の人々は親しみを込めて、ご先祖様の霊のことを“お精霊さん”や“おしょらいさん”と呼び、この行事を大切にしてきました。
9月の京都のお祭り・行事・イベント
八 朔祭(松尾大社)
立春から数えて二百十日前後に行われるお祭りで、収穫を控えた大切な時期に風雨安泰と五穀豊穣を神様に祈る行事として行われてきました。
八朔相撲のほか、女神輿の巡行、また無形文化財でもある嵯峨六斎念仏踊など伝統芸能の数々が行われ奉納されます。
開催日:9月の第一日曜日
重 陽の節句
重陽の節句は9月9日に行われる五節句の一つで、別名「菊の節句」とも呼ばれています。
陰陽道の考え方では奇数は縁起が良いとされ、その最大の数字が重なるめでたい日に、菊の花をお供えして邪気払いと長寿を願います。
この日は京都の寺院や社寺でさまざまな神事がおこなわれているので、ぜひ回ってみてください。
開催日:9月9日
烏相撲・重陽神事(上賀茂神社)
烏相撲は、上賀茂神社の重陽神事の祭典の一つです。
白い装束の神職が烏の鳴き声を上げてユーモラスな受け答えを行った後、東西に分かれた氏子の子ども達による奉納相撲が行われます。
参拝者には菊酒が振る舞われますよ♪
開催日:9月9日

重陽の節句とは、いったいどんな日なのでしょう。現代では影が薄く、忘れられがちな重陽の節句。実はとてもおめでたい日なのです。今回は重陽の節句の意味や過ごし方について、簡単に紹介していきます。
10月の京都のお祭り・行事・イベント
ず いき祭(北野天満宮)
京都の秋を代表するお祭りの一つで、里芋の茎である「ずいき」や穀物、野菜、湯葉、麩などの食べ物で飾った珍しい神輿が北野天満宮から西ノ京の御旅所の間を巡行します。
秋に収穫される野菜や穀物をお供えし1年の五穀豊穣に感謝をするお祭りの期間中には、周辺に多くの出店が立ち並び賑わいます。
開催日:10月1日~10月5日
時 代祭(平安神宮)

京都三大祭の一つである時代祭は、明治28年(1895年)に平安遷都1100年を奉祝する行事としてはじまり、毎年平安神宮にて催されています。
延暦時代から明治維新まで、さまざまな時代ごとに厳密に再現された衣装を身にまとい、それぞれの時代の調度品や祭具などとともに約2,000人が2kmにもおよぶ行列が進む光景は豪華絢爛です。
開催日:10月22日

秋が深まる頃、毎年京都で盛大に行われる「時代祭」。葵祭、祇園祭と並ぶ京都三大祭の一つに称され、参加者およそ2000人、長さ2㎞におよぶ時代行列が都大路を練り歩きます。この記事では、令和の時代にも受け継がれている京都市民の心意気とも重ね合わせて、時代祭の由来や見どころルートなどをテーマにご紹介します。
大 陶器市・清水焼の郷まつり
清水焼団地町一帯にて、年に一度開催される京焼・清水焼を中心とした陶器市。
150組以上の陶磁器卸や陶芸家が出店し、多種多様な器が特別価格にて販売されます。
団地内では、府内各地から農産物や加工品といった絶品グルメが揃う“京都ほっこりひろば”や楽焼コーナー、ロクロ体験、京陶人形絵付け体験などが催され、例年多くの人が訪れます。
開催日:10月中旬
※開催時期については公式HPをご確認ください

学生から海外の方、さらには地元民まで、連日多くの観光客が訪れる京都屈指の観光名所であり、世界文化遺産にも認定されている『清水寺』。この記事では、清水寺の歴史や見どころ、オススメの観光シーズンまで、清水寺に関する情報を盛りだくさんでお届けします♪
11月の京都のお祭り・行事・イベント
曲 水の宴(城南宮)
4月の行事でもご紹介した城南宮の曲水の宴は、11月にも行われます。
秋は紅葉が色づきはじめる神苑が美しく、なんとも優雅な光景が広がりますよ。
開催日:11月3日(文化の日)
も みじ祭り
もみじの名所が点在する京都では、さまざまなもみじ祭が各スポットにて行われます。
真っ赤に色づいたもみじの絨毯が広がる神社仏閣境内では、特別拝観をはじめ、趣向をこらしたライトアップなどが楽しむことができ、毎年国内外からの観光客で大いに賑わいます。
嵐山もみじ祭
京都を代表する紅葉の名所、嵐山渡月橋上流周辺で行われる「嵐山もみじ祭」では、能楽や舞楽、今様歌舞などさまざまな芸能船が大堰川に浮かび、川を上り下りしながら技を披露するほか、河原でも数々のイベントが催されます。
開催日:11月第2日曜日
もみじ祭(地主神社)
縁結びの神様として知られる地主神社はもみじの名所でもあり、毎年秋には豊作と縁結びのご利益に感謝をするもみじ祭が催されます。
祭りでは神楽“もみじの舞”、“剣の舞”、“扇の舞”の奉納のほか、火焚神事なども行われ、家内安全・商売繁盛を祈願します。
開催日:11月23日

全国各地で見られる秋の紅葉の中でも歴史ある場所や建物が多い“京都の紅葉”は、やはり格別。しかし、実際に訪れるとなると、名所が多いだけにどこへ行けば良いのか迷ってしまいますよね。この記事では、京都出身のワゴコロ編集部員が厳選した、『京都のオススメ紅葉スポット20選』を各スポットの特徴とともにご紹介します!
12月の京都のお祭り・行事・イベント

12月の京都オススメのスポット21選!伝統行事・イベント・観光・グルメ・ライトアップや、東福寺の看楓特別拝観、終い天神・終い弘法、空也踊躍念仏、知恩院の除夜の鐘、八坂神社のをけら詣り、宇治の平等院、千枚漬け、ぼたん鍋、伊根の寒ブリなど、年末の京都をご堪能ください♪
大 根焚き
無病息災を祈願して京都のさまざまな寺院で行われる大根炊きは、京都の冬の風物詩として広く親しまれています。
大根焚き(千本釈迦堂 大報恩寺)
お釈迦様が悟りを開いたとされる12月8日を記念し、法要の度に四本の大根を縦半分に切り、切り口に釈迦の梵字を書いて供え、参詣者へ悪魔除けとしたことから、境内で大根炊きが振る舞われたことがはじまりといわれています。
開催日:12月7日~12月8日

日本各地には、地域の民俗や風土に合わせた、さまざまなお祭りや行事が伝えられてきました。特に、1年の締めくくりに当たる年末の12月は、新年を迎える準備を進めるため、伝統的な行事が数多く行われます。今回は、ワゴコロ編集部がオススメする12月に催される全国の伝統行事18選をお届けします!
京 都・嵐山花灯路
3月の行事でもご紹介した花灯路。
3月は東山、12月には嵐山で開催されます。
美しい自然景観や歴史的文化遺産が広がる嵯峨・嵐山地域の散策路に、露地行灯の灯りといけばなの作品が演出された美しく幻想的な空間が広がる季節イベントです。
周辺の寺院や文化施設にてライトアップや特別拝観なども行われ、冬のはじまりに華を添えます。
開催日:12月13日~12月22日

日本各地には、地域の民俗や風土に合わせた、さまざまなお祭りや行事が伝えられてきました。特に、1年の締めくくりに当たる年末の12月は、新年を迎える準備を進めるため、伝統的な行事が数多く行われます。今回は、ワゴコロ編集部がオススメする12月に催される全国の伝統行事18選をお届けします!
おわりに
古式ゆかしい装束に身をつつんだ神職による厳粛な神事から、美しい芸舞妓さんによる華やかな演舞、地元の人たちによって時代をこえて受け継がれてきた伝統的なお祭りまで、京都には多様な行事がたくさんあります。
1年を通してさまざまなお祭りが行われている京都。
あなたもぜひ、満喫してみてはいかがでしょうか?

京都最強の縁切り神社と名高い「安井金比羅宮」など、京都の縁切り神社・お寺・スポットをご紹介します。人間関係や男女関係、病気などの悪縁を断ち、良縁を結びましょう。

女の子なら一度は舞妓さんに憧れるかもしれません。
しかし実際に舞妓になるには、厳しいお稽古だけでなく年齢の制限もあります。
1日だけでも舞妓さんになってみたい!という方にオススメなのが「舞妓体験」です!
京都には、舞妓さんと同じメイクをして、同じ着物を着られる体験ができるお店が多くあります。

四季折々の要素が盛り込まれた美しい形と繊細な色合い、上品な味わいで人気の京都の和菓子。長いこと都であったという歴史と立地などの条件が、京都の菓子文化を発展させてきました。

旧暦の和風月名で6月は「水無月」ですが、京都では行事食として有名な和菓子の名前でもあります。一年中売っている店もありますが、多くの店では6月に入ってから店先に並びます。6月30日の夏越の祓はらえに欠かせないものとなっています。

京都市北西部の一帯を指す「西陣」は、日本だけでなく世界でも織物の産地として知られています。
「染の着物に織りの帯」という言葉がありますが、織りの帯でも品格が高いといわれているのが西陣織の帯です。
そんな日本を代表する織物である西陣織とはどんなものなのか、その魅力や特徴をご紹介します!

京友禅とは、江戸時代前期に宮崎友禅が奈良時代頃から伝わる染色技法を元にして考案し、京都で発展し生産されてきた伝統ある模様染めのことです。華やかで優雅な絵柄で染められる京友禅は、世界からも評価される日本の伝統的工芸品です。この記事では、京友禅の歴史や特徴、魅力、そしてその制作工程について詳しくご紹介していきます。

清水寺をはじめとする歴史ある寺社仏閣、庭園、史跡が点在する京都府では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた80品目以上の伝統工芸品が存在します。経済産業大臣によって京都府の「伝統的工芸品」として指定されている西陣織、京鹿の子絞、京仏具、京仏壇、京漆器、京友禅、京指物、京焼・清水焼、など17品目をご紹介します。

地蔵盆とは、主に京都を中心とした近畿地方で行われている子供が主役のお盆です。
京都では“京都をつなぐ無形文化遺産”に選ばれていますが、地蔵盆は関西以外ではあまり知られていないのが現状です。
この記事では、地蔵盆とは何をする日なのか、地蔵盆の意味や歴史、いつ頃どのように行われているのかをまとめました。

この記事では、日本の有名なお祭りを、北から南まで地域別に25個ピックアップしてご紹介します。日本では古くから、五穀豊穣や家内安全などを祈願し、神様に感謝するさまざまな祭りが行われています。どの祭りも、その地域ならではの由来・特色があるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね!







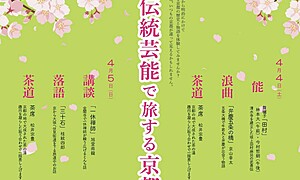

























![[PR]【大分県】別府竹細工の旅~温泉だけじゃない!別府の魅力をレポート~](/uploads/article/image/1101/eyecatch_96e1c509-6186-4da4-98ca-e6a5e5b3534f.jpeg)

















