
1月は、全国各地で年の始まりを祝う伝統行事が多く催されます。
「とんど」「左義長」または「道祖神(どうそしん)まつり」と呼ばれる正月の火祭りをはじめ、裸参り、福を呼ぶうそ替(かえ)神事、さらにだるま市やランタンフェスティバルなど、ワゴコロ編集部がオススメする1月の代表的な行事20選を紹介します♪
だるま市
高 崎だるま市(群馬県高崎市)
顔におめでたい鶴と亀が描かれていることから“縁起だるま”・“福だるま”とも呼ばれる高崎だるま。
『1年の恵は高崎にあり』とうたい、年の初めに高崎駅西口駅前通りで「高崎だるま市」が開催されます。
大小さまざまなだるまやカラフルなだるま販売のほか、3m近くの特大高崎だるまや地元のうまいもんを集めた“開運たかさき食堂”、各種ステージなど見どころが目白押し!
見て、食べて、買って、楽しめるイベントです♪
このだるま市は平成29年(2017年)から始まった新しいイベントですが、高崎市のだるま市自体は300年以上の歴史があります。
もともとは、高崎市内のだるま市は縁起だるま発祥の地である「少林山達磨寺」で開かれていました。
しかし達磨寺と露天商が経費負担などで対立し、露天商と達磨製造協同組合は市の協力のもと、駅前広場でだるま市を開催することに。
それが、現在の高崎だるま市です。
ちなみに、達磨寺では「少林山七草大祭だるま市」という名前で1月6日と7日にだるま市を開催しています。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
その他のだるま市(関東)
だるま市は関東各地で開催されますので、近くまでお立ち寄りの際はチェックしてみてください♪
1月3日:【埼玉県川越市】川越大師 喜多院の「初大師 だるま市」
1月6日・7日:【群馬県高崎市】少林山達磨寺の「七草大祭だるま市」
1月9日:【群馬県前橋市】「前橋初市まつり」
1月12日:【東京都青梅市】「青梅だるま市」
※開催予定・詳細などは公式サイトをご確認ください。
毘 沙門天大祭だるま市 (静岡県富士市)
静岡県富士市の妙法寺(富士毘沙門天)で3日間にわたり開催される「毘沙門天大祭だるま市」は、日本三大だるま市の一つに数えられています。
このだるま市は、期間中、毘沙門天王が人々の願いを聞いてくれるという毘沙門天大祭に、富士市の特産品である紙の端で作った達磨を売り出したのが始まりです。
JR・吉原駅から1㎞沿いに露店が連なり、『東海一の高市』と呼ばれるほど賑わいます。
境内には富士市の“鈴川だるま”はもちろん“高崎だるま”など全国から集まったカラフルなだるまがあふれかえっています。
縁起物のだるまと毘沙門天大祭を楽しんでみてはいかがでしょうか。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
だるま市でお気に入りのだるまを購入したら、下記の記事を参考に“目入れ”をしてみましょう♪

手足のない丸い体と、ヒゲをたくわえた凛々しい表情が特徴の「だるま」。
年の瀬から新年にかけて買い求め、厄除けのために飾るのが一般的です。
また、だるまは大願成就の縁起物としても親しまれ、願掛けしながら片方の目を入れ、願いが叶ったらもう一つの目を入れることでも知られています。
早池峰神楽(岩手県花巻市)
「早池峰神楽」とは、岩手県花巻市の“岳神楽”と“大償神楽”という2つの神楽の総称です。
山伏の祈祷の舞を起源とする500年以上の伝統を持つ神楽で、平成21年(2009年)にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。
毎年新年のお祝いとして、1月2日には“神楽の館”で大償神楽、翌3日には“早池峰神社”で岳神楽の舞初めが催されます。
大償神楽は優雅で繊細な舞、岳神楽は力強く勇壮な舞に見えるとされるため、2つの違いを見比べてみるのも面白いですよ。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
早池峰神楽について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

早池峰神楽は、岩手県花巻市大迫町の大償と岳という2つの神楽座に伝承されている神楽を演じる民俗芸能のことです。早池峰神楽は大変希少性の高い民俗芸能であることから平成21年(2009年)にユネスコの無形文化遺産に登録されました。今回は、早池峰神楽についてご紹介します。

ユネスコは、国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)のことです。本記事では、日本で登録されているユネスコ無形文化遺産を一覧でご紹介します。
追儺祭(神奈川県高座郡寒川町)
「追儺祭」は“鬼はらい”とも呼ばれる災厄を祓う神事で、神奈川県寒川町の寒川神社では、江戸時代から行われてきました。
午後8時、境内の灯を消した暗闇の中を、兜、太刀などを持った神職たちが“難波の小池”と唱えながら太鼓の音とともに粛々と境内を練り歩きます。
難波の小池から汲んだ御神水を境内の2か所に撒いて、神職は“宝物かぞえ”と呼ばれる唱和を唱え除厄を祈願。
供えられた弓矢は災難よけとして参拝者に授与される、厳かで神秘的な神事です。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
てんてこ祭り(愛知県西尾市)
「てんてこ祭り」は、愛知県西尾市の熱池八幡社で五穀豊穣を祈念し行われるお祭りです。
平安時代、天皇即位後初めて実った米を供える神事(大嘗会/大嘗祭)の悠紀斎田の土地に選ばれたことちなんだ1100年近く続く伝統のお祭りですが、その内容はとてもユニーク!
赤い衣装をまとった厄男たちが大根で作った男性のシンボルを腰にぶら下げ、『てんてこ、てん』という太鼓の囃子に合わせて腰を振りながら練り歩く奇祭です!!!
神社に到着後、厄男が竹箒で藁灰を威勢よくまき散らします。
この灰をかぶると厄除けになるとされているので、ぜひ灰まみれになってみてください♪
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
以下の記事では、てんてこ祭りの起因となった大嘗祭や斎田に関して取り上げています。
併せて読むと一層、てんてこ祭りへの理解が深まりますよ♪

皇室へ献上されるお米「献上米」をご存じですか?献上米とは、毎年11月23日(勤労感謝の日)に皇居で行われる重要な儀式「新嘗祭」に献穀米として献上するお米のことです。本記事では、献上米について解説します。
玉せせり/玉取祭(福岡県福岡市東区)
福岡市の筥崎宮では正月3日、室町時代から始まったとされる「玉取祭(別名・玉せせり)」が行われます。
これは陸組と浜組に分かれた締め込み姿の男衆が、触れると幸運が訪れるといわれる木製の玉(重さ8kg)を末社である玉取恵比寿神社から本社に運びつつ、激しく奪い合う勇壮な神事です。
神職に玉を渡した組の願い(豊作、豊漁)が叶う占い神事であるため、争奪戦は肩車をして激しくもみあうなど白熱し、観客の声援も高まります!
寒い冬に参加者、見物客ともに熱くなるお祭りです♪
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
七日堂裸詣り(福島県河沼郡柳津町)
七日堂裸詣りは、“赤べこ発祥の地”とも伝わる福島県柳津町の圓藏寺で行なわれる、勇ましい裸祭りです!
その昔、玉を奪い返しに来た龍神を民衆たちが団結して追い払ったという伝説に由来する、1000年以上の歴史を誇る伝統行事です。
大鐘の音を合図に、褌姿の男たちが圓藏寺を目指して113段の石段を駆けのぼり、本堂内にある大鰐口の長さ4.8mもある巨大な綱を我先にとよじ登ります。
綱に飛び乗り登る者、力尽きて落下する者など男たちの力強い熱気に魅了される、見ているだけでも楽しい賑やかなお祭りです♪
男性の一般参加も可能なので、「我こそは!」と思う方はぜひ参加してみては?
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
開門神事&福男選び(兵庫県西宮市)
福を授けるえびす神の総本社である西宮神社では、1月9日~11日に大祭・“十日えびす”が執り行われます。
そのハイライトが10日(本えびす)の「開門神事」と「福男選び」です。
早朝6時の開門と同時に人々が表大門から飛び出し、本殿への一番乗りを目指して約230mを全速力で駆け抜けていきます!
3着までが“福男”と呼ばれ、1年の福を授かるといわれています。
このお祭りは9日(宵えびす)の夜に、大祭に向けて身を清めるため閉門(忌籠神事)し、翌十日えびすの朝、参拝一番乗りを目指し“走り参り”をしたことから発展したお祭りです。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
1月20日には関東でも、えびす様をお祀りする行事「えびす講」が行われます。
意外と知らない七福神などについても説明しているので、ぜひご覧くださいね。

「えびす講」とは、七福神の一人で商売繁盛の神・えびす様をお祀まつりする行事のことです。関西では1月10日に、関東では10月20日・1月20日に行われることが多いです。今回は、えびす講の意味や時期、えびす講では何が行われているのか、意外と知らない七福神などについて簡単に説明します。
墨つけとんど(島根県松江市)
しめ飾りや書初めなどを焼く正月行事の“とんど”。
島根半島の漁師町・片江地区で約250年続く「墨つけとんど」は、紙ではなく、顔に墨を塗るというユニークなお祭りです♪
約20mのとんどが立てられ、神輿が街を練り歩く際、女性たちが墨を道行く人の顔に次々と塗りつけていきます。
墨を塗られると風邪をひかず、海難除けになるという魔よけのおまじないで、多くつくほどご利益があるのだとか。
お互い真っ黒に塗られた顔を見て、見物客ともども地域は笑い声に包まれます!
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
ホーランエンヤ(大分県豊後高田市)
「ホーランエンヤ」は、大漁と航海の安全を祈る新年の伝統行事です。
大分県豊後高田市では、宝来船に乗り込んだ男たちが「ホーランエンヤ エンヤサノサッサ」と掛け声とともに、若宮八幡宮を目指し桂川を漕ぎ上ります。
その途中、川岸の観衆が祝儀を差し出すと、それを受取ろうと漕ぎ手が冷たい川に飛び込んでいく姿に驚かされます。
極寒の川を泳ぐ海の男の豪快な姿は見逃せません!
また、船から撒かれる餅を巡り、観衆も盛り上がります♪
江戸時代に年貢米を運ぶ船の航海安全を祈り始まった行事で、県の選択無形民俗文化財※に指定されています。
※選択無形民族文化財:「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」の通称で、国(文化庁長官)が選択する文化財のこと。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
寒中みそぎ祭り&寒中みそぎフェスティバル(北海道上磯郡木古内町)
「寒中みそぎ祭り」は、北海道木古内町の左女川神社で天保2年(1831年)から続く神事です。
1月13日から4人の若者が神社に籠り、冷水で身を清める鍛錬を重ね、15日に御神体を抱いて津軽海峡に飛び込み、豊作豊漁を祈願します。
厳冬の海峡で沐浴する若者の姿は崇高で、彼らが立てる水しぶきを浴びると無病息災のご利益があるといわれています!
期間中はちょうちん行列やステージ、グルメなど一般参加型のフェスティバルが開催されているのも楽しみの一つ♪
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
鳥追い祭り(群馬県吾妻郡中之条町)
群馬県中之条町の「鳥追い祭り」は、田畑の作物を荒らす害鳥を追い払い、豊作と厄除け、家内安全を祈るお祭りです。
400年近い伝統があり、県の重要無形民俗文化財に指定されています。
鳥追い祭りのハイライトは、直径1m以上もある大太鼓や小太鼓を乗せた山車が登場する“鳥追い太鼓”。
太鼓の音を雷のように響かせながら、『追い申せ、追い申せ、唐土の鳥を追い申せ』という掛け声とともに町を練り歩くさまは迫力満点です。
観客も太鼓を叩いたり、厄年の人や店からくじ付きのミカンが投げられるなど、参加して楽しむことができますよ♪
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
道祖神祭り(長野県下高井郡野沢温泉村)
長野県・野沢温泉の「道祖神※祭り」は日本を代表する道祖神行事の一つで、日本三大火祭りにも数えられます。
約300年前から五穀豊穣と安産、無病息災などを祈願して行なわれており、国の重要無形民俗文化財にも指定されました。
祭りのクライマックスは、15日の夜に10数mの高さの社殿に火をつける点火役と、それを防ごうとする厄年の人たちによる防火役の攻防戦!
男たちが火のついた松明や松の枝で叩き合う気迫ある姿は壮絶で、フィナーレの社殿炎上では吹きあがる火柱に圧倒されます。
※道祖神:地域の守り神のこと。道祖神祭りは“とんど祭り”とも呼ばれる
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
三十三間堂 通し矢(京都府京都市東山区)
「三十三間堂の通し矢」は、新成人や弓の有段者たちが京都・三十三間堂で弓の腕を競う京都新春の風物詩です!
江戸時代に軒下の端から端に射通した通し矢にちなんだ競技で、ここでは弓を的に当て、決勝では的中者が最後の1人となるまで射ていきます。
カラフルな振袖袴姿に身を包んだ新成人たちが凛々しく弓を引く姿は、新春にふさわしい光景です。
この日は三十三間堂が無料公開され、通し矢も見学可能なため、この機会にぜひ寺院に足を運んでみては?
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
大磯の左義長(神奈川県中郡大磯町)
神奈川県の「大磯の左義長」は、地域の守護神・セエノカミサン(道祖神)に息災などを願う火祭りです。
メインは高さ約8mの9つの斎灯が一斉に燃やされる“セエトバレエ”で、夜空を焦がす炎の嵐は圧巻!
この火で団子を焼いて食べると、風邪をひかないともいわれています。
続いて、裸の男衆が豊漁を願い海中と浜辺に分かれて綱を引きあう「ヤンナゴッコ」は、勇ましく見応え抜群です♪
「大磯の左義長」は、道祖神巡拝、御仮屋で子どもが神様と遊ぶ風習なども含め、国の重要無形民俗文化財となっています。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
船だんじり(三重県北牟婁郡紀北町)
三重県紀北町の長島地区で行なわれる「船だんじり」は、江戸時代から続く豊漁を願う行事です。
色鮮やかなカツオ船を模した山車に法被姿の子供たちが乗りこみ、竿を巧みに操ってカツオの一本釣りの様子を再現します。
時には餌に見立てた福飴をまきながら、長島港から長島神社まで勢いよく練り歩き、長島神社に到着すると餅まきも行われますよ♪
風情豊かな漁師町に『チョーサヤ』という威勢のいい掛け声が響き、飴や餅など見物客とも福を分け合うお祭りです!
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
ヘトマト(長崎県五島市下崎山町)
「ヘトマト」は長崎県五島市下崎山地区に伝わる子孫繁栄や大漁、豊作を祈る、国指定重要無形民俗文化財に指定されている行事です。
奉納相撲に始まり、新婚女性の羽付き、スス(ヘグラ)をつけた若者が藁玉を奪い合う“玉せせり”や“綱引き”など複数の催し物で盛り上がります♪
ハイライトは長さ3m、重さ300kgという大草履の奉納です!
大草履を担ぐ若者たちが、沿道の女性を草履に乗せて『ワッショイ、ワッショイ』と胴上げすると、お祭りの熱気も最高潮に。
観客もヘグラを塗りつけられ、一体となれるお祭りです。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
ランタンフェスティバル(長崎県長崎市)

写真提供:(一社)長崎県観光連盟
長崎の冬の名物でもある「ランタンフェスティバル」の期間中、市内中心部は約1万5000個にも及ぶ極彩色のランタン(中国提灯)や大型オブジェに彩られ、幻想的な雰囲気に包まれます♡
このお祭りは、平成6年(1994年)に長崎新地中華街の人々が行っていた“春節祭(中国の旧正月を祝う行事)”を発展させた形で始まりました。
そのため、期間中は雑技や龍踊りなどのステージや皇帝パレードなど、中国風の異国情緒溢れるイベントが満載です♪
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
長崎ランタンフェスティバルでは、沖縄の伝統芸能“エイサー”も振る舞われるのだとか。
エイサーの記事を読んで理解を深めておけば、よりフェスティバルを楽しめること間違いなしです!

「エイサー」とは、沖縄全島と鹿児島県の奄美大島に伝わる伝統芸能の一つで、踊りながら地域内を練り歩く、いわゆる盆踊りです。ですが一言にエイサーと言っても、地域ごとに曲や型、衣装などが異なります。この記事では、沖縄の伝統芸能・エイサーの歴史や魅力、注目するとより楽しくなる見所、イベント情報をご紹介します♪
鷽替え神事(東京)
「鷽替え神事」は、主に天満宮系列の神社で行われる神事。
鷽の木彫りを取り(鳥)換えることで、前年の凶を嘘にして吉を招くという嬉しいお祭りです。
ここでは東京都江東区・亀戸天神社の神事を紹介します。
う そ替え神事(東京都江東区:亀戸天神社)
「うそ替え神事」は江戸時代に始まり、多くの人が集まってお互いに鷽鳥を交換しあうものですが、東京の亀戸天神社では鷽の木彫り人形を神社に納めて、新しい鷽を持ち帰ります。
ヒノキを使って神職が一つずつ心を込めて作った木彫りは愛嬌があり、この日にしか手に入らない開運のお守りを手に入れようと各地から参拝客が訪れます!
東京では湯島天神、上野五條天神などでもこの神事が行われています♪
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
そ の他の鷽替え神事(全国)
鷽替え・鬼すべ神事 太宰府天満宮(福岡県太宰府市)
太宰府天満宮でも「鷽替え神事」が行なわれ、参加者同士が『替えましょ、替えましょ』の掛け声の下、木彫りの鷽を交換します♪
同日に「鬼すべ神事」と呼ばれる火祭りも行なわれますよ。
開催日:毎年1月7日
鷽替え神事はこのほか、千葉県の千葉神社、愛知県名古屋市の山田天満宮、大阪の大阪天満宮や道明寺天満宮など1月25日を中心に各地で行われます。
神社によって木彫りの鷽のデザインが異なるのも面白いですね♡
気になる神社へ出かけて、悪い出来事を嘘にして、今年の幸運を呼び込みませんか?
若草山焼き(奈良県奈良市)
奈良の早春を彩る行事である「若草山焼き」の行事。
各種行事や鮮やかな花火に続いて、若草山に点火されると、山全体が赤々と燃え上がり、冬の夜空を焦がす壮大な情景に圧倒されます!!!
山焼きは市内各地から眺められますが、“若草山麓”から見ればダイナミックな臨場感を体感できますよ。
山焼きの起源は幽霊封じや先人の鎮魂説、環境を維持するための野焼き説など諸説あり、江戸時代にはすでに行われていましたが、明治時代に観光行事となりました。
情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。
おわりに
1月の全国の伝統行事を紹介しました。
1月は正月や小正月(15日)にまつわる行事が多く、それらは1年の吉を祈ったり、占ったり、年の初めにふさわしい内容ばかりです♪
1年の幸運やパワーをもらいに、気になる行事に出かけてみませんか?

お正月とは、実はいつまでと言い切ることはできず、1月いっぱいを正月と呼ぶこともあれば、門松を飾っておく期間(=松の内)を正月と呼ぶこともあり、考え方は地域によって異なります。この記事では、お正月とはどのようなものか、その意味と由来や、お正月の期間について、飾りや食べ物などお正月に関する基本的な知識を紹介します。

皆さんのお家では、お正月に自宅の神棚や玄関、床の間などに鏡餅を飾っていますか?お餅といえば昔は高級品であり、特におめでたい「ハレの日」に食べられていました。そんな、ハレの日の一つでもあるお正月に食べられるのが鏡餅。

2月といえば寒い時期ですが、正月の関連行事や冬ならではの雪まつり、立春に向けた節分祭など、さまざまな行事があります。心が高まるバレンタインも楽しみの一つでしょう♡今回は、ワゴコロ編集部がオススメする令和5年(2023年)2月の全国の伝統行事やイベントをご紹介します。

日本各地には、地域の民俗や風土に合わせた、さまざまなお祭りや行事が伝えられてきました。特に、1年の締めくくりに当たる年末の12月は、新年を迎える準備を進めるため、伝統的な行事が数多く行われます。今回は、ワゴコロ編集部がオススメする12月に催される全国の伝統行事18選をお届けします!

日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。

日本の年中行事は、長い歴史と伝統の中から生まれ、古くから現在まで変わることなく大切に守り伝えられてきた日本の財産です。各行事の歴史や意味、その特徴や楽しみ方を知ることで、より深い魅力を感じることができます。

ユネスコは、国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)のことです。本記事では、日本で登録されているユネスコ無形文化遺産を一覧でご紹介します。

長い歴史と伝統が息づく古都・京都には、世界的にも名の知れた有名なお祭りから地元の人達によって大切に受け継がれている年中行事まで、さまざまなイベントが1年を通して行われています。そこで今回は、京都で一度は見に行きたいお祭り・行事・イベントを一覧でご紹介します♪

世界屈指の温泉大国である日本には、古くから多くの人々に愛されてきた魅力的な温泉地がたくさんあります。地元の温泉で日頃の疲れを癒すのも最高ですが、たまには全国各地の温泉へも足を運んでみませんか?今回は、全国のオススメ温泉地を厳選してランキングでご紹介します♪

戦国時代から江戸時代にかけて、武将たちが居住し、戦闘のための要塞でもあった日本のお城。武将たちが実用的な機能と美観を両立するべく精魂注いだお城は、今では日本を代表する観光スポットとして人気を集めています。ここではそんな数多く残る日本の城のなかから、一度は訪れたい名城をランキング形式で15城ご紹介します!

京都最強の「安井金毘羅宮」、東京で有名な「豊川稲荷東京別院」など、全国から選りすぐりの“悪縁”をバッサリ切ってくれると話題の縁切り神社・お寺を20選ご紹介!人との縁以外にも、病気との縁、煙草やアルコールといった辞めたくても辞められない縁などの縁切りにも効果的ですので、ぜひ参考にしてみてください。







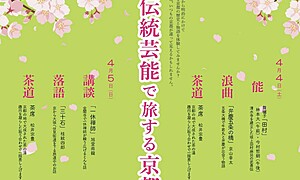

























![[PR]【大分県】別府竹細工の旅~温泉だけじゃない!別府の魅力をレポート~](/uploads/article/image/1101/eyecatch_96e1c509-6186-4da4-98ca-e6a5e5b3534f.jpeg)

















