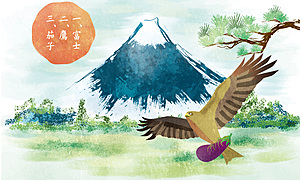「えびす講」といっても、聞きなれない人も多いでしょう。
れっきとした日本の季節行事なのですが、盛んでない地域もあるので無理もありません。
特に若い人たちは、初めて聞く言葉かもしれませんね。
そこで今回は、えびす講の意味や時期、えびす講では何が行われているのか、意外と知らない七福神などについて簡単に説明していきます。
えびす講とは?意味や由来
えびす講とは、七福神の一人・えびす様をお祀りする行事のことです。
えびす様といえば烏帽子を被り、右手には釣り竿、左手には鯛を抱えた姿でおなじみの「商売繁盛」の神様ですね。

え びす講はいつ行われる?
えびす様はもともと漁民の神様で、海運守護や豊漁といったご利益があるとされていました。
ところが、商家では商売繁盛の神、農村でも豊穣の神として信仰されるようになったのです。
みんなにとって“ありがたい”えびす様をお祀りするのが、えびす講というわけですね。
全国的に行われているえびす講ですが、地域によって日程は大きく異なっています。
全国的に行われているえびす講ですが、1月の10日や20日に開催される地域、10月20日や11月20日に開催される地域など、地域によって日程は大きく異なっています。
主に関西では1月10日に行われることが多く、「十日戎」と呼びます。
一方、主に関東を含む東日本では、1月20日・10月20日に行う地域が多いため、「二十日戎」と呼ばれることもあります。
神 無月との関係
旧暦10月は神無月です。
神無月とえびす講、一見関係ないように見える両者には、意外な関係があるともいわれています。
神無月の語源は、全国の神様たちが出雲大社に集まって話し合いをする月なので、各地で神様が不在になるからといわれています(諸説あり)。
反対に出雲では、旧暦10月のことを神在月と呼びます。
えびす様も神様の一人、当然旧暦の10月には出雲へ出かけるのでしょう……と思いきや、何故かえびす様だけは、各地に居残るのだそうです。
他の神様から置いてきぼりをくらったえびす様を慰めようとして始まったのが、えびす講の起源といわれることもあります。
えびす講には、いろいろな書き方があります。
多すぎるので、今回の記事では「えびす講」で統一しています。
■ 恵比須講
■ 恵比寿講
■ 夷講
■ 蛭講
■ 戎講
えびす講では何をするの?
具体的にえびす講では、どんなことが行われているのでしょうか。
地域によってさまざまですが、お参りへ行ったり、お供え物をしたりするのが一般的といわれています。
え びす様をお祀りする神社にお参りへ行く
昔から商家には、えびす様をお祀りする神社にお参りをして、商売繁盛を願う風習があります。
神社の参道には、熊手や福笹(下記で詳しく)といった縁起物を売る店が並びます。
おもしろいのが、えびす講の日に京都で行われる「誓文払い」です。
四条寺町の冠者殿にお参りすると、商いをするうえでやむなくついたウソなどの罪を祓えるとされています。
商売の大変さが伝わりますね。
他にも商工会議所などが「えびす講祭り」を盛大に催し、花火が打ち上げられるところもあります。
特に長野えびす講煙火大会は、ツアーが組まれるほど有名です。
お 供え物をする
神棚にお供え物をするのも、昔からの風習です。
お供えするのは食べ物やお酒、縁起物などです。
また、鮒など生きた魚をお供えする風習もあります。
食べ物は地域や家庭によって異なりますが、えびす様にちなんで鯛をお供えすることもあります。
他にも、その土地の旬の食べ物(サンマ・柿・栗・大根など)をお供えするのが一般的です。

【左】熊手【右】福笹
えびす講の縁起物といえば、熊手や福笹(福笹飾り)が有名です。
熊手は竹製で先端がつめ状になった道具に、宝船や大判・小判などを取り付けたものです。
福をかき集めるという意味で縁起がよいとされています。
一方福笹は、笹に俵や判・小判などを取り付けたものです。
まっすぐ伸びる笹も、縁起がよいのだとか。
これらの縁起物をお供えして、毎年取り換えるようにすれば、福が来るそうですよ。
えびす講の食べ物
えびす講では、特定の行事食というものはないといわれています。
お供え物と同様、地域や家庭によって異なります。
そこで、各地にみられる興味深い食べ物について紹介します。
笹 に小判
京都ではえびす講の日、「笹に小判」が食べられています。
その正体は九条ねぎとはんぺい(はんぺん)の汁物。
福笹に見立てて作られた、縁起のよい料理です。
京都の商人はお参りの後、笹に小判を食べて縁起を担ぐのだとか。
べ ったら漬け

べったら漬けとは、甘みのある大根の浅漬けのことです。
江戸時代、日本橋のえびす講で誕生したといわれています。
偶然売られていたべったら漬けでしたが、えびす講に関連する品を売っていたはずの市が、やがて「べったら市」と呼ばれるほど評判になりました。
現在でも宝田恵比寿神社を中心として、10月19・20日に「日本橋恵比寿講べったら市」が開催されています。
えびす講と七福神の関係

えびす様は七福神の一人であるということはご説明しました。
お正月には七福神モチーフの置物を飾ったり、七福神巡りをしたり……日本人にとって身近な存在にもかかわらず、実はよく知らない七福神。
というわけで、最後に七福神について簡単に説明していきます。
恵 比須神
七福神とは、福をもたらしてくれる神様のグループのこと。
意外にも、ほとんどが外国出身の神様なのです。
唯一日本を起源とするのは、えびす様こと恵比須神だけ。
日本神話に出て来る、イザナギノミコトとイザナミノミコトが最初に生んだ蛭子神とされています。
上述の通り、もとは漁民の神様でしたが、商家や農村にも信仰が広まっていきました。
大 黒天
大黒さまとしておなじみの大黒天
頭巾を被り、右手には小槌、左手には袋を持ち、米俵に乗っている姿が特徴的ですね。
実はインドのヒンドゥー教由来の神様で、日本に入ってくると大国主神と結びつきました。
豊穣の神とされています。
毘 沙門天
毘沙門天もヒンドゥー教由来の神様です。
もとは「クベーラ」という武神で、仏教に取り入れられてからは四天王の一人になりました。
戦国武将の上杉謙信が、自身を毘沙門天の生まれ変わりと信じていたエピソードも有名です。
福徳や財宝の神様とされています。
弁 財天
七福神唯一の女神・弁財天(弁才天)も、ヒンドゥー教出身です。
もとは「サラスヴァティー」という川の神様でした。
琵琶を弾いているのが特徴的ですね。
芸術・音楽・学問・財などの神様とされています。
福 禄寿
福禄寿は、中国の道教に由来する神様です。
南極星の化身ともいわれています。
背が低く、長い頭・ヒゲを持つ福禄寿は、幸福・富貴・長寿の徳を持っています。
ややこしいのですが、寿老人と混同される場合もあります。
寿 老人
寿老人も道教由来の神様です。
先ほども書きましたが、福禄寿の異名の神様といわれることもあります。
健康・福徳・長寿の神様です。
布 袋
布袋はなんと、実在した人物に由来する神様です。
もとは中国の後梁時代の禅僧といわれています。
実際に杖と袋を持ち歩いていたことから、神様となってもそのように描かれているようです。
良縁・夫婦円満・子宝の神様です。
おわりに
お参りに行ったり、神棚にお供え物をしたりするなど、家庭でも簡単にできるえびす講。
今までご存じなかったという方も、季節を感じられる行事として、生活の中に取り入れてみるのもいいかもしれません。
例えばえびす講の日に、いつもは食べられない高級料理をお供えしてみるというのはどうでしょう。
きっと、えびす様も喜んでくれるはずです。
お供えした後は、おいしくいただきましょう!

日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。

酉の市とは、商売繁盛を願い毎年11月の酉の日に行われるお祭りです。今回は酉の市とは何か、その由来や歴史、楽しみ方に熊手の意味、有名な酉の市(新宿・浅草・横浜など)について、わかりやすく説明していきます!

みなさんは二十四節気という言葉を聞いたことがあるでしょうか?二十四節気とは、太陽の黄道上の視位置を24に等分しているもののことを指します。この24等分の一つに「冬至」があります。この記事では、冬至はいつなのか、かぼちゃとの関係や冬至にするといいことについてご紹介します。

縁結びで有名な出雲大社。そんな出雲大社は最強のパワースポットとしても有名で、一生に一度は必ず訪れていただきたい神社の一つです!この記事では、出雲大社の歴史や神話、縁結びの由来、国宝などの文化財や参拝方法に加え、出雲大社周辺の観光情報についてご紹介します♪

1月は、全国各地で年の始まりを祝う伝統行事が多く催されます。「とんど」「左義長」または「道祖神まつり」と呼ばれる正月の火祭りをはじめ、裸参り、福を呼ぶうそ替(かえ)神事、さらにだるま市やランタンフェスティバルなど、ワゴコロ編集部がオススメする1月の代表的な行事19選を紹介します♪