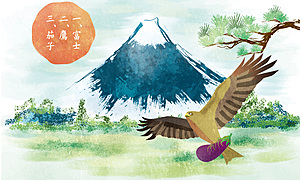近年、日本の入浴剤市場が伸びているのをご存知でしょうか?
疲労回復・肩こり・冷え性・肌荒れ…など、さまざまな効能を持った入浴剤が次々と登場しています。
入浴に関心が高まる中、改めて注目したいのが【菖蒲湯】です。
菖蒲湯は、日本人が昔から入ってきた天然の入浴剤といえるでしょう。
こちらの記事では、菖蒲湯とは何か、効能や作り方などについてわかりやすくご紹介していきます!
菖蒲湯とは

菖蒲湯とは、植物の菖蒲を入れて沸かすお風呂のことです。
冬至(12月22日頃)にゆずの実を入れて沸かす「ゆず湯」と並び、日本ではメジャーな薬湯※です。
では、菖蒲湯はいつ入るものなのでしょうか。
※薬湯:薬草を入れたお風呂
菖 蒲湯はいつ入る?
伝統的に菖蒲湯に入るのは5月5日、いわゆる「端午の節句」に入ります。
ゆず湯は冬至に入るので、菖蒲湯は夏至(6月21日頃)に入るもの、と勘違いされている方もいるようですが、これは間違いです。
また、端午の節句といえば、男の子のお祭りですね。
男の子のいる家庭では、鯉のぼりをあげたり、五月人形を飾ったりして、子供の健やかな成長を願います。
そういうこともあってか、“菖蒲湯=男の子が入るもの”と考えている方も多いようです。
ですが、菖蒲湯には女の子も大人も入って大丈夫!
後ほど説明しますが、菖蒲湯には効能があるので、むしろ積極的に入っていただきたいです♪

ゴールデンウイークももう終わり……、憂鬱な気分になる人も多いのではないでしょうか。しかし、そんな時期に子どもの一大イベント「子どもの日」があります。「端午の節句」とも言いますよね。今回は意外と知らない、端午の節句にまつわる知識についてご紹介していきます。
端 午の節句(こどもの日)に菖蒲湯に入るようになった由来
少なくとも室町時代にはあったとされる、菖蒲湯に入る風習。
なぜ端午の節句になると、菖蒲湯に入るのでしょうか?
日本の端午の節句は、古代中国の影響を大きく受けており、菖蒲湯の由来も古代中国からきているとされています。
中国では端午の節句になると、「蘭湯」に入る風習がありました。
蘭湯とは、肩こり・神経痛・皮膚のかゆみなどに効果があるといわれている蘭草の葉を入れて沸かすお風呂のことです。
旧暦の5月は伝染病の流行や害虫被害などが多く、古代中国の人々は邪気払いのために蘭湯に入ったといいます。
この風習が日本にも伝わったものの、日本には肝心の蘭草が少ないという問題がありました。
そこで蘭草の代用となったのが、日本人にとって身近な菖蒲だったのです!
独特な強い香りを持つ菖蒲は、厄除けや清める力があると古くから信じられてきた植物。
古代中国の端午の節句でも、蘭草のほかに菖蒲やヨモギを用いて邪気払いをしていました。
本来は蘭湯だった菖蒲湯。
もし日本にも蘭草が多ければ、存在しなかったかもしれませんね。
菖蒲湯の効能
菖蒲には多くの効能が認められています。
乾燥させた菖蒲の根茎は、生薬にもなっているほど。
菖蒲には厄除けの力がある、というのはただの迷信ではなかったのです。
菖 蒲の力はこんなにすごい!
菖蒲にはテルペンやアザロン、オイゲノールといった成分が含まれています。
これらの成分を皮膚や呼吸器から吸収すると、疲労回復・精神安定・リラックス効果・血行促進・冷え性や肩こりなどに効くといった効果が期待されています。
大人にこそ、必要な効能ですね!
ぜひ大人にも菖蒲湯に入ってほしいといった理由、ご理解いただけたでしょうか?
赤 ちゃんや妊婦さんも菖蒲湯に入っていいの?
気になるアレルギー成分は?
さまざまな効能があるとはいえ、気になるのがアレルギーです。
菖蒲湯には、アレルギーを引き起こす成分は確認されていません。
ただし、かゆみやかぶれが出たという声もありますので、心配な方はやめておいたほうが良いでしょう。
では、赤ちゃんや妊婦さんの場合はどうでしょう。
赤ちゃんの場合
まず赤ちゃんですが、基本的には問題ありません。
しかし、生後3ヶ月くらいまでは入れないほうが良いとされます。
生後間もない赤ちゃんは肌のバリア機能ができあがっていないため、肌荒れを起こす可能性があります。
また、菖蒲の葉が直接触れることで、肌を傷つけてしまう恐れも。
入れる場合も短時間にとどめ、最後に体を洗い流しましょう。
妊婦さんの場合
一方、妊婦さんは菖蒲湯に入っても、何ら問題はありません。
注意したいのは、菖蒲とヨモギが一緒になった、菖蒲湯用のセットを購入する場合です。
ヨモギには、陣痛を促進する作用があります。
セットを購入する際には、ヨモギが入っていないことを必ず確認しましょう!
菖 蒲湯以外の菖蒲の使い方
菖蒲湯に入れない方は、その他の方法で香りだけでも楽しみましょう!
例えば5月4日の夜、菖蒲とヨモギを束ね、枕の下に敷いて寝る「菖蒲枕」 という風習があります。
これは菖蒲の強い香りでもって、邪気を払おうとするものです。
また菖蒲の根(茎や葉で代用)を刻み、30分ほどお酒に浸せば「菖蒲酒」の完成です。
こちらは解毒効果や殺菌効果が期待できるそうですよ♪
お子さんや妊婦さんは、お酒をお水に変えてくださいね。
菖蒲湯に入ろう!
家で入るのは面倒くさいかも…という方も必見!
菖蒲湯に入るために必要な準備や入り方、後始末の方法などをご紹介します。
菖 蒲はどこに売ってる?

菖蒲は端午の節句が近づくと、生花店・八百屋・スーパー・インターネット通販などで購入できます。
その際は、茎の付いたものを選びましょう。
根が付いたものがあればなお良いですよ♪
なぜなら効能のある成分は、根や茎の部分に含まれているからです。
また、5月5日当日は売り切れてしまうこともあります。
早めに購入し、冷蔵庫などに保存しておきましょう!
処分などを考えると菖蒲を買うのはためらわれるという方は、菖蒲湯の入浴剤を購入してはいかがでしょうか。
菖 蒲湯の作り方
菖蒲湯の作り方には、大きく2通りあります。
菖蒲をそのまま入れる方法と、菖蒲を刻んで入れる方法です。
(1)菖蒲をそのまま入れる方法
菖蒲の束(約5~10本)をそのまま湯船に入れるだけ。
菖蒲を空の浴槽に入れ、温度をやや高めにして給湯すると、より香りが高まります。
(2)菖蒲を刻んで入れる方法
まずは菖蒲を細かく切り、袋(ネットやお茶パックなど)に入れます。
菖蒲の入った袋を洗面器や耐熱性の器に入れ、熱湯を注ぎます。
10分たったら、袋と抽出した液を湯船に入れたら出来上がりです。
菖 蒲湯の入り方
大人だけなら、ゆっくりと浸かりたい菖蒲湯。
ですが、お子さんのいるご家庭なら、頭に細長い菖蒲をハチマキのように巻いてあげましょう!
菖蒲を頭に巻くと、頭が良くなる、頭痛にならないといった伝承があります。
菖 蒲湯に入り終わったら?
菖蒲湯に入り終わったら、避けて通れないのが菖蒲の後始末です。
束もしくは袋のまま処分する方が多いと思いますが、使用後の菖蒲を乾燥させれば芳香剤や虫よけになります。
残り湯も洗濯に再利用できますが、菖蒲の香りが残る可能性があるのでご注意くださいね。
菖 蒲湯祭り
菖蒲湯は、自宅でしか入れないわけではありません。
端午の節句の頃になると、菖蒲湯のイベントを開催する銭湯や温泉施設などもあります。
とりわけ盛大なのが、毎年6月4・5日(旧暦の端午の節句)に石川県・加賀温泉郷で行われる「菖蒲湯まつり」です。
菖蒲みこしの勇姿を見届けた後、温泉でゆっくりと菖蒲湯に浸かって1年の無病息災を願ってみてはいかがでしょうか。
菖蒲とあやめの違いとは?花菖蒲は別物!
これまで「菖蒲、菖蒲…」といってきましたが、皆さんはその姿をすぐにイメージできますか?
こちらが、菖蒲湯に使う菖蒲です。

え?花びらがないじゃないかって?
そうなんです。
菖蒲湯に使う菖蒲は、ガマの穂のようなごく小さな花を咲かせるサトイモ科の植物。
池や沼地付近など湿地帯に生息する多年草で、先が尖った葉っぱが特徴です。
この菖蒲には、名前が似ているため間違えられやすい植物があります。
ここでは、“あやめ”と“花菖蒲”との違いについてご説明しましょう。
菖 蒲とあやめの違い

こちらは「あやめ」の画像です。
「菖蒲」と書いて「あやめ」と読む場合があります。
サトイモ科の植物である菖蒲を「あやめ」と読むとは、ややこしい話ですね。
古来、あやめとは菖蒲を意味していたそうで、菖蒲は「あやめぐさ」とも呼ばれ和歌にも使われています。
時代が下ると、あやめは別の種を意味するようになりますが、読み方は残ったものと考えられます。
菖 蒲と花菖蒲は別物
また、菖蒲とよく間違えられるのが、名前の似た花菖蒲です。
花菖蒲を縮めて菖蒲と呼んでいるのかと思いきや、実はまったくの別物!
菖蒲がサトイモ科であるのに対して、花菖蒲はアヤメ科の植物です。

【左】菖蒲【右】花菖蒲
写真は、両者の花の様子です。
違いは一目瞭然ですね。
花菖蒲は美しい花を咲かせるのに対し、菖蒲はガマの穂のようなごく小さく密生している花を咲かせます。
一方、葉の部分はよく似ていると思いませんか?
葉が菖蒲に似ており、美しい花を咲かせるため、「花菖蒲」と呼ばれるようになったといいます。
おわりに
お風呂好きで知られる日本人が、古くから入ってきた菖蒲湯。
邪気を払うという“謂れ”だけでなく、効能もしっかりと認められています。
準備や後始末が面倒くさいという方もいらっしゃるかもしれませんが、やってみると意外と簡単に入れます。
ぜひ一度、いつもの入浴剤を菖蒲に変えてみませんか?

日本には毎月、菖蒲湯やゆず湯など、各月にちなんだ薬草や植物を入れる、季節湯という習慣があります。季節湯は日本の風土や伝統を由来としたものが多く、四季の移り変わりを肌で感じながら楽しむことができるのもその魅力です。今回は、12ヶ月の季節湯それぞれの由来と歴史・効能・作り方について詳しくご紹介します♪

日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。

祝日の中でも耳にする機会が多い「こどもの日」ですが、一体どんな日なのか、どのように祝うのか、実はよくわからないという方もいるのではないでしょうか?この記事では、そんな「こどもの日」について意味や由来、端午の節句との違いやお祝いの仕方を解説していきます!

みなさんは二十四節気という言葉を聞いたことがあるでしょうか?二十四節気とは、太陽の黄道上の視位置を24に等分しているもののことを指します。この24等分の一つに「冬至」があります。この記事では、冬至はいつなのか、かぼちゃとの関係や冬至にするといいことについてご紹介します。

酉の市とは、商売繁盛を願い毎年11月の酉の日に行われるお祭りです。今回は酉の市とは何か、その由来や歴史、楽しみ方に熊手の意味、有名な酉の市(新宿・浅草・横浜など)について、わかりやすく説明していきます!