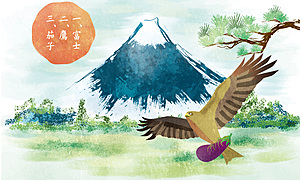立秋とは?暦の上では秋ってどういうこと?

「立秋」とは、毎年8月8日頃から次の節気の「処暑」までの15日間のことをさします。
この時期になると天気予報で「暦の上では秋ですが、暑い日が続くでしょう」というフレーズが聞こえてくる通り、まだまだ夏真っ盛りの気候が続く期間です。
ではなぜ、「秋」という言葉が用いられているのでしょうか?
そもそも「立秋」とは二十四節気の一つのことをいいます。
二十四節気とは、古代中国から伝わった季節の区分法で、おもに農作業の目安とされていました。
地球から見て太陽が移動する天球上の道である黄道を基準に1年を24等分して季節の移り変わりを示したもので、それぞれの節気を15日間隔でおいています。
この二十四節気をさらに3つの季節に分けて1年を72等分したものを七十二候といいます。
二十四節気の1つに対し、前半の「初侯」、中盤の「次候」、後半の「末候」の3つの七十二候からなります。
立 秋の意味と立秋頃の七十二候
立秋はこの言葉の通り「秋の気配が立つ」という意味で用いられています。
七十二候でもあるように、夕方になると秋の蝉といわれるヒグラシが鳴き始めたり、どこか秋を感じる風が吹いたりします。
また、立秋による身近な変化といえば、暑中見舞いが残暑見舞いに切り替わるタイミングでもあるということでしょう。
厳しい暑さから相手の体調などを心配してお見舞いする暑中見舞いに対し、なかなか終わらない暑さをお見舞いするものが残暑見舞いです。
しかし、残暑と言っても、ここ何年も暑さの厳しい日が毎年続いていますよね。
そこで今回は、立秋に食べたい旬の食べ物や日本古来の納涼方法、さらに立秋に行われる京都のお祭り「五山送り日」をご紹介します。

五山送り火とは、京都市で8月16日に行われる伝統行事です。京都の街を取り囲む山々で、5つの大規模な「送り火」が焚かれ、燃え上がる火で「大」「妙」「法」の文字と「船」「鳥居」の形が描かれます。この記事ではベストスポットや関連行事などをご紹介します。
立秋の時期に食べたい旬の食べ物
と ころてん

冷たく喉越しの良い、夏ならではの食べ物です。
平安時代に中国大陸から日本に伝えられ、当時は宮廷や貴族の人々が口にする贅沢な食品であったといわれています。
その後、江戸時代から庶民も 口にできるようになりました。煮溶かした海藻を冷まし固めてつくります。
食物繊維が多く整腸作用があるため健康食品としても人気があります。
三杯酢をかけてさっぱりといただきましょう。
ス イカ

スイカは園芸的には野菜、食品的には果物と言われています。
ちなみに、定義から言うと「木になる食用植物」が果物とされるので、スイカのほかにメロンやイチゴも果物ではないのでは?などという面白い話もあります。
日本で本格的な栽培がはじまったのは明治末期からです。
スイカは冷やすほどに甘みが増す特徴があるので、しっかり冷やしてからおいしく食べましょう。
と うもろこし

甘くておいしいため、子どもから大人まで人気のある夏の食べ物です。
収穫してから鮮度が落ちるのがとてもはやいので、なるべく鮮やかな色をした皮つきの採れたてを選ぶようにしましょう。
また、とうもろこしのヒゲが新鮮でふさふさとして、しっとりと乾燥していないものが良いそうです。
生のまま保存せずすぐに調理していただくのが良いとされます。

梅雨でじめじめ蒸し暑いとき、夏の暑さが厳しいときなどに「暑気払い」という言葉を聞いたことがあると思います。暑気払いは、夏の暑さに負けないように暑さを打ち払おうとする、日本に古くから存在する年中行事です。今回は、暑気払いでは何をするのか、暑気払いの時期や食べ物、納涼会との違いについてご紹介していきます!
日本古来の納涼の工夫

今でも有名な納涼の工夫として、道に水をかけてその場の気温を下げる打ち水や、氷水が入った桶に足を入れてからだを冷やすもの、涼しげな音で暑い夏をやり過ごすための風鈴などがあります。
さらに、今はクーラーや扇風機など便利なものがありますが、これらがなかった時代の人がどのようにして暑い夏をしのいでいたのかをご紹介します。
平安時代、貴族たちは山の涼しい所に別荘を設けて夏の間はそこで過ごすようにしたり、別荘まで行かなくても屋敷の庭の池にせり出した釣殿という建物で涼むことができました。
そこで新鮮な鮎や瓜、さらに冬の間にできた氷を夏まで保存しておいて食べることもあったといいます。
貴族が贅沢な納涼をしている中、各地の農村でも暑い夏に涼む時間を設けていました。
夏の真昼の一番暑い時間帯は、作業効率も悪く体調も崩しやすいため、この時間は仕事を中断して昼寝をしていたそうです。
夏は日が落ちるのも遅いため、仕事にも影響はなかったようです。
そうして仕事でかいた汗を行水でさっと流し、浴衣に着替えて夜風にあたるのが一番の納涼でした。
夜も蒸し暑くなってしまったこの時代から見ると、このような夏の過ごし方は何よりも贅沢な過ごし方に感じますね。
立秋にまつわる行事
五 山の送り火
立秋にまつわる行事の一つに、五山送り火があります。
五山の送り火は、立秋期間の中盤にあたる8月16日の夜に、京都で毎年行われます。
足元を照らし、お盆に招かれた祖先の霊が迷わないで帰れるようにしているのです。
東山浄土寺の如意ヶ嶽は「大」、松ヶ崎西山と東山は「妙法」、西賀茂船山は「船形」、金閣寺大北山は「左大文字」、北嵯峨曼荼羅山は「鳥居型」というように、市街を囲む5つの山に送り火の文字が浮かびます。
送り火の灯りを映した杯の水を飲み干すと、無病息災が叶うという風流な言い伝えもあります。
大 文字

午後8時頃になると、東山如意ヶ嶽に縦160m、横120mもの「大」の字が点火されます。
起源は諸説あり、疫病を払うために空海あるいは弘法大師が焚いた、足利義政が息子の義尚の冥福を祈るために焚いたなどと言われています。
妙 法

大文字の10分後に松ヶ崎西山と東山それぞれに「妙」「法」の字が点火します。
鎌倉時代末期に日像上人という僧が西山に「南無妙法蓮華経」の「妙」の字を書いたという伝説があり、「法」の字はのちに江戸時代の頃つけくわえられたと言われています。
約95㎡です。
船 形
妙法の5分後、盆に帰ってきた霊を送るための精霊船をあらわす船形の火が西賀茂妙見山に点火されます。
縦130m、横200mもの大きさです。
左 大文字
船形と同時に金閣寺大北山の「大」に火が灯ります。
東山如意ヶ嶽の左側に見えることから「左大文字」と呼ばれ、約68㎡の大きさです。
明治時代には大の字の上に一画加えて「天」という文字にしたこともあったようです。
鳥 居型

最後は北嵯峨曼荼羅山の鳥居形が点火されます。
この鳥居形は愛宕山の参道にある鳥居をあらわしたものと言われており、この鳥居形だけが他山と違って木を組むのではなく、松明をそのまま突き立てています。
大きさは縦76m、横72mです。

五山送り火とは、京都市で8月16日に行われる伝統行事です。京都の街を取り囲む山々で、5つの大規模な「送り火」が焚かれ、燃え上がる火で「大」「妙」「法」の文字と「船」「鳥居」の形が描かれます。この記事ではベストスポットや関連行事などをご紹介します。
おわりに
今回は立秋、そして立秋にかかわる旬の食べ物や風習について紹介させていただきました。
ぜひ旬の食材で栄養をつけ、日本ならではの納涼を試してみてください。
秋への準備期間である立秋を楽しみながら、残りの暑さを乗り越えましょう!

日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。

日本の伝統的な計算道具である「そろばん」。室町時代の頃に中国から伝わってきたといわれており、江戸時代に花開いた商業文化の中で日本に根付きました。この記事では、そろばんの歴史や種類、使い方をはじめ、そろばんに取り組むことによるメリットやそろばんを実際に見ることのできる展示施設まで紹介します。

毎年8月11日に制定された国民の祝日「山の日」。比較的新しい祝日なので、あまり馴染みがないという方も多いのではないでしょうか?この記事では、なぜ山の日は8月なのか、山の日が制定されるまでの歴史、山の日を楽しむ方法などをご紹介していきます!

社会人にとって、それはそれはうれしいお盆休み。いろいろな過ごし方がありますが、一ついえることは、日本人にとってお盆は特別な期間のようです。この記事ではお盆の意味や時期、過ごし方など基本的な知識についてまとめました。

日本では、ニュースなどからも防災についての意識を高める必要があることを実感させられます。そのような中、制定されている「防災の日」ですが、いつなのか、どんな目的や由来があるのかなどはあまり詳しく知らされていません。
そこで防災の日はどのような日なのか、制定されるまでの歴史や過ごし方などをご紹介します!

重陽の節句とは、いったいどんな日なのでしょう。現代では影が薄く、忘れられがちな重陽の節句。実はとてもおめでたい日なのです。今回は重陽の節句の意味や過ごし方について、簡単に紹介していきます。

お彼岸は、春のお彼岸と秋のお彼岸の2つがあり、どちらもご先祖様を敬う期間です。お彼岸に行うことといえば、お墓参りが一般的ですが、実はその風習が日本で生まれたものとご存じでしょうか?今回は、そんな秋のお彼岸とはどういった風習でいつの日程なのか、過ごし方や食べ物などをご紹介します。

最近は、各地でおしゃれなお月見のイベントも増えているようです。見るなら、絶対に中秋の名月がいいですよね?
ですが、ちょっと待ってください。中秋の名月って何ですか? 今回は知っているようでよく知らない、中秋の名月にまつわる基礎知識について簡単にご紹介します。