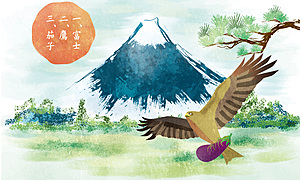2月は国民の祝日が2日あります。※令和5年(2023年)時点
天皇誕生日(2月23日)と建国記念の日(2月11日)です。
天皇誕生日は天皇の誕生日を祝うための日、と簡単に理解できますよね。
一方で建国記念の日とは何の日なのか、疑問に思ったことはありませんか?
「建国記念日」ではなく、なぜ「建国記念“の”日」なのか。
建国記念の日は、なぜ2月なのか?どのように過ごせばよいのか?
多くの方が休んでおきながら、建国記念の日について考えたことはあまりないのではないでしょうか。
こちらの記事では、そんな疑問にお答えしていきます!
建国記念の日とは

日本の建国記念の日は2月11日です。
年によって日にちが変わるということはなく、毎年2月11日であることが政令によって定められています。※令和4年(2022年)時点
国民の祝日に指定されているので、楽しみにされている方も多いでしょう。
といっても何のための休みなのか、よくわかりませんよね?
実は「建国をしのび、国を愛する心を養う」ための日なんですって。
名前から察するにそうなんでしょうね……と思う一方、日本という国ができた日だから休みなわけではないことも読み取れます。
この点は非常に重要ですので、以下で詳しく説明していきますね。
「建国記念の日」と「建国記念日」の違い
「建国記念の日」と「建国記念日」とでは意味が異なることをご存知でしょうか?
「の」があるかないかだけの違いではありません。
世界を見渡してみると、国が独立したり革命を達成した日が建国記念日になっていることが多いのです。
つまり「建国記念日」は国ができた日と言い換えられます。
建 国記念の日が2月11日になった理由
それでは、日本という国ができた日はいつでしょうか?
……答えは誰も知りません!
すなわち日本では、国ができた日を祝う建国記念日はありえないのです。
代わりに定められたのが、日本という国ができたこと自体を祝う日である「建国記念の日」でした。
ではなぜ、日本の建国記念の日は2月11日になったのでしょうか。
ずいぶん中途半端な日にちだと思いませんか?
その理由は戦前、紀元節と呼ばれていた日にあります。
「日本書紀」によると、初代天皇の神武天皇が即位したのは紀元※前660年の1月1日とされています。
※紀元:歴史上で基準となる年のこと。
神話の世界の話なのですが、明治時代にはこの出来事に基づいて紀元節という国家の祝日が制定されていました。
制定にあたり、問題となったのが暦です。
かつての日本は旧暦を使っていましたが、明治の日本では太陽暦を使っていたからです。
旧暦の1月1日は太陽暦に換算すると2月11日ということで、この日が紀元節になったと一般的にはいわれています。
世 界各国の建国記念日
建国記念日もしくはそれに相当する日がある国の多くは、植民地支配をしていた国から独立した日を記念日にしています。
例えばアメリカは、1776年にイギリスからの独立を宣言した7月4日を独立記念日(インディペンデンス・デー)としています。
もちろん独立以外の場合もあります。
フランスでは、フランス革命の発端である1789年のバスティーユ牢獄襲撃事件の日(7月14日)をパリ祭としています。
中国では、1949年に毛沢東が北京の天安門広場で国の成立を宣言した10月1日を国慶節としているのです。
建国記念の日はなぜ祝日になったのか?
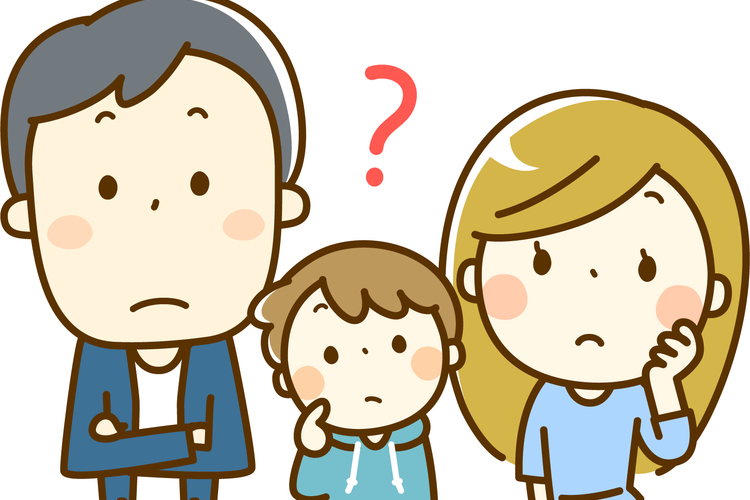
戦前に祝日だった紀元節は、もちろん現代の日本にはありません。
しかし、戦後に同じ2月11日が建国記念の日と制定されたことと、紀元節は無関係ではありませんでした。
G HQによる「紀元節」の廃止
第二次世界大戦で負けた日本は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の占領下に置かれたのはご存じのことと思います。
GHQは日本に対し、非軍事化・民主化のための占領政策をとりました。
それらの手段の一つが、紀元節の廃止だったのです。
紀元節は、かつて憲法の中で天皇を「神」としていた日本において、国家主義や軍国主義の高揚のために利用されていました。
例えば太平洋戦争の際には、紀元節である2月11日がシンガポール陥落の目標日にされたこともあったほどです。
そこで昭和23年(1948年)、紀元節は日本国憲法の理念にふさわしくないとして廃止されました。
建 国記念の日として復活
紀元節は廃止されましたが、2月11日は「建国記念の日」という名前で、国民の祝日として復活するのです。
昭和41年(1966年)に祝日法改正が行われ、翌年の昭和42年(1967年)に施行されました。
きっかけは国民から紀元節復活の声が上がったからです。
紀元節復活の動きに対し、もちろん国内でも反対意見が出ました。
国家主義・軍国主義が復活するのではないか。
そもそも神話を由来としているなんておかしいのではないか……。
そういった声もあり、法案はすんなりとは通りませんでした。
そこで「建国をしのび、国を愛する心を養う」日として登場したのが建国記念の日だったのです。
ただし、現在でも建国記念の日に反対する声があることは、知っておいたほうが良いのかもしれません。
建国記念の日のイベント・過ごし方
せっかくお休みの2月11日。
ゆったりするのも良いですが、建国記念の日らしさを感じる過ごし方をしてみたい方も多いはず。
歴史が浅いためこれといったしきたりはありませんが、例えばこんな過ごし方はいかがでしょうか?
奉 祝パレード(神宮外苑~明治神宮)を見に行こう!(東京都)
都内にお住まいの方なら、明治神宮周辺で行われる奉祝パレードを見に行ってはいかがでしょう。
パレードは神宮外苑いちょう並木通りを出発し、青山通りを経て、表参道ではお神輿と合流して明治神宮まで続きます。
パレードの参加者だけでも、例年6,000人を超えるというビッグイベントです。

明治天皇をお祀りする明治神宮では、玉串のお供えや国家斉唱などが行われます。
まさに「建国をしのび、国を愛する心を養う」日にピッタリのイベントですね!
神宮外苑~明治神宮周辺には素敵なお店がたくさんありますので、パレード後に立ち寄ればより充実した休日を過ごせそうです。
全 国各地のイベントに参加してみよう!
建国記念の日には神社を中心に、全国各地でイベントが開催されています。

例えば、奈良県の橿原神宮の紀元祭です。
橿原神宮の紀元祭には勅使(天皇の意思を伝えるための使者)が派遣され、例年数千名規模で盛大に行われています。
なぜ橿原神宮に勅使が派遣されるのかというと、日本の初代天皇である神武天皇が即位したのが橿原の地にあった大和橿原宮とされているためです。
まさに日本という国ができた場所といえますね。
橿原神宮以外でも、建国記念の日には全国の神社で紀元祭が行われています。
ご近所で開催している神社がないか、ぜひ検索してみてくださいね!
日 本について調べてみる
せっかくの休みの日にわざわざ外出するのは面倒くさい!
そんなインドア派の方へオススメなのは、日本について調べてみることです。
例えば「古事記」や「日本書紀」という本の名前は聞いたことがあっても、二つの違いを説明できる方は少ないのではないでしょうか。
また日本の歴史を海外の方に説明するとしたら、どんなストーリーを紹介したらよいのでしょう。
意外と難しいですよね。
普段はなかなか考えない日本のこと、建国記念の日に改めて調べてまとめてみませんか?
おわりに
神話の世界の出来事に由来すること、かつて国家主義・軍国主義を支えてしまった紀元節の存在……。
日本の建国記念の日にはいろいろ事情があったことが、おわかりいただけたでしょうか?
反対の声もある建国記念の日ですが、自分が生まれた国を愛すること、それ自体を否定するものではありません。
建国記念の日にはぜひ、日本という国に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。

2019年11月14日、15日の二日間にかけて執り行われる「大嘗祭」と呼ばれる重要な儀式は、天皇陛下にご即位後、初めて行われる宮中祭祀というだけでなく、一世一代限りのとても珍しい儀式です。

平成31年(2019年)4月30日。30年間天皇陛下としてお勤めになられた明仁上皇陛下がご退位されました。その時に行われた「退位礼正殿の儀」は、みなさんの記憶にも新しいのではないでしょうか。世界中が注目した明仁上皇陛下の天皇としての最後のお姿を、私たち国民もテレビ中継を通して観ることができましたよね。

令和元年(2019年)5月1日に行われた、「剣璽等承継の儀」を含む即位礼は、現在の明仁上皇陛下が天皇陛下の位をご退位(譲位)し、今上天皇が”天皇”の地位を受け継いだ形となったため、江戸時代の光格天皇以来、202年ぶりのとても珍しいケースとなりました。

みなさんは二十四節気という言葉を聞いたことがあるでしょうか?二十四節気とは、太陽の黄道上の視位置を24に等分しているもののことを指します。この24等分の一つに「冬至」があります。この記事では、冬至はいつなのか、かぼちゃとの関係や冬至にするといいことについてご紹介します。

皆さんは「節分」と聞くと何を思い浮かべますか?保育園や幼稚園、小学校で豆まきをして鬼退治をした!なんて思い出がある人も多いのではないでしょうか。今回の記事では、節分とは本当はいつ行うものなのか、由来や歴史、豆をまく理由、行事食などをご紹介します。

スポーツの日は、毎年10月の第2月曜日に制定されている、国民の祝日の一つです。「体育の日」の名で馴染み深い、という方も多いのではないでしょうか。本記事では、そんなスポーツの日の令和6年(2024年)の日程や由来、名称変更の理由や過ごし方までご紹介します!