
出典:(公社)ひょうご観光本部フォトライブラリー
全国的にも有名な有馬温泉や城崎温泉、世界文化遺産に登録されている姫路城など、多くの魅力的な観光資源を保有する兵庫県。
バラエティに富んだ気候や風土から“兵庫県は日本の縮図”とも言われています。
そんな兵庫県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、25品目以上の伝統工芸品が存在します。
この記事では、その中でも経済産業大臣によって兵庫県の「伝統的工芸品」として指定されている、播州そろばん、丹波立杭焼、出石焼、播州毛鉤、豊岡杞柳細工、播州三木打刃物をご紹介します。
経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。
要件は、
・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること
・日常生活で使用されていること
・主要部分が手作業で作られていること
・一定の地域で産業が成り立っていること
本記事の内容は、令和4年(2022年)2月時点のものです。
掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

「姫路城」は、兵庫県南西部に位置する姫路市の姫山と呼ばれる高台にあり、日本三大名城の一つです。別名「白鷺城」とも呼ばれ、白亜の天守群が青空に翼を広げた白鷺のように優美な姿で親しまれています。この記事では、国宝でありユネスコ世界文化遺産にも登録されている姫路城の歴史や伝説、逸話、見どころなどをご紹介します♪
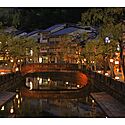
城崎温泉の楽しみ方は、7つの外湯を中心とした温泉巡りだけではありません!
情のある街並みや、海鮮料理、松葉ガニや但馬牛などの美味しい食事を楽しむこともできるんですよ♪そんな魅力いっぱいの城崎温泉を満喫できる、オススメ観光スポットを厳選して紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

日本三名泉の1つである兵庫県の『有馬温泉』は、日本最古の温泉として有名で、年間を通して多くの観光客が訪れる人気の温泉街です♪そんな有馬温泉には宿泊施設や日帰り温泉だけでなく、湯泉神社や炭酸泉源公園など、温泉にちなんだ観光スポットがたくさん!今回は、そんな有馬温泉の歴史や泉質、周辺観光スポットをご紹介します!
播州そろばん
「播州そろばん」は、兵庫県南部(播州と呼ばれる地域)の小野市を中心に作られている伝統的なそろばんです。
そろばんは室町時代末期に中国から長崎県を経由して、滋賀県の大津に伝わりました。
安土桃山時代、豊臣秀吉の三木城(現在の兵庫県三木市)攻めに際して、大津に逃れた三木の住民たちが、そろばんの製作技法を習得して地元に持ち帰り製造をはじめたことが、播州そろばんの起源とされています。
100を越える製作工程は専門の職人たちによって分業化されており、繊細な手作業から生まれるそろばんは、使いやすさや珠はじきの良さはもちろん、美術品としての美しさも備えています。

古くから身近な計算道具として親しまれてきた「そろばん」。小学校で出会ったという方も多いのではないでしょうか。電卓やパソコンの発展とともに一度は衰退しましたが、近年、能力開発ツールとして再び脚光を浴びています。今回は、そろばんの国内シェアNo.1を誇る「播州そろばん」の歴史や特徴、魅力などについて詳しく解説します!

日本の伝統的な計算道具である「そろばん」。室町時代の頃に中国から伝わってきたといわれており、江戸時代に花開いた商業文化の中で日本に根付きました。この記事では、そろばんの歴史や種類、使い方をはじめ、そろばんに取り組むことによるメリットやそろばんを実際に見ることのできる展示施設まで紹介します。
丹波立杭焼
「丹波立杭焼」は、兵庫県篠山市今田周辺で作られている、日本六古窯※の一つにも数えられる陶器です。
平安時代末期頃に誕生して以来、主に湯呑や皿、鉢といった生活容器が多く作られてきました。
焼成過程で薪の灰を被り、釉薬と溶け合うことで生まれる“灰被り”という独特の色・模様や、器の表面を削って稜線模様を作る“しのぎ”という技法が特徴です。
※日本六古窯:日本古来の陶磁器窯のうち、中世から現在まで生産が続く代表的な6つの産地の総称
素朴な風合いや美しい発色が印象的で、観賞用としても人気の高い焼き物です。
出石焼
「出石焼」は、兵庫県豊岡市出石地区で作られる磁器です。
国内で生産される磁器の中でも、珍しいほどの透きとおるような白さが特徴で、“これこそ磁器中の磁器”と言われるほどです。
諸説ありますが、天明4年(1784年)に伊豆屋弥左衛門が出石町に土焼窯を開いたことが出石焼の起源だといわれています。
その後、寛政11年(1799年)に周辺の柿谷で白磁の原料となる陶石が発見され、本格的な磁器製造がはじまりました。
明治時代以降は、繊細で華麗な彫刻や、絵付けが施された器が作られるようになりました。
現在の代表的な製品は花器や茶器で、菊の花などの模様を掘り込んだものが典型となっています。
播州毛鉤
「播州毛鉤」は、兵庫県西脇市周辺で製造されている魚釣り用の毛鉤です。
毛鉤とは疑似餌※の一種で、虫に似せて作られています。
天保年間(1830年~1844年)に京都から播州へ製作技法が伝わった後、農家の副業として生産されるようになりました。
1cm足らずの鉤に数種類の鳥の羽を巻き付け、金箔や漆によって仕上げられる播州毛鉤は、釣り具として精巧なだけでなく、芸術性も高い逸品です。
現在は、国内で生産される毛鉤の9割が西脇市周辺で作られており、多くの釣り人が愛用しています。
※疑似餌:魚釣りの際に用いる、普段魚が食べない物で人工的に作られた餌のこと。
豊岡杞柳細工
「豊岡杞柳細工」は、兵庫県豊岡市周辺で作られている柳のかご細工です。
豊岡市を流れる円山川周辺に自生するコリヤナギなどを編み込んで作られ、衣類などを収納する箱である柳行李やかごバッグが代表的な製品として知られています。
起源は弥生時代にまで遡るとされ、天日槍命という朝鮮半島の新羅という国の王子が、日本に柳細工を伝えたことにはじまるといわれています。
その後、江戸時代に豊岡藩主・京極高盛が杞柳細工を保護奨励したことをきっかけに、全国的に広まっていきました。
自然素材を活かした優しい風合いと、丈夫さや軽さなどの実用性が魅力です。
播州三木打刃物
「播州三木打刃物」は、兵庫県三木市周辺で生産されている刃物です。
“打刃物”とは、炉で熱した金属をハンマーで打つことで形作られる刃物のことで、日本刀などと同じ製法で作られます。
播州三木打刃物が発展するきっかけとなったのは、天正6年(1578年)からはじまった羽柴(豊臣)秀吉による三木城攻め(三木合戦)です。
焼け野原となった三木の町の復興のため、大工職人や大工道具を作る鍛冶職人が集まったことにより、大工道具の生産が盛んになりました。
ゆえに、播州三木打刃物では特に大工道具が有名で、鋸・鑿・鉋・鏝・小刀の5品目が伝統的工芸品に指定されています。
その他の伝統工芸品
| 工芸品名 | 概要 |
| 播州そろばん | 読み:ばんしゅうそろばん カテゴリ:文具 主要製造地域:小野市 指定:国 |
| 丹波立杭焼 | 読み:たんばたちくいやき カテゴリ:陶磁器 主要製造地域:丹波篠山市 指定:国 |
| 出石焼 | 読み:いずしやき カテゴリ:陶磁器 主要製造地域:豊岡市 指定:国 |
| 播州毛鉤 | 読み:ばんしゅうけばり カテゴリ:その他の工芸品 主要製造地域:西脇市、丹波市 指定:国 |
| 豊岡杞柳細工 | 読み:とよおかきりゅうざいく カテゴリ:木工品 主要製造地域:豊岡市 指定:国 |
| 播州三木打刃物 | 読み:ばんしゅうみきうちはもの カテゴリ:金工品 主要製造地域:三木市 指定:国 |
| 大阪唐木指物 | 読み:おおさかからきさしもの カテゴリ:木工品 主要製造地域:大阪府大阪市、貝塚市、門真市、摂津市、枚方市、柏原市、東大阪市、兵庫県姫路市、洲本市、たつの市、淡路市、東浦町、奈良県奈良市、葛城市、和歌山県有田市、福井県越前市 指定:国 |
| 有馬の人形筆 | 読み:ありまのにんぎょうふで カテゴリ:文具 主要製造地域: 神戸市 指定:県 |
| 有馬籠 | 読み:ありまかご カテゴリ:竹工品 主要製造地域:神戸市 指定:県 |
| 兵庫仏壇 | 読み:ひょうごぶつだん カテゴリ:仏壇 主要製造地域:加古川市 指定:県 |
| 杉原紙 | 読み:すぎはらがみ・すいばらがみ カテゴリ:和紙 主要製造地域:多可郡多可町 指定:県 |
| 明珍火箸 | 読み:みょうちんひばし カテゴリ:金工品 主要製造地域:姫路市 指定:県 |
| 姫革細工 | 読み:ひめかわざいく カテゴリ:その他の工芸品 主要製造地域:姫路市 指定:県 |
| 城崎麦わら細工 | 読み:きのさきむぎわらざいく カテゴリ:その他の工芸品 主要製造地域:豊岡市 指定:県 |
| 丹波布 | 読み:たんばふ / たんばぬの カテゴリ:織物 主要製造地域:丹波市 指定:県 |
| 名塩紙 | 読み:なじおがみ カテゴリ:和紙 主要製造地域:西宮市 指定:県 |
| 美吉籠 | 読み: みよしかご カテゴリ:竹工品 主要製造地域:三木市 指定:県 |
| 赤穂雲火焼 | 読み:あこううんかやき カテゴリ:陶磁器 主要製造地域: 赤穂市 指定:県 |
| しらさぎ染 | 読み:しらさぎぞめ カテゴリ:染色品 主要製造地域:姫路市 指定:県 |
| 姫路仏壇 | 読み:ひめじぶつだん カテゴリ:仏壇 主要製造地域: 姫路市 指定:県 |
| 和ろうそく | 読み:わろうそく カテゴリ:仏具 主要製造地域:西宮市 指定:県 |
| 姫路独楽 | 読み:ひめじこま カテゴリ:木工品 主要製造地域:姫路市 指定:県 |
| 姫路張子玩具 | 読み:ひめじはりこがんぐ カテゴリ:その他の工芸品 主要製造地域:姫路市 指定:県 |
| 王地山焼 | 読み:おうじやまやき カテゴリ:陶磁器 主要製造地域: 丹波篠山市 指定:県 |
| 丹波木綿 | 読み:たんばもめん カテゴリ:織物 主要製造地域:丹波篠山市 指定:県 |
| 三田鈴鹿竹器 | 読み:さんだすずかちっき カテゴリ:竹工品 主要製造地域:三田市 指定:県 |
| 播州鎌 | 読み:ばんしゅうがま カテゴリ:金工品 主要製造地域:小野市 指定:県 |
| 播州山崎藍染織 | 読み:ばんしゅうやまさきあいそめおり カテゴリ:織物 主要製造地域:宍粟市 指定:県 |
| 淡路鬼瓦 | 読み:あわじおにがわら カテゴリ:その他の工芸品 主要製造地域:南あわじ市 指定:県 |
| 赤穂緞通 | 読み:あこうだんつう カテゴリ:織物 主要製造地域:赤穂市 指定:県 |
| 稲畑人形 | 読み:いなはたにんぎょう カテゴリ:人形 主要製造地域:丹波市 指定:県 |
| 皆田和紙 | 読み:かいたわし カテゴリ:和紙 主要製造地域:佐用郡佐用町 指定:県 |

日本には、各土地に古くから受け継がれてきた多くの伝統工芸品が存在します。全国で230品目以上ある伝統的工芸品。今回は、日本の歴史の中で長く政治や文化の中心地であった、近畿地方の伝統的工芸品45品目をご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

粘土を成形し、高温の窯などで焼成し器や造形物を作ることを陶芸と言います。
火山の噴火によってできる岩石が長い年月をかけ砕かれ、有機物と混ざりあったものが粘土。
世界中に存在しています。
陶芸によって作られる陶磁器と呼ばれるものにはおおまかに2種類あり、土が主な原料で叩いた時ににぶい音がするのが「陶器」。

金工とは金属に細工をする工芸、あるいはその職人のことを指し、金属を加工して作られる工芸品のことを金工品と言います。日本に金属とその加工技術がもたらされたのは、弥生時代初期、紀元前200年頃のこと。中国大陸・朝鮮半島から伝わった金工技術によって剣や銅鐸、装身具などが作られ、材料として青銅や鉄が使われていました。

「一枚…二枚……」
悲しげな女の幽霊が、夜ごと井戸に現れては皿を数える……という怪談、番町皿屋敷。古くから知られている怪談話の一つですが、幽霊となった女は誰になぜ殺されたのかと訊かれたら、答えられますか?この記事では、知っているようで意外と知らない「番町皿屋敷」について解説します。

日本の伝統的な計算道具である「そろばん」。室町時代の頃に中国から伝わってきたといわれており、江戸時代に花開いた商業文化の中で日本に根付きました。この記事では、そろばんの歴史や種類、使い方をはじめ、そろばんに取り組むことによるメリットやそろばんを実際に見ることのできる展示施設まで紹介します。




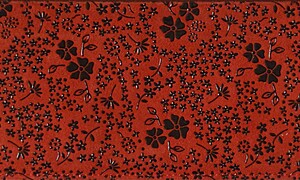









![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)













![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)





















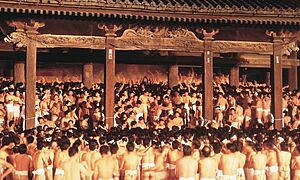











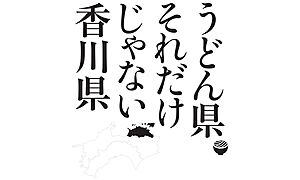













![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)


![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)
![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)





![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2024年6月15日~19日](/uploads/article/image/1122/eyecatch_24107622-f100-4f1a-a93c-af21c3dbdb58.jpeg)





