古くから日本で受け継がれ、洗練された美しさと実用性を兼ね揃える日本の伝統的工芸品。
そして、長い年月をかけて技を習得し、その伝統的工芸品の歴史を守り伝える「伝統工芸士」。
日本の伝統的工芸品を後世へと守り伝えていくためにも、ぜひ彼ら匠の仕事や素晴らしさを広めていきたいですよね。
この記事では、伝統工芸士とは何か、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。
伝統工芸士とは

日 本の伝統工芸士は国家資格
日本の伝統工芸士は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて行われる、伝統工芸士認定試験に合格した職人のみが名乗ることを許される国家資格です。
認定されている伝統工芸士の数は、令和2年(2020年)2月の段階で3,912人と決して多くはありません。
伝統工芸士は、その伝統的工芸品を制作するための技を磨き、作品を作り上げ、そしてその技と伝統的工芸文化を後世に語り継ぐ役割を担っています。
現在、日本及び全世界では、電気自動車や5Gなどの新たな技術が目にもとまらぬ速さで生まれ、その利便化とグローバル化は留まるところを知りません。
そのような中で、500年、1000年と大切に守られてきた伝統的工芸品をこれからも存続させるためには、こういった伝統に対する真心と探究心に満ちた伝統工芸士の存在は必要不可欠なのです。
伝 統工芸士の種類
伝統工芸士の種類をご紹介する前に、「伝統工芸品」と「伝統的工芸品」について簡単にお話したいと思います。
まず、「伝統工芸品」と「伝統的工芸品」はどちらも名前が似ていますが、実は指すものが異なります。
「伝統工芸品」は、古より受け継がれてきた技術を用いて作られる、日本の工芸品のことを広く指します。
それらのうち、“伝統的工芸品産業の振興に関する法律”に基づいて認められた伝統工芸品を「伝統的工芸品」と呼びます。
そして、当記事でご紹介する「伝統工芸士」は、後者で示した伝統的工芸品に携わる職人のみがなることを許されています。
また、全国の伝統的工芸品に指定されている工芸品は下記の通りです。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。
伝統工芸士になるには

では、伝統工芸士になるには一体どうすれば良いのでしょうか?
ここからは、伝統工芸士になるために必要なことをご紹介します。
伝 統工芸士の受験資格
伝統工芸士になるには、資格試験を受ける必要があります。
伝統工芸士の試験は、「受験したい!」と思ったときにすぐに受けられるものではありません。
一級建築士やパイロットのように受験資格をクリアし、自分の実力を証明する必要があります。
伝統工芸士の資格試験を受験するためには、
実務経験を12年以上積み※、かつ原則的に産地内に居住しており、現在もその工芸品を作るための作業に従事している
必要があります。
認定業種は多くあり、織物や染色品、仏壇・仏具、人形などは“意匠”や“仕上”などの工程ごとにも細かく分けられています。
※実務経験年数は、各産地組合で独自の規定を設けていることもあり、工芸品によって異なる場合がある。
伝 統工芸士試験
伝統工芸士の試験は、知識試験と実技試験に分けられます。
知識試験では、伝統的工芸品についての一般知識を問う問題と、技術や技法、原材料や歴史などの専門性を問う問題が用意されています。
実技試験では作業場での工程科目と、主宰側が規定する材料で、規定の作品を作り上げます。
伝 統工芸士としての認定・登録
合格率およそ65%の試験に晴れて合格したら、産地委員会を通して登録申請を行います。
試験を合格してから約2ヶ月後に「伝統工芸士」として登録されるので、その後は培ってきた知識と経験を活かして日本の伝統文化を守る一員となります。
また、国が認める伝統工芸士のほかに、東京都指定伝統工芸士や奈良県伝統工芸士のように、各自治体が独自に認定している場合もあります。
奈良県では令和2年(2020年)3月に吉野手漉き和紙の職人が夫妻揃って県伝統工芸士に認定され、新聞記事になるなど話題となりました。

古くから愛されてきた銀器。
その歴史は古く、現在日本では東京が主要な産地となっている。
「東京銀器」は昭和54年に経済産業大臣より伝統的工芸品として指定され、台東区や荒川区を中心に、アクセサリーや日用品など幅広い銀製品が作られている。
東京都台東区浅草に工房を構える銀泉いづみけんもその一つだ。

東京都墨田区に工房を構える、むさしや豊山。明治元年に創業して以来150年、墨田区の下町で江戸押絵羽子板を作り続けている。今回は、むさしや豊山五代目の当主となる野口豊生氏に、江戸押絵羽子板の魅力や、職人となったきっかけなどを詳しく伺った。

埼玉県越谷市に工房を構える柿沼人形。
1950年に東京で創業し、二代目である父の柿沼東光氏が広さを求めて埼玉に工房を移した。東京都の伝統工芸品「江戸木目込み」の技法を使い、主に節句人形を製造している。伝統を守りつつ、10年20年先を見据えた他にない唯一のものを作ろうと、本物志向で挑戦を続けている。

東京都新宿区高田馬場に東京手描友禅のアトリエを構える小倉染芸。
格調高く、深い色合いの作品が特徴である。
取材させていただいた隆氏の師匠である父の貞右(ていゆう)氏は、多数の賞を受賞し、上皇后美智子妃殿下の訪問着を作った経験もある。
この度は、平成30年に伝統工芸士を取得した3代目の小倉隆氏にお話を伺った。

東京都荒川区、南千住に工房を構える畠山七宝製作所。ここでは東京都の伝統工芸品「東京七宝」のデザイン・製作が行われている。今回は七宝焼き職人畠山 弘氏の工房で話を伺った。
女性の伝統工芸士
伝統工芸士や工芸職人というと、今まで男性職人のほうが圧倒的に多く、女性で活躍されている職人は多くありませんでした。
しかし平成10年(1998年)には430人だった女性伝統工芸士も、令和2年(2020年)には621人に増加しており、今後もますます女性伝統工芸士の誕生が期待できます。
女 性伝統工芸士展
伝統的工芸品産業振興協会は、毎年「女性伝統工芸士展」を開催しています。
女性伝統工芸士展は、女性ならではの審美眼を通して紡がれる伝統的工芸品の魅力を多くの人々に伝え、次の時代へ語り継がれることを願って開催されています。
令和2年(2020年)の当展示会は、社会情勢を考慮し残念ながら中止となってしまいましたが、来年以降はまた開催されると思いますので、ぜひ一度足を運んでみてください。
なお、令和2年(2020年)は6月17~22日までの6日間、福岡で信州紬や伊万里・有田焼、博多人形などの種類豊富な作品が一堂に集まる予定でした。

大正12(1923)年創業の清水硝子で働く中宮涼子さんは、江戸切子初の女性伝統工芸士。
今回は、職人になったきっかけや一つ一つの作品に込められた想い。
この仕事をしている上でのこだわりなどを詳しく伺った。
伝統工芸士や伝統工芸品に触れてみたくなったら
伝統工芸士や伝統工芸品についてもっと知りたいと思ったときは、各地にあるギャラリーやサテライトショップに足を運んでみると、多くの発見が得られるでしょう。
伝 統工芸 青山スクエア
青山スクエアは、日本全国で守り育まれてきた伝統工芸品を一度に堪能できるギャラリー&ショップです。
作品見学はもちろん、気に入った木細工や焼き物などをその場で購入できるところが魅力的です。
住所:〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目1-22 1F
営業時間:11:00~19:00 ※日によって短縮営業の場合あり(詳細は公式サイト要確認)
定休日:年中無休 ※年末年始を除く
K YOTO in TOKYO presented by 京都館
京都館は、東京都内で京都の伝統工芸品を見ることができるアンテナショップです。
ここでは京都が誇る伝統工芸品74品目およそ500点を展示しており、随時和文化にフィーチャーしたイベントも開催しています。
東京駅八重洲中央口から徒歩1分の立地なので、東京駅に立ち寄る際に覗いてみてはいかがでしょうか。
住所:〒103-0028 東京都中央区八重洲2-1-1ヤンマー東京ビル1F
営業時間:10:30~19:00
定休日:12月30日~1月3日、3月と9月の最終水曜日
全 国各地の博物館
伝統工芸品を持つ多くの自治体で、それらの保護と紹介を目的とした博物館・美術館を開館しています。
こけしで有名な宮城県では「みやぎ蔵王こけし館」や「日本こけし館」が、輪島塗の匠が集まる石川県では「輪島塗会館」、「石川県輪島塗漆芸美術館」などがあります。
「(居住地域名)伝統工芸 博物館」などで検索すると、国内に80館以上あるミュージアムの中から、お住まいの近くの伝統産業に関する博物館が簡単に探せますよ♪
おわりに
伝統工芸士は「技術の習得に時間がかかる」、「売上の減少により工房側が後継者を育てられない」などの理由で、後継者不足が問題視されていました。
そのため長らく存続の危機に瀕していましたが、近年では和紙がユネスコ無形遺産に登録されるなど、伝統文化産業が改めて注目されるようになりました。
現在では、伝統工芸を守ることの大切さを受け、美術系大学や職業訓練校で伝統工芸の専門技術を学ぶ場も増えてきています。
伝統工芸品や伝統工芸士に興味が湧いたら、伝統工芸を学ぶことができる学校のオープンキャンパスに参加したり、ギャラリーや展示会に足を運んで、日本文化の息吹を間近に感じてみていただけたら幸いです。

東京メトロのCMでおなじみ、“Find my Tokyo”でも掲載されている「松崎大包堂」さんでの「江戸木版画」体験レポートです!

ワゴコロ編集部が全国の伝統工芸体験を紹介していくワゴコロ体験レポート。今回は、“江戸風鈴製作体験”をしに、江戸川区にある「篠原風鈴本舗」さんに行って来ました!

ユネスコは、国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)のことです。本記事では、日本で登録されているユネスコ無形文化遺産を一覧でご紹介します。




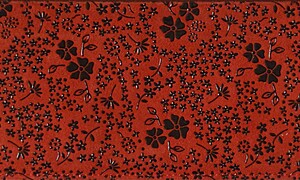









![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)
![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)













![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)






















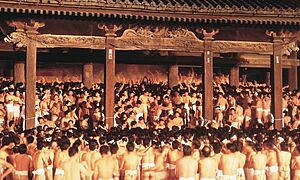











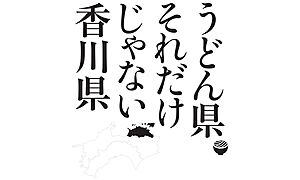













![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)


![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)
![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)





![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2024年6月15日~19日](/uploads/article/image/1122/eyecatch_24107622-f100-4f1a-a93c-af21c3dbdb58.jpeg)





